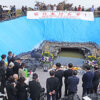| 岩国市在住の吉田松陰研究家・折本章氏の「高杉晋作と奇兵隊」と題する講演が5日、下関市の桜山会館でおこなわれた。桜山神社での奇兵隊祭の一環として青年神職会が主催した。 折本氏は冒頭「全国に名をはせた郷土の偉人がしだいに若い世代に忘れられようとしていることをひじょうに残念に思う。その生き方を次世代に働きかけ、ついでいくことは有意義なことだ」とのべた。 また、「萩と下関でいえば、高杉にとって萩は静で、下関は動であったといえる。萩では静かに精神を練っていく部分が多く、これといった活動をしていない。大きな活動というのはみな下関だ。亡くなるときも吉田、吉田といって亡くなったという話もある。自分の骨は下関に埋めてほしかったのだと思う」とのべて本題に入った。 折本氏の講演の要点はつぎのとおり。 生涯の師・松陰との関係 松陰は松をひじょうに愛した。「松下陰深きところ更に人有り」。自分はいまは陰にあるけれどもやがて大きなエネルギーとなってあらわれるということを暗示しているようだ。松は寒風に、風雪にさらされてもいつも青青としている。つまり生気を失わない。自分は松のように生きたいというのが、松陰の願いだった。 高杉は梅を愛した。春が来たら一番先に花を咲かせる。高杉は機先を制するところがあり、人生の先を見ぬいてどっと咲くところがあった。 このことは、松陰の不屈の精神、高杉の先見の明を象徴しているように思う。 松陰はみずからを「二十一回孟士」といっているが、二人の共通性は猛挙、狂挙に示される。どちらも義に従って突きすすむ。正しいと思ったらそれを突きすすんでいく、損得とか生命とかを考えないで、とにかく理想にむかって突きすすむことが大事だと思っていた。 高杉は松陰から「生きた学問」を学んだ。晋作がつくった詩に、「百年一夢の如し/何を以てか歓娯を得ん/自ら笑う平生の拙/区々として腐儒を学ぶ」というのがある。明倫館に行っていたときにつくった詩で、人生は長くても百年だが、夢のように過ぎ去ってしまう。なにをもって喜びや楽しみを得たらいいだろうか。それなのに、自分はせっせとして錆びついた学問を明倫館で学んでいる。なんとも笑うべきではないか。明倫館では講義形式で字句の説明をしたり、書いてある本の説明をしたりで、いわば死の学問だと晋作は思っていた。 松陰はいつも、君ならどうするか、今日ならどうするかということをつねに問いかけていた。本を読んでもこの本に描いてあることは昔のことであるが、このことを今日ならどうするかということをつねに訴えかけていた。だからいまなにをなすべきかということが焦点になっていた。晋作は学問の真価を教えられる。 晋作はどこへ行ってもまわりから頭を抑えられていた。ところが松陰はそれを少しも抑えなかった。それをむしろすばらしい才能としてもっと伸ばそうとしていた。ただ松陰は、方向性を考えた。つまり社会に役立たない方向に伸びていったのでは意味がない。高杉の頑固なところを社会の有用な方向に伸ばしていきたいというのが松陰の狙いだった。そして、松陰がいったとおりに高杉がなっていく。 松陰には平等な人間観があった。士農工商は身分の違いではなく、職業上の区分であると教えた。松下村塾には、魚屋や農家、坊さんとかいろんな人が集まってきた。松下村塾は縦の関係ではなく、横の関係で結びついているから、協力的なムードであった。 高杉は、松陰から死生観を学んだ。これはひじょうに大きな影響を晋作に与えた。「潔いという死は無意味」と松陰は教えている。当時の武士は失敗すれば腹を切ればすむと思っていた。高杉はそれはまったく無意味だ、犬死にはしないと、いざというときは逃げ回り、紆余曲折しながら自分の命を長引かせて、最後に大きなことをした。松陰は「心死すれば生くるも益なし、魂存すれば身滅ぶるも損なきなり」、心が生きていれば、体が死んでも意味がある。反対に、体が生きているが心が死んでしまったのでは、まったく生きる意味がないと教えた。 「生きて大業の見込みあらばいつでも生くべし。死して不朽の見込みあらばいつでも死すべし」高杉はこの言葉をかみしめて生きぬく。 奇兵隊創設の経緯 ペリーが来て和親条約を結べといい、ハリスが来て通商条約を結べという。幕府は迷いに迷う。そこで朝廷にお伺いを立てるが、天皇の許しが得られなかった。当時の大老・井伊直弼は勅許を待たずに、条約を結び、激怒した尊皇攘夷派に桜田門で暗殺される。 朝廷と協定を結べば尊皇攘夷派を少しは抑えられるのではという公武合体派が、手段として天皇の妹である和宮を幕府に降下させる。 長井雅楽の「航海遠略策」は、条約を破棄してもうまくいかないから、それはそれで認めよう、あらためて朝廷から幕府にたいして命令を下して、各藩に伝達すればいいというものだ。これは実質的には幕府の思いになった。形のうえでは、朝廷が幕府に命令を下すということで身分の上下があることがはっきりした。当面は幕府も朝廷も大喜びで長井雅楽に報償を与える。これはのちに朝廷をないがしろにしたということになった。 松陰門下の久坂玄瑞、桂小五郎、高杉晋作らがこれに猛反対して、公武合体はだめだ、条約を破棄して攘夷するのだという「破約攘夷」が盛り上がっていく。攘夷祈願のために天皇が加茂神社、あるいは石清水八幡宮に祈願する。そして、攘夷期限を5月10日と定めた。長州では外国艦隊を砲撃する。そのときはむこうは軍艦ではなく普通の商船だった。これを追い払って、大喜びするが、六月にはすぐ仕返しがあって、長州はやられてしまう。 そういう流れのなかで、郷土を防衛しなければならないということで奇兵隊を創設するにいたった。晋作の熱烈な祖国愛が、なんとかして国を救おうとして奇兵隊の結成になった。 高杉が奇兵隊の結成を思いついた動機は、松陰の草莽崛起論、つまりいまでいえば官職にあるもの、公の職についているものは、やはり自分の地位や名誉がほしいから、なかなか勇敢にたたかうことはできない。だから官職にあるものはだめだ。役についていない自由な身の人、農民とか漁民とかを草莽といった。 従来の武士は大砲の音を聞いて馬から落ちるなど、ふがいなかった。久坂玄瑞の光明寺党の奮斗に見るように、下級武士たちは勇敢にたたかった。僧月性の農兵論もあった。それから、天保一揆のひじょうに大きなエネルギーがあった。晋作が生まれるちょっとまえのことで、その話を聞いていた。さらに、上海渡航の経験がある。それから晋作の天性、なにかをヒントにして新しいものがひらめくというのがあった。そういうものが総合されて奇兵隊の結成を思いついたと思う。 功山寺決起について 高杉晋作の大きな事業をあげるなら、奇兵隊の結成と功山寺決起の二本柱だと古川薫先生もいっている。功山寺決起は高杉の先見の明がもっともよくあらわれている。高杉は俗論党に追われて九州に逃げるが、俗論党が幕府のいいなりになって長州はつぶれてしまうという危機感を持って帰って来る。そしてここで決起しようじゃないかと説く。 情勢は幕府の軍がとりまいている。俗論党との対戦がある。外国艦隊が攻めこんでくるという情報も入っている。そういうときに立とうといっても意味がない、負けるのは、決まっていると、普通の人間なら考える。山県たちもそう思っていた。 そのとき高杉は「一日の遅れは百歩の後退だ」といっている。わたしはこれを初期消火にたとえて解釈したい。火事が起きているんだ。その火事はいま消せばなんとか消える。だがもう一時間おけば火の手はどんどん上がって消せない。長州はつぶれる。後世に汚名を残すじゃないか、立つときはいまだと熱烈に説くが、つうじなかった。そこで高杉はわずか80名前後の兵を率いて立った。 このときに、松陰の死生観が出てくる。「武士の一死は、泰山よりも重く、或は鴻毛より軽きにおけ」。高杉は、いまが松陰のいう鴻毛のときだと決意する。 この決起について賭けか、信念かといわれる。普通のものは賭けだったというだろう。だが高杉には信念があった。高杉はたくさんの民衆がいるが、みな正義派に味方しているか、正義派に近い、俗論は嫌っていると見ていた。だからだれかが旗を振ったら迷っているものがかならず寄ってくると思った。旗を振る役を高杉が担った。それで民衆がなびいてきて、奇兵隊も立ち上がり、諸隊も立ち上がって、俗論政府を倒した。 赤根武人もまじめな人だが、俗論党と正義派を調停して一つにまとめようとした。高杉はこれは絶対にだめだといっている。幕府のいいなりになっている俗論になにが正義派と合体できるか、水と油だ。絶対にわかるはずがないのだ、と説いている。そういう先見の明はほんとうにすばらしいと思う。 |