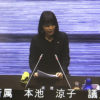昨年8月1日から始まった本紙「下関市立大学トイレ改修工事損害賠償請求事件についての調査報告書」の連載は、半年近くにわたって全20回を数え、昨年末に最終章を迎えた。本稿を書くにあたり、全部の記事に再度じっくり目を通した。事件の内容、その後の経緯、さらには問題点の整理に至るまで、微に入り細にわたって叙述されているので、ここで委細を繰り返すことはしない。丹念な事実の積み重ねによって、真相の究明に尽力された方々に敬意を表したい。
一般論として、損害賠償を求める場合、たとえそれが法律にかなった正当な金額であっても、債務者の弁済能力を超える金額に固執して、1円も回収できない事態に陥るよりは、減額して確実な金額で妥協する、という選択はあり得る。そういう和解はよくあることで珍しくない、とも聞いている。本件の場合、市立大学の経営責任者が現実的な判断をすることは、あり得たのかもしれない。
しかし、今回の損害賠償は、個人が求めた損害賠償ではない。市立大学は、個人の資金で運営されているのではない。大雑把に言って、大学収入の約九割は学生の授業料などの納付金であり、残りの一割が下関市からの運営費交付金である。したがって、そもそも経営責任者が、学生および保護者に、そして、下関市、下関市議会、下関市民に、説明責任を負っているのは明らかである。この点で、和解の秘密条項が、その説明責任から逃れる都合のいい口実になっている、と疑念をもたれても仕方がないだろう。
他方で、メディアにも報道され、市議会でも取り上げられているのに、この間、当事者の大学内部から一言も発言がないのはどうしたことか、市立大学の先生たちは、この問題についてどのように考えているのか、という声があるとも聞いている。先生たちは、発言できないのではなくて、発言しないのである。というのも、すでに声を挙げてきているからである。
2016年11月29日付のA新聞下関版に、「市立大「健全運営を」教員ら市議会に請願書」という見出しの記事が掲載されている。そして、いくつかの請願内容の一つとして、「理事長らの任命は、公正で民主的な大学運営を進める能力のある人材を選ぶ」ことが書かれている。その後、市議会での請願採択は叶わなかったと聞いているが、少なくとも市立大学の先生たちは声を挙げてきているのである。
それにもかかわらず、市立大学を取り巻く様子は相変わらずのように見える。損害賠償の処理も大事だが、本当の問題は、なぜそのような事件が起きたのかという点にある。本稿では、市立大学の来し方を振り返り、その行く末を考えたい。
◇
どうしてこんな市立大学になってしまったのか。一つの契機は、2007年の「法人化」だったのではないか。公務員の削減という国策の中で、市立大学の法人化もやむを得なかったのかもしれない。当時、学内には、市役所の部局から切り離されて、むしろ本来の「大学」になれるのではないか、という前向きの期待や受け止めもあった。
新たに傘下の法人理事長ポストが一つ増え、定年後の再就職先に気を揉んでいる市役所の方たちには朗報だったに違いない。しかし、逆に大学は、新たに法人の「役員報酬」を負担しなければならなくなった。しかもそれ以上に深刻だったのは、市役所から切り離されるとともに、市役所のガバナンス(健全運営の仕組み)からも切り離されたことだった。市役所の部局では不可能だったことも、法人化した大学では自由裁量に委ねられる。そういう仕組みになっているのではないか。期待された本来の「大学」の姿はどこかへ吹き飛んでしまった。
「法人化」以前にも問題がなかったわけではない。いわゆる大学財政の問題である。国から下関市に交付される「地方交付税交付金」の積算根拠として、市立大学の「学生数」がカウントされている。それにもかかわらず、毎年度の下関市の大学予算には、その相当額どころか、公費がほとんど算入されていない。経常費だけを見れば、学生の授業料などの納付金だけでまかなわれている。いわば「自主財源率100パーセント」の大学である。「公立大学」とは名ばかりで、実態は「学生立大学」だとも言われた。このような大学財政の状態は、法人化の前まで続いていた。
要するに、市立大学は、下関市が国からお金をもらうための「道具」に過ぎない。下関市には、高等教育行政(大学行政)の理念や組織はない。国立大学には文部科学省があるが、下関市にはそれに相当する部局はない。窓口は総務部である。それはちょうど、総務省が国立大学を担当しているようなものである。そのため、下関市は市立大学を、高等教育の視点ではなくて、地方自治の視点から、つまり市の「財源」としてしか見ることができない。
最近になって、国のこの積算根拠の考え方が怪しくなってきた。つまり、単純に「学生数掛けいくら」ということではなくて、「大学授業料無償化」とか、「実務系教員の採用」とか、「研究者でない理事」とか、そういうことが国からの交付金の積算に関係してくるのではないか。「地方創生」への貢献度が反映されるような仕組みになるのではないか。そういう見方もある。下関市としては、これらの時流を先取りして、強引にでも市立大学の将来計画を策定する必要があるのだろう。市の「財源」の死活問題になるからである。
ただし、市立大学をそういう「道具」として利用できるのも、市立大学が存続してこそ可能になる、という点を見落としてはならない。
◇
市立大学は、「財源」として下関市の財政に貢献し、市民生活を豊かにすることに役立っている、という見方もあり得るかもしれない。しかし、「事件の現場」になることだけは、まっぴら御免である。「大学」は教育の場であり、将来を担う若者たちが全国から集う場である。少なくともこの下関で、彼らにそういう「現場」を見せたくない。コンプライアンス(法令遵守)の欠如は、大学の問題以前の話である。
しかし、たとえこれまでそうだったとしても、今後の「希望」の余地はある。現在の下関市には「大学」としての高等教育の理念はないが、かつての下関市はそうではなかったからである。六十年余りさかのぼって、市立大学の設立の原点を想起すべきである。
1950年代、下関市内にあった山口大学の経済学研究所の「夜間大学講座」を受講していた学生たちが、下関市議会に「夜間短期大学」設立の請願書を提出し、市議会で採択された。そして、下関市の行政や産業界の後押しによって、1956年に夜間課程の「下関商業短期大学」が開学した。その後、後援会や同窓会などの尽力によって、1962年に4年制の「下関市立大学」が誕生したのである。
しかし、市立大学の歩みは平坦ではなかった。開学直後から下関市の財政状況は危機的状況に陥っており、当時の市長は、市議会で「市立大学をつくったことは失敗であった、いずれ県立か国立に移管すべき」であると述べ、その後も、「国立移管が難しいので、私学移管もありうる」と述べている。これに対して、学生たちは、授業料値上げ反対、私学移管反対などを掲げて、デモやストライキを決行している。当時の学長は、市議会で「あえて開学させたのであるから、市大を存続させるべき」であると発言し、教授会も私学移管に反対の表明をしている。結局、下関市は「地方財政再建準備団体」として財政再建への途を開き、下関市立大学は、父兄の後援もあって私学移管を免れ、今日に至っているのである。

「私学移管反対」「授業料値上げ反対」を掲げてデモ行進や署名活動をする下関市立大学の学生の行動を報じる本紙(1966年2月16日付)
「学びたい」という学生たちの声に、下関市の行政、財界、産業界、さらには市民が一丸となって応えたのが、「下関市立大学」の設立だったはずである。だからこそ、財政危機による私学移管の問題も乗り越えられたのではないか。下関市には、市立大学に対するそういう熱い思いがあったはずである。もう一度、「建学の原点」に立ち返って、今後の市立大学のあるべき姿をしっかりと見通すことが必要である。
さて、市立大学の一員として、いま、あえて繰り返し学外に発言したいことは、次の四点である。市立大学を「事件の現場」にしないでほしい。「学生」のことをまず第一に考えてほしい。大学教員を学生の「教育」とその基礎である「研究」に専念させてほしい。教育と研究を支えている事務職員の処遇に目を向けてほしい。この四点である。これらのことが叶うだけで、市立大学の行く末に「希望」がもてるはずである。
最後に、いまの市立大学に求められているのは、長期展望に立って「学生」と「大学」のために意思決定のできる経営責任者、すなわち「公正で民主的な大学運営を進める能力のある人材」であることは言うまでもない。