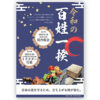(2025年4月14日付掲載)

人々が会場いっぱいに詰めかけた「ごはん会議」(12日、富山市)
れいわ新選組が鈴木宣弘氏(東京大学大学院特任教授)を講師に迎え、全国各地でおこなっている「ごはん会議」が11日と12日、福井県福井市と富山県富山市で開催された。福井県はコメの大産地であり、コシヒカリを産んだ県でもある。また富山県は米騒動発祥の地であり、現在は水稲種もみの生産量と県外出荷量が日本一の「種もみ王国」として全国のコメ生産を支えている。全国的なコメ不足により価格が高騰し高止まりするなか、政府の備蓄米放出も「焼け石に水」の状態で、コメの生産量が圧倒的に不足していることが露呈している。すべての国民にとって直接的で最重要課題である「食」の危機が可視化されるなかで、多くの人々が日本の食料安全保障の問題について関心を高めている。全国のごはん会議では、そうした消費者の問題意識と、生産に従事する農家の問題意識が響き合い、熱い議論が交わされている。

挨拶するれいわ新選組の八幡愛㊨、阪口直人両衆議院議員
開会に先立ち、れいわ新選組の阪口直人衆議院議員が挨拶に立ち、ごはん会議を全国で開催する目的と意義について、以下のようにのべた。
ごはん会議は、農業の問題についてじっくり考えるということが大きな目的だ。また今、トランプ大統領の関税の問題、コメの高騰の問題などを通して食料問題への関心がとても高まっている。私たちは、農業を国際的な競争に晒すのではなく、しっかりと守っていかなければならない。
また、日本には今、他国では許可されていないような安全基準の低い食べ物がどんどん入ってきている。そうした現状を認識し、賢い消費者としてどう対応すべきかということを考えていきたい。
日本の安全保障における最大の要は食料安全保障だ。どんな国でも農業を大事にしているが、日本政府は農業を売り渡し、自動車などのより国際競争力があるモノを海外に売り込んで経済発展を遂げてきた。そうした流れを変え、まずは食料、農業を守るための政策転換が必要だ。
ごはん会議を主催しているのはれいわ新選組だが、「れいわ新選組」という名前は大きく出していない。食の安心や食料安保問題は、右も左も、政党の争いもなく、とにかくみんなで考えていくものだからだ。そうやってれいわの仲間を増やしながら、各地域でも、国でも私たちの考えを前に進めていきたい――。
続いて挨拶したれいわ新選組の八幡愛衆議院議員は、「私は国会の農林水産委員会で毎日のように質問している。とにかく日本のコメが大変なことになっている。都内では今、冗談抜きでブレンド米しかなく、カリフォルニア米ばかりが店頭に積み上がっている。なぜこんなことになっているのかと江藤農林水産大臣を追及している。食の安全や自給率向上は、与野党関係なく“やるしかない”というテーマなはずだが、それなのに今はどんどん農林水産予算が削られ、これだけコメが不足しているのに海外放出を進めたりと、農林水産委員会はおかしなことをやっている。みなさんと一緒に勉強していきたい」とのべた。
富山の会場で挨拶したれいわ新選組の多ヶ谷亮衆議院議員は、「昨日(11日)、5年ごとに変更される食料農業農村基本計画が閣議決定された。その内容を見てみると、今コメの値段が1俵2万円だが、これを“9500円の低コストを目指す”という。そして5割以上の事業者が15㌶の農地を耕作することを目指すという」「大規模化を進めてきた農家はすでに限界まで拡大している。それでも国は中山間地などは無視して相変わらず大規模化を進めている。このままでは本当に国は滅びる。アメリカは余った農産物を国が買いとっている。それは輸出でもうけるためなどではなく、何があっても自国民を飢えさせないためだ。それこそが安全保障だからだ。日本はその真逆をやっている。国民の命も守れないのならそれはもう国家とは呼べない。なぜ日本がこうなっているのか、みんなで一緒に考えていきたい」とのべた。
対米従属構造に根源 鈴木宣弘教授の講演

鈴木宣弘教授
鈴木宣弘氏は、170枚以上ある資料のデータをすべて参加者にQRコードで共有し、それらを使いながら約1時間にわたって現在の食料問題や農政の問題について講演をおこなった。講演のなかでは、現在のコメ不足の問題や政府の備蓄米放出、さらにこの期に及んで政府がコメの輸出量を増やそうとしていることなど、食をめぐって日本国内で起きている現在の問題についても触れて解説した。以下、内容の一部を紹介する。
日本の食料自給率がなぜこれだけ下がっているのかということを考えてみると、すべて今回のコメ騒動の問題に繋がっている。アメリカの占領政策の下、アメリカで余ったたくさんの農産物を日本人に食べさせるために、日本ではコメ以外の農産物の関税がどんどん撤廃され、日本の麦や大豆、トウモロコシは一度壊滅状態になった。さらには「日本人の食生活を改善させる」という名目で、日本人がコメを食べないようにし、アメリカの農産物に依存せざるをえない状況が作られ、日本国内での減反政策にも繋がった。それが今回の米騒動にも繋がっている。
アメリカを喜ばせるために食料の関税を次々に撤廃し、日本は自動車でもうければいいんだという政策がとられ続け「食料なんてカネを出せばいつでも輸入できるんだ」「これが日本の食料安全保障だ」というかのように、自動車中心の製造業でもうける体制がとられてきた。今回も自動車輸出を守るために、コメの市場を開放するという話にまでなってきている。こんなバカなことをまだ続けるのか。
農家がコスト高で生産量が減るなかで、これから先、海外からの輸入が止まったら私たちは子どもたちの命を守れるのか。今の日本はいざというときに国民の命を守ることのできる「独立国」といえるのかということが厳しく問われている。
令和の米騒動が一向に収まらないのには、根本的な原因がある。それは現場の農家を苦しめる政策をやってきたからだ。農家がどれだけ赤字でも補填せず、「余っているから作るな」「毎年10万㌧ずつ減らせ」といい、最近では「田んぼなんかいらない。潰せば手切れ金だけは出してやる」とまでいいだした。現在の大変な状況は、生産が減りすぎていることが根本原因だ。それなのに国は間違いを認めず、国は「悪いのは流通だ」「誰かが投機のために隠している」という。
だが先日、農水省が「買い占め」の犯人捜しの調査をやった結果、隠されていたコメは1万㌧もなかったことがわかった。それでもまだ「コメは足りている」といい続け、生産量の不足を認めない。
農家が増産できるような対策を打たないから根本問題が解決できない。そればかりか、今度はコメの輸出量を八倍に増やすために、輸出向けの作付けに対しては10㌃当り4万円の補助金を支給するとまでいいだしている。仮に10㌃で8俵収穫できるとすれば、60㌔当りの補助金額は5000円だ。それだけの補填ができるのなら、今こそその補助を主食米生産に充ててコメ不足の改善をやるべきだ。増産すればコメの値段が下がるのが不安かもしれないが、仮に1俵1万5000円に下がったとしても、補助金で5000円足せば2万円になる。こういうことを政策として打ち出して増産しなければならない。
もう一つ、輸入米の問題もある。コメの値段が高くなるなかで、輸入米がどんどん増えている。1㌔当り341円という大きな関税があるから入ってこないといわれてきたが、その関税を乗りこえて入ってきたとしても、5㌔当り3000円くらいなので、安く売れるようになっている。「輸入米で良いじゃないか」となってきているなかで、そこにアメリカが食い込もうという上手いストーリーができている。
アメリカは「日本のコメの関税は700%もある」などとふっかけてきているが、実際はそんなにない。これから交渉が始まろうとしているが、前トランプ政権のときに、他の国が断るなか日本だけは「自動車関税を25%にする」と脅されて、当時の茂木大臣は会見で「アメリカが日本車の関税を引き上げないかわりに、日本は農産物の関税を下げる提案を用意した」などといい、牛肉と豚肉の関税を引き下げ、生け贄にした。
そして、今残っているのは本丸であるコメと乳製品だ。これをアメリカが狙っている。今後さらにアメリカから自動車の関税引き上げで脅され、下手すれば「コメだって差し出します」という話になってくる。基本戦略など何もなく、まともに交渉もできない。とにかくアメリカにしっぽを振って付いていくだけの外交戦略だから、日本独自の主張がまるでない。アメリカ依存から脱却し、日本がどうやって国際社会で生きていくのかをみんなで考えないといけない。
どう立て直すか 質疑応答から

参加者との質疑応答も熱を帯びる「ごはん会議」(12日、富山市)
鈴木氏の講演の後、参加者との質疑応答をおこなった。参加者からは、消費者の立場から食の安全や食料自給と安定供給の課題、さらに生産者からは農業に関わる具体的な質問や問題意識が語られた。「食」や「農」という身近なテーマを入り口にして現状の課題を直視し、その根底にある国民の命や生活を無視した日本の政治の問題として議論を深める場となっている。
質問(福井) 今年の夏までコメはあるのだろうか?
鈴木 すでに2024年産米がどんどん流通して先食いされており、夏頃までに本当になくなってしまう可能性がある。2025年産米の作付けも、前年度比1・8%くらいしか増えないといわれており、非常に心配な状況だ。政府はとりあえず備蓄米をどんどん出すといっているが、備蓄米そのものがどれだけ残っているのかも怪しい。そこにアメリカの輸入米を増やすというストーリーまでできあがっていくとなると恐ろしいことだ。だからこそ、農家が増産を頑張れるような政策を早急に打ち出さないと根本問題は解決しない。このままでは本当に農家がコメを作れなくなり、今の米騒動は終わらないどころかもっとひどくなる。
質問(福井) 輸入米には、防カビ剤などもたくさんかかっているのか?
鈴木 その通りだ。収穫後、船で運ぶときにカビが生えないようにどうしても防カビ剤をかけないといけない。だがこれは日本では禁止農薬であり、本来なら海に棄ててもおかしくないものだ。しかし日本政府はこれを食品添加物ということにして流通している。そして今は国産米と米国産米を混ぜてブレンド米として売っている。
八幡愛 イオンが積極的に発売する「二穂の匠」というコメは、米国産8割、日本産2割のブレンド米だ。そのことを国会で質問した後、全国各地の売り場にブレンド米が増えていることなど、実情が事務所に届くようになった。パッケージはいかにも日本風の見た目だが、国産米よりも若干安い。私がスーパーに行ったときに、高齢の方が「安くなってる」といってブレンド米を買おうとしていたので、「ブレンド米ですよ」と伝えると、驚いていたが結局は「でも仕方ないか」といって買っていた。これからはブレンド米が主流になっていくのではないかと思うと怖い。
質問(福井) 食料自給率には、「カロリーベース」と、「生産額ベース」の2種類あり、先生はなぜカロリーベースを元に話をしているのか?
鈴木 カロリーベースと生産額ベースにはそれぞれ役割がある。生産額ベースとは、日本の農家の皆さんがさくらんぼなど付加価値が高いものを作って、売上が上がるように頑張って経営をしているというとりくみを見るうえで重要な指標だ。しかし、海外からの輸入が止まって食べるものがなくなったときに、自分たちの体を動かすエネルギーを調達するためには、カロリーを生み出す作物が自国でどれだけ生産できているかが大事になる。つまり食料危機などに対処することを考える場合は、カロリーベースの食料自給率が必要になる。
一方、海外では、カロリーベースの自給率を計算するのが面倒なので、穀物自給率を用いている。日本の穀物自給率は28%で、カロリーベースの自給率(38%)よりもさらに低い。人によっては「カロリーベースなんて意味がない。生産額ベースで見るべきだ」などという人もいるが、最終的にどれだけお金があっても札束は食べられない。指標を使い分けることは重要だが、カロリーを生み出す穀物がどれだけ自給できるかということを考えないといけない。
質問(福井) わが家は米屋で、いつも祖父が空を見ながら天候の心配をしていたのを見て育ってきた。農家がいくら生産してももうからない状態はおかしいと思う。もっと農家がお金をかけず、高い機械など使わなくとも農業ができる方法はないのだろうかと思う。また、農家ではない自分たちも、あちこち余っている土地や農地を使って自分の家族分くらい生産できる方法はあるのではないかとも思う。
なぜ農家が成り立たぬ 切実な質問相次ぐ
鈴木 みずから生産に関わっていくことは非常に重要なことで、高い機械を買わなくても地産地消のとりくみは拡大できるはずだ。今、農家が大規模化して大きな機械を購入すると国から補助金が出るが、機械そのものが非常に高額で、いくら補助金をもらっても、実は自分で普通の機械を買った方が借金をせずに済んだのにということもめずらしくない。
また、いろいろ予算をつけても、しっかりと農家に届いていないという実情もある。私は政府の「食料・農業・農村審議会」の畜産部会の座長を務めていた。2008年に起きた国際的な穀物相場の高騰による「エサ危機」に対して農家救済のために4千数百億円の緊急対策予算を決定したが、そのうち酪農家に届いたのはわずか100億円だった。4000億円の予算が途中で消える。中間には農水省の天下り組織や、機械や施設を作る企業などもすべてぶら下がっており、そういう部分に予算が流れて農家に届かない。
質問(富山) 砺波市の農家の多くは、コメの時期以外はチューリップを育てている。コメ農家が少なくなると、チューリップ農家も少なくなる。私もチューリップの球根の組合に入っていて、そこでスマート農業のことが話題にあがっている。「スマート農業があれば、農家が少なくなってもサポートすることができる」なんて話も聞く。だがスマート農業の機械はとても大きく、実際に砺波の小さな田に出入りしたり道を行き来するのも大変で、手作業でした方が早いという場面も多々ある。
鈴木 「機械化してスマート農業にすれば上手くいく」なんて簡単な話はないし、機械屋がもうかるためにやっているだけではないかと思えてならない話もたくさんある。機械を使う農家ではなく、その機械を作ったり売る業者のもうけのために補助金をつけて、やたら高い機械にして農家の借金ばかり増えるという構造ができ、関連業者がお金だけ持っていってしまう仕組みがかなりある。輸出にしても、農家の手取りが増えるのではなく、輸出企業がもうかるような仕組みになっている。そんなことが多すぎる。いかにも農家のために予算を付けたように見えて、本当は農家のためになっていないようなものがたくさんある。スマート農業もそういう側面があると思う。
質問(福井) 私は農家で、個人ではやっていけないので父が農業法人を立ち上げ、集落営農で大規模農業をやっている。コンバインなども1台1000万円かかる。個人で小規模に農業をやるというのはとても難しく、全体で集まって法人化し、補助金をもらってなんとかやっていけるという状態だ。国があてにならないというのもよく分かるが、なぜ国はこれほど間違った政策を続けるのだろうか。農業に限らず、経済対策や少子化対策などすべてが間違った方向に向かっていると感じる。
鈴木 政治家は利権で繋がっているし、自分にお金を入れてくれる人がもうかるように優遇することばかり考えて、みんなが幸せになることなど関係ない。みんなからむしりとって、みんなの健康を害しても構わないという利権構造が問題であり、そこを断ち切らないといけない。一気に変えることは難しいが、また選挙もあるので、みんなで政治を変えていくしかない。
質問(富山) 40代の若い農家の友人が、経営が立ちゆかなくなり、金融機関からもお金を借りているなかでどうすればいいだろうかと相談を受けた。その件について農協の職員との話し合いに私も同行した。事業計画を立て、融資額を決めて融資タイミングを決めたのは金融機関であり、経営が立ちゆかなくなったから、計画を見直すための話し合いをするのかと思っていたら、農協は「あなたは農業をやめたら一括返済になりますよ」と脅してきた。農協も有機栽培の生産者を支援するようなコミュニティを作ることはできないのだろうか?
鈴木 本来農協が何をすべきかということをよく考えないといけない。共同販売によって農家の価格交渉力を高めるという点は農協の重要な役割だが、一方でどうやって農家を支え、販路も含めたコミュニティを作っていくかということについて、農協はもっと関わっていくべきだと思う。
一つ例をあげると、JAやさと(茨城県)では、農家が農地、技術、資金、売り先を確保できるようにと、農地を提供し、技術支援をして最終的に販路まで確保するとりくみをしている。そのために農協がたくさんの生協に依頼し、販路を確保している。仕組み作りに力を入れる農協がもっと増えてほしいと思っている。農協にはいろいろな問題もあり、改善してみんなの役に立つ組織にしていかないといけない。
借金の問題については、農協に限らず、お金を貸している農業系の金融機関が、農家を突き放すようなことをやって苦しめているという例をいくつも耳にしている。とくに酪農家では、2014年にバターが足りないからということでクラスター事業でどんどん借金してでも規模を拡大し、増産してくれという呼びかけのもと、生産者も増産を進めた。
そして、やっと軌道に乗ったと思ったところで、国から「もう乳を搾るな。牛は殺せ」といわれて、結局酪農家の手元に残ったのは借金だけだった。首が回らなくなった結果、千葉、北海道、熊本などで何人もの酪農家が命を絶ったという話も聞いた。生産者を支えるために、政治、行政も含めて何ができるかを考えていかないといけない。今はそれがまったくできていないから、生産者がどんどん追い込まれてしまっている。
政治の変革求める 会場での参加者の声

鈴木宣弘氏の講演を聴く参加者(11日、福井市)
福井、富山両会場とも多くの参加者がつめかけた。農家も多数参加し、現在直面している生産現場での人手不足や高齢化などに対する問題意識を語った。また、誤り続ける日本の農政を厳しく批判するとともに、現在可視化されている食料安全保障の危機を転換するためにも、一刻も早い政治の変革を求める声があいついで聞かれた。
70代の米農家の男性は「消費者の人たちが高いコメを買わされ、将来の食に不安を抱いている今の状況は、生産者として本当に心苦しい。日本の農政は絶対に間違っている。今でも大規模化を進め、それに対して補助金を出すという方向だが、日本の少ない耕地面積でいくら“効率化”といったところで、アメリカやオーストラリアに勝てるわけがない。補助金のために大規模化して何千万円もする農機具を購入して多少効率化できても、規模が大きくなればその分肥料の高騰などのリスクも大きくなる。一方で、減反政策によって中山間地から田をなくし、どんどん集落が消滅していっている。今私がいる地域もあと5年もすれば地域として成り立たなくなるだろう」と語った。
また「“生産性”や“競争力”など、私たちは求めていないし、何か特別なことをして補助をもらって自分だけもうかることも望まない。そうではなく、消費者が生きるために安心して安全な食料を食べられることこそが一番の願いだ。農家が生産したものを、みんなに喜んで食べてほしい。だが今はあまりにも流通、販売者側の都合が現場に押しつけられていると感じる。それではだめだ。持続可能な農業とは、生産者と消費者が互いに尊敬し合い、支え合える関係性が成り立ってこそ実現できるものだと思う」と語った。
30代のコメ農家の男性は「法人化して地域の農地を集約して大規模化し、機械も大きくしてコメを作っている。実際に、作業の効率化は進み、少ない人手でより広い面積で稲作をできるし、週末に飲食店をやりながら今は家族が食べていけるだけの収入は得られている」という。ただ、今の状態がいつまで続くかという不安はかなり大きく、「高齢化は本当に深刻だ。集落営農も70~80代の農家さんが中心でやっているので、5年先に今の規模での農業が続けられるかも怪しく、いずれ自分たちの代だけが残されたときに、農地を守るのは難しくなる。いずれ山際の農地は手離す他ないだろう。草刈りも重要な仕事で、地域には十数人の草刈り専門の部隊があり本当に助かっているが、メンバーはみな高齢者だ。草刈り部隊がいなくなると、残った農家で今以上に広い農地で稲作をしながら、草刈りまで自分たちでやらないといけない。今は獣害を防ぐために、田と山林の境界にある農地以外も草刈りしてもらっているが、そうした部分の手入れも難しくなるだろう。いくら大規模化といっても、集落に人手がいないと農業はできない。今は法人化による集落営農が増えているが、このまま放置していれば集落単位で稲作が消えていくことになる」と話していた。
40代の建設会社経営者の男性は「食は、人間にとってもっとも必要なものであるにも関わらず、それをないがしろにして衰退に任せている今の日本政府は絶対に間違っている。自分の子どもが大人になったときに、果たしてまともに食べていける社会が存在しているのだろうかと思うと不安だ。建設業界も他人ごとではない。資材高騰で、利益が出ずに賃金を払えず、人材流出は加速。人手不足で仕事が回らなくなり、休日も働かなければならず、余計に人が集まらない。まさに悪循環だ。他の業者では何人も外国人を雇い、経費を抑えてなんとか経営を続けているが、本当にこのままでいいのだろうか。日本人をどう育てていくかということがこれからの日本社会にとって重要なテーマになってくると思うが、今それができなくなっている。今日生きていくためには、知らず知らずのうちに“今だけ、カネだけ、自分だけ”に流れてしまう社会に向かってしまっている気がして、危機感を感じている。今この流れを変えないと、数年で日本は今以上に廃れてしまうと思う」と話していた。
弁当屋で働いているという男性は「コメも高騰しているが、野菜も値上がりしているし、魚も漁獲量が減り以前のように安くはなくなった。コメは200㌘のパックを、今年2回に分けて100円から150円に値上げした。その他のおかずも値上げしないと経営が成り立たない。より良い食材を使って、調理して付加価値を付けて売って利益を上げたいが、一方で、店には生活保護や高齢の客も来る。うちの弁当や惣菜がライフラインになっており、そういった人たちにこれから食を提供していくことも社会的な使命だと思っている。これだけ食料の値段が上がってコメまで手に入らないというなかで、誰もが食の危機が迫っていることを実感していると思う」と語った。
また、ごはん会議に参加して生産者の話などを聞き、「食は、人間の生きがいの基本だと思う。また、農業の魅力とは、食を支え、どんなに歳をとっても地域のため、家族のため、消費者のために自分が体を動かして草刈りひとつでも誰かの役に立てることだと思う。農業を通じて地域の人たちが元気になる。だが今、農村集落そのものが維持できなくなっており、一方で農業そのものが利益、効率、競争といったまったく逆の方向に向かっていると思う」と話していた。