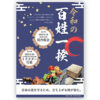(2025年4月2日付掲載)

全国各地から集まった30台のトラックが都心を行進した(3月30日、東京都港区)

各都道府県の幟の下、農家など4500人がデモ行進をおこなった(3月30日、東京都)
「農家に欧米並みの所得補償を! 市民に安心して食を手にできる生活を!」を掲げ、3月30日、東京都内で「令和の百姓一揆」がおこなわれた(主催/令和の百姓一揆実行委員会)。戦後農業の基礎を築き、食料生産を支えてきた農家の高齢化と離農が急速に進み、とくに稲作農業が壊滅状態に追い込まれている。「食と農と命を守り、食料自給率を高めるため、農政の質的大転換をつくり出そう」という呼びかけに呼応する動きは実行委員会の想定をこえて広がり、全国から個性豊かなトラクター約30台、農家や市民約4500人が集まって東京都内を行進しながら沿道の人々に「食と農を守ろう!」とアピールした。東京都内をはじめ全国14カ所での同時開催となった「令和の百姓一揆」は、コメ不足と価格高騰が深刻化するなかで、農業立て直しに向けた大きなうねりが全国各地で起こっていることをあらわした。
3月30日午後2時、集合場所の青山公園(東京都港区)には、「農家は日本の宝」「食糧価格の安定 若者も農業ができるような制度に!!」「百姓滅びて民飢える」「農家は希望」「お米大好き」など、多彩な手作りプラカードを携えた人々が続々と集まってきた。
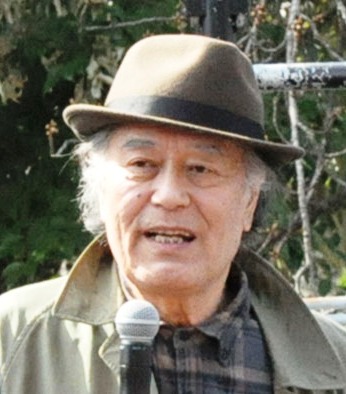
菅野芳秀氏
出発にあたり、同実行委員会代表で山形県で農業を営む菅野芳秀氏は、「日本の農業は今、崩壊局面に入ってきたといっても過言ではない。日本の村から農民が消え、農民がつくる作物が消え、そして今、村自体が消えようとしている。農村で交わされているのは“農じまい”という言葉だ。その影響を受けるのはわれわれ農民ではない。困るのは消費者、国民だ。だからこそ、まだたくさん残っている農民とみなさんとが力を合わせながら、日本の農業を滅ぼす政治を変え、食と農と命を大事にする日本に変えていかなければならない。今日はそのための第一歩だ」と力強く挨拶した。
そして、「ものごとは農であり、食であり、人々の命だ。保守も革新もない」とのべ、政治信条をこえた大きな連携をつくり出してこそ、日本の農業の行き詰まりを打開する道が開けていくと強調。「たおやかに、柔らかく、喜びを持って道を切り開いていくという視点に立ってこそ道が広がっていくし、波紋が広がっていくのだろうと思う。主義主張をこえたおおらかな、伸びやかな運動をつくっていこう」と呼びかけた。
茨城県、千葉県、山梨県、埼玉県、神奈川県、遠くは長崎県五島列島や広島県尾道市・因島から、トラクターや農耕機とともに東京に集った農家たちは、「地元で自分たちのような若い世代が本当にいない。それを変えていき、楽しい農家を見せたいと思ってここに来た」「この集会を機会に、馬鹿もうけはできなくても、採算が合う農家が全国に増えるように頑張りたい」「みなさんの思いを背負って行進したい」「日本の食の未来は私たちがつくるべきだと思っている」「食と農の大切さを一人でも多くの人に知ってもらい、社会構造を変えていきましょう」など、一言ずつ力を込めて挨拶。会場から大きな拍手が送られた。

ステージに登壇して挨拶するトラクター運転手たち(3月30日、東京・青山公園)
人のデモ行進の先導トラクターを担当した静岡県の男性農家は、「食と農を守ることは国防だ。国の未来を守ること。なにより子どもたちの未来を守ることになる。心を一つにして、今日は同じ道を未来に向かってともに進んでいきましょう」と呼びかけた。
参加者を代表して挨拶した福島県伊達市の農家の女性は、家族農業でイチゴ、キュウリをメインに農業をしていること、年明けに百姓一揆のフェイスブックを初めて目にし、ポジティブな雰囲気を感じて参加したいと思ったことを語った。福島県の仲間に話したところ、力を合わせて経費や人を集め、大型バスを確保してみんなで参加することができたと話し、「生産者とか消費者とか、そんな垣根をこえて、日本国民の一人として、一人でも多くの方に興味を持ってもらえるきっかけになればいいと思っている。現状を知れば無視できないはずだ」と語った。自身の好きな言葉として「土に根をおろし、風とともに生きよう。種とともに冬を越え、鳥とともに春を歌おう。どんなに恐ろしいロボットをつくっても人は土から離れては生きられない」(『天空の城ラピュタ』より)を紹介し、「土は命の源。日本の国土を守りましょう。農民を守りましょう。農村を守りましょう」と呼びかけた。
山田正彦元農林水産大臣は、「若いころ、最初の仕事は農業だった。しかし農業では食べていけない。これは世界の農業すべてがそうだ。だからヨーロッパは国の税金で農家収入の八割の所得補償をしている。アメリカでは農家収入の4割が国の所得補償だ。日本ではそれがない。農家がここまで頑張ってきたのは、戦後の農地を大事にして、なんとかして国民の食料を守ろうとしてきたからだ」とのべた。農林水産大臣当時におこなった戸別所得補償では、わずか4000億円の予算で、右肩下がりだった農家所得が17%上がったことを明らかにし、「日本も欧米並みに所得補償が必要だ。みんなで所得補償の声を上げていこう」と力を込めて訴えた。
未来の子どもたちのために


「令和の百姓一揆」の濃紺ののぼり旗や横断幕を掲げ、青山公園を出発したトラクターは明治通り、渋谷駅前を通って約5・5㌔㍍の道のりを代々木公園へと向かった。当初の予想をこえる参加者で、デモ行進に入り切れなかった人々も沿道で見守り、各所の歩道橋には写真を撮る人、手を振る人たちが待ち構えて声援を送っていた。
トラクターを見送った後、出発した約3200人のデモ行進は「農家に補償を 所得の補償を 欧米並みの所得の補償を」「農家を守れ 国産守れ 未来の子どもに 国産残そう」「時給10円でお米つくって 限界こえてる農家を守ろう」「今動かなくちゃ農業守れない みんな立ち上がれ 今が正念場」などのコールを響かせながら、表参道や原宿を抜けて、代々木公園へと向かう3・2㌔の道のりを歩いた。
行進の合間には宣伝カーから「コメ農家は時給10円ともいわれ、農家の限界はとっくにこえた状態でこれまで頑張ってきた。今日は令和の百姓一揆として、全国から農家がトラクターで集まり、別ルートでトラクター行進をしている。北海道から沖縄まで全国各地の農家が立ち上がっている」「今こそ農政の転換が必要だ。農業を守り、私たちの食と命を守ること、未来の子どものためにみんなで立ち上がりましょう」と道行く人々に訴えた。
コメの価格高騰が生活に大きな影響を与えるなかで、デモには若者や家族連れなど消費者も多数参加した。手作りのプラカードを持って家族3人で参加した女性は、「農家がつくった作物を消費者に届ける事業をしたりしてきた。農家が危機的な状況にあるということを、一人でもたくさんの人に知ってほしいと思って参加した」と話した。
10人ほどで参加したという女性は、グループで山田正彦氏の講演会を開催したり、みんなでコメ作りをするなどの活動をするなかで、消費者が食べ物がどこから来ているかについて関心が薄いことを感じてきたという。「少しでも農業に関心を持ってもらい、自分事として考えてほしいと思って参加した。私たちは消費者の立場。政府にもの申すというより、自分たちが買い支えることで農を守らないといけないと思っているが、今日はギリギリまで耐えてきた農家を応援するつもりで来た」と話した。
今回を出発点に広げる


デモ行進終了後、「令和の百姓一揆」実行委員会は、明治記念館で次に向けた寄り合いを開催。当日の成果を確認するとともに、今後どのように運動を広げていくか協議した。
提案者の一人である山田正彦氏は、呼びかけから約3カ月の準備期間にもかかわらず、実行委員会メンバーの尽力で、想定をこえる規模の参加者、全国14カ所に広がり、第1回目が成功に終わったことを確認した。
クラウドファンディングは2カ月余りで1900万円超、サポーター登録は2300人をこえ、実行委員会には1500人が登録して、この日に向けて協議を重ねてきたという。当日は100人超がボランティアとして運営を支えた。実務を担ったスタッフも、「コールをしていると、後ろから大きな声が聞こえ、歩道橋の上からも同じコールが聞こえてきて、そうしたことも勇気になりながら一緒にできた」「すべての人が初めてのことだったので試行錯誤だったが、メディア含めてすごい拡散力だったと思う。さまざまあったが、すべてを帳消しにするほどインパクトのある行動だったと思う」など、確信を持って語られた。同時に、「これが始まりということを意識して活動していかないといけない。各地で一人一人がこれからの農業を変えていく意識を持って、この国の農業政策を勉強し、まわりの人にも自分の言葉で伝えていくことが大事だと思う」(コメ農家)といった今後に向けた意見もあいついだ。
最後に、菅野芳秀代表と山田正彦氏より、今回がスタートであり、さらに農家生産者と消費者、市民との連携を強め、また議会に働きかけて農家への所得補償の実現、日本の農業が持続できる政策の実現をめざして全国各地域でとりくみを広げていくこと、そのうえで「令和の百姓一揆の会」を設立し、具体的な行動を起こしていくことが確認された。