
武谷三男
湯川秀樹、坂田昌一などと原子核・素粒子を研究した理論物理学者・武谷三男(1911~2000年)が亡くなって来年で20年を迎えるのを前に16日、江戸東京博物館(東京都墨田区)で講演会「今なぜ武谷三男なのか―その思想と現代の諸問題―」(主催/武谷三男史料研究会)がおこなわれた。福島原発事故をへても進む原発再稼働、大学や研究機関を軍事利用に巻き込む軍学共同、不特定多数の人間を管理し、生体情報を商品化する高度医療や遺伝子・ゲノム技術など、科学技術の進歩と科学者の社会的使命をめぐる問題が浮上するなかで、戦後の理論的物理学の基礎を築いた武谷三男の業績と思想に光を当て、現代社会の問題の解決に役立てる試みが始まっている。
武谷三男は、1911年に福岡で生まれ、高校卒業まで父親の就職にともなって移住した台湾で過ごした。後に京都帝国大学理学部を卒業し、湯川秀樹、坂田昌一の共同研究者として中間子論(後に湯川秀樹がノーベル物理学賞を受賞)の研究を進め、中井正一、久野収らとともに反ファシズムを標榜する『世界文化』に参加し、後に主著『弁証法の諸問題』に収められる多くの論文を書いた。それによって治安維持法違反で官憲に検挙されるが、特高警察調書で書いた「技術論」は多くの支持を得て、戦後の技術論論争の盛り上がりに貢献した。
戦後は、鶴見俊輔らとともに『思想の科学』を創刊し、科学、技術の問題など多くの論文を発表し、原子力問題では、原子力研究三原則(自主・公開・民主)を提唱。放射線被曝において米国が主張する「許容量」は安全を保証する自然科学的な概念ではなく、放射線利用の利益・便益とそれにともなう被曝の有害性を比較して決まる「がまん量」と呼ぶべきであると主張し、ビキニ環礁で米国がおこなった水爆実験を厳しく批判した。
生産技術向上に伴う公害問題や人権問題にも積極的にとりくみ、「安全性の哲学」「特権と人権」など、進歩発展する科学を否定する立場からではなく、それをよりよい社会の構築や人間生活の向上のために使う科学者の哲学・思想にかかわる提言を数多く残した。

講演会には150人が詰めかけた(16日、東京)
今回の講演会にあたって主催者は、「原発、コンピューター、医療・福祉、ゲノム操作、軍事など非常に多くの分野で現代技術と社会との緊張関係、相克が鬱積している。これらを解く鍵として武谷の思想が今こそ有効だと思う。持続可能な社会、貧困・格差のない社会、差別のない人権を守る社会、一人ひとりが生きがいのある社会をつくるにはどうすればいいか、戦後半世紀にわたって武谷三男がとりくんだテーマと共通する問いが、今私たちすべてに課せられている。現代の諸問題に対して、どのように対処すべきかを没後20年の武谷三男の思想から探り出せないか」――と呼びかけ、当日は定員をこえる150人が詰めかけた。
講演会は、はじめに武谷三男と1950年代から親交のあった小沼通二氏(元日本物理学会会長)が、このたび武谷家から段ボール31箱にのぼる史料の寄贈を受け、より多くの人の研究に役立てるため史料研究会としてリスト化、デジタル化を進めていることを明かした。
さらに経過報告として、史料を管理する三本龍生氏(武谷三男史料室長)がその経緯を、デジタル化を担当する藤田貢崇氏(法政大学教授)がデジタル化の方法と現状を報告した。三本氏は「若い人たちには武谷の名前も業績も知らない人が多いと思うが、今こそ武谷の思想を引き継ぎ、現代の学問的、社会的な問題に立ち向かう“知の力”を提供できるようにするのが私たちの役割だ」とし、要望に応じて資料を提供できる体制を整えていくことを約した。
続いて、武谷三男の史料をひも解きながら、「若き日の日記から」として西谷正氏(武谷三男史料研究会会員)が少年期の武谷の人となりを当時の日記から紹介。また、「武谷思想の源流」として八巻俊憲氏(武谷三男史料研究会会員)が武谷三男の思想の構造や特徴について解説した。
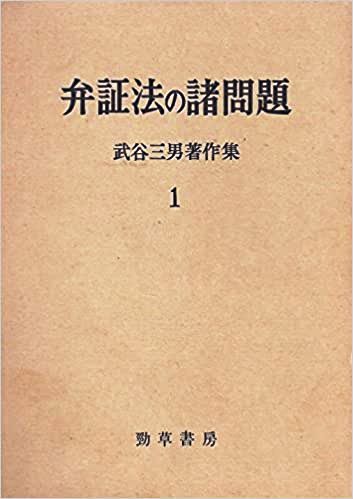
『弁証法の諸問題』( 1968年、勁草書房)
八巻氏は、武谷が終戦直後の1947年に書いた『弁証法の諸問題』(第二版)のはしがきに「この諸論文は主としてあの弾圧と暗黒の時代に、ささやかであるがしかし何か確実なものをつかみ、これを守りたいと思って一歩一歩進みながら、記録し、歴史の進歩を願い、そのために闘う人々の共同の財として、また、あの強烈なせん風の中でしっかりとその確信を守るための何らかの支えになればと願ったものです」と書いていることを紹介し、「これが武谷の思想家としての姿勢だ」とのべた。
武谷の言論活動は、認識論、物理学、三段階論、技術論、科学史・科学論、原水爆戦争や核戦争の脅威についての解説と警告、科学政策のあり方提言、原子力平和利用の提唱と批判(原子力平和利用三原則)、市民の立場からの社会における科学技術批判など多岐にわたり、「物理学者武谷は、物理学をこえて自然科学全般、自然科学をこえて科学技術全般、科学技術をこえて、哲学、社会科学、教育、宗教など、学術の諸問題と社会(政治、軍事、市民生活)とのつながりについて議論しており、さらに一市民としての立場から、科学、技術、文化、社会のあり方について議論した」と概括した。トルストイやロマン・ロランの人道主義から、昭和10年以降には唯物弁証法をとり入れ、マルクス主義を受け入れるようになり、独特の思想が形成されていったことに触れ、「ヒューマニズムの名の下に呼ばれ得るものは、何らかの意味において人間尊重、人間解放の主張を持っていなければならない」(武谷三男)とのべていたことを紹介した。
特別講演として、看護師時代に武谷三男から直接薫陶を受けた川嶋みどり氏(日本赤十字看護大学名誉教授)が「武谷技術論と看護」と題して、戦後も封建的な境遇におかれていた看護師の地位向上や看護技術の発展に武谷思想が果たした役割と現代における医療問題を結びつけて提起した【下別掲】。
さらに「現代社会と武谷思想」と題して講演した佐高信氏(評論家)は、「人間の理性はいかなる困難に面しても必ずそれを貫く道を見いだすものです。いま現実は私を悲しませているが、人間の人間に対する愛が人間の優れた理性を勇気づけて必ずすばらしい道を切り開くでしょう」(『弁証法の諸問題』まえがき)との言葉に感銘を受けた広島の原爆詩人・峠三吉が、肺病による喀血をしながらも、広島訪問中の武谷に会いに行ったエピソードなどを紹介。「武谷の本は、敵をはっきりと見据えたたたかいの書であったがゆえに思いがけないところにも影響を与えている。武谷三男の思想を現代社会に広げていくことが必要だ」とのべた。
最後に武谷三男史料室長の三本氏が、今回の講演会を機に、武谷に関するシンポジウムを続けていくことをのべ、「武谷思想を現代の諸問題に生かして、いかにたたかっていくかを考えていきたい」と締めくくった。
-------------------------
武谷技術論と看護
日本赤十字看護大学名誉教授 川嶋みどり

私が武谷先生の技術論に触れたのは1951年のことだ。それまでは武谷先生の顔も知らないし、なにも知らなかった。たまたま私が後の連れ合いに下北沢の駅のプラットホームで“結婚してからも仕事やめないでいいかしら”と聞いたとき、“看護師って職人なの? 技術者なの?”と質問された。とにかく当時は3年間のハードな教育を受けながら勉強し、新小児病棟の新人看護師として無我夢中で働いている最中だったので、返答に困って“とにかく毎日忙しいし、看護は看護よ”というのが精一杯だった。そのとき彼が“読んでごらん”と貸してくれたのが星野芳郎さんの『技術論ノート』だった。武谷さんの技術論を解説した本だ。この本のなかに、技術と技能を分離して考えなければいけないことが書かれていて、驚きとともに目を開かされたのが始まりだった。
そのころの小児病棟は、進駐軍による母子分離の命令で親が付き添えず、36人の子どもたちを看護師たちが24時間看護していた。戦前戦中の赤十字の従軍の名残があるため、いくら戦後の民主国家になったとはいえ上下関係は厳しく、なにも先輩は教えてくれない。私たちはただ彼女らの後ろ姿を追い求めながら、見よう見まねで仕事に慣れるために振り回される日日だった。この本を読み、彼女らが意地悪で説明しないのではなく、その経験をまだ口で説明できない技能レベルであったからではないかとの思いがよぎった。
新憲法が発布され、婦人参政権が定着し、男女同権とか、民主国家、文化国家とかいわれていたが、私たち看護師はいまだに全寮制が原則という時代。門限の夜7時には点呼があり、9時に消灯という厳しい私生活をよぎなくされていた。だが外で吹く民主国家、文化国家の風が窓の隙間から入ってきて、だんだん個人的にも“私たちも人間だ”“専門職は一生の仕事といわれるのだから、一生の仕事をやるんだったら結婚したい”という思いが募った。この疑問は時代の流れと一致していた。
1960年6月19日に日米安全保障条約改定案が自動承認され、国会周辺は連日デモ隊で埋め尽くされ、岸信介首相を退陣に追い込んだ60年安保闘争が始まる。忘れもしないが、30万人が集まった6月18日の国会前デモでは、私も1歳5カ月の長男を背負って生まれて初めてデモに行った。両手を繋いで道玄坂一杯のデモにドキドキしながら参加したのを覚えている。このような時代の流れと合わせて、看護師たちが「私たちも人間だ」「寮の中に閉じ込められているのはおかしい」「通勤しても辞めさせられないようにしないといけないんじゃないか」「結婚しても辞めてはいけないじゃないだろうか」ということに目が覚め、1960年10月に初めてストライキで病院の門前にスクラムを組んで座り込んだ。「忍従こそ最大の美徳」とされ、低賃金にも甘んじて、どんなに労働条件が厳しくても文句をいわずに我慢に我慢を重ねるのが赤十字精神だったが、「私たちも人間だ!」とスクラムを組み、「夜勤に疲れた重い足に/みんなで言い聞かそう/夜明けが来る/人並みの暮らし/幸せを求めて/苦しみに負けないで立ち上がろう」(涙のスクラム)と涙を流しながら歌った。当時はいくら権利だといわれても「看護師も人間です」というだけでも恐ろしく、「看護師が患者をほったらかしてストライキをしてもいいのか」という批判も受けてとても辛かった。それでもたたかい続けたからこそ技術論にも巡り会うことができたと思っている。
国中で広がる安保闘争、労働組合の高揚期、看護師の人間宣言、さらに個人個人の看護師が目覚めていったことなどが重なりあっていった。だが、最初は低賃金と労働条件の改善を求めてスタートした看護師たちのたたかいは、当時、三矢作戦計画(自衛隊統合幕僚長会議でおこなわれていた机上作戦演習)などが出てきたことにより、「もしかしたら看護師がまた従軍させられるのではないか」という問題意識を生み、政治闘争へと転換していく。私たちの労働運動が未熟だったこともあって、これは大弾圧を受ける。職場は四分五裂になり、第一組合から第五組合までできて「このままでは看護できない」という状態になるが、看護師一人一人の所属組合や思想信条が違っても「よりよい看護をしたい」という点では一致する。「それなら看護の勉強をしよう」ということで、1965年につくったのが東京看護学セミナーだった。

東京看護学セミナーで講師を務める武谷三男
当時、組合運動が叩かれる一方で、フルブライト奨学金で同年代や下級生が米国に留学していく。私たち組合活動をしていた者が希望しても除外され、国内留学さえかなわなかった。「それなら自分で勉強しようじゃないの」ということで開いたセミナーにお迎えしたのが武谷三男先生だった。
よりよい看護へ勉強会
もう一つの背景は、医療事故の頻発だった。赤ちゃん取り違え事件、酸素ボンベ爆発事件、輸血間違え事件、寿産院事件などいろんな医療事故があり、そのとき岩波新書で『安全性の考え方』(著・武谷三男)という本が出て、「この筆者にぜひ会いたい」という声もあり、私も技術論に感銘を受けていたのでお呼びすると喜んで来て下さった。
第1回目は技術論の話ではなく、イギリスのコメット機墜落事故の調査が後の航空技術にたいへん寄与したという話だった。それが看護技術と何の関係があるのか私たちはわからず、すっきりしない思いだったが、その後に店でお茶を飲みながら話をしたときに、武谷先生は「あなたたちは専門職、専門職というけれども、医者に断ることがあるのか。断ることがないのなら専門職といわない方がいいよ」というようなことをいわれた。
私も一知半解であったが、あるとき先生が安全性の話をされたときに手をあげて、「先生は技術論も書いておられる。そこでは“技術とは、人間実践(生産的実践)における客観的法則性の意識的適用である”と書かれ、技術と技能は違うといわれているが、看護は技術でしょうか? 技能でしょうか?」という質問をし、先生がその質問に驚かれていたのを覚えている。
公開セミナーを重ねるなかで、今起きている看護の事故を分析すれば、看護が技術として発展するかもしれないということに落ち着き、技術論の勉強と事故事例分析が始まる。東京と関東圏の経験も職場も違うナースたちが100人ほど集まり、武谷先生の『安全性の考え方』を土台にしながら頻発する事故事例分析をし、技術論へ行くプロセスが30年くらい続いた。1985年ぐらいまで武谷先生の直接の教えを受けながら勉強をしていた。当時、武谷先生から学んでいることの重みは感じていたが、これが非常に理にかなったものだということを実感しているのは近年になってからだ。
セミナーをくり返すなかで看護界一般に武谷先生の名前が知られてくる。原子とか分子とか量子学とか抽象的論理や概念、科学の最先端で手が届かない理論物理学の研究をしている武谷先生が、どうしてまだ技術ともいえない未分化な行為であり、思いやり、人柄、優しさというようなレベルの看護のところまで降りてきてくれたのか不思議だった。先生は「降りてきたのではない。対等だ」と怒っておられたが、私には、理論物理学と看護というまったく異次元ともいえる世界が繋がったことが不思議だった。
そして、武谷先生の「技術は実践概念だ。実践を内面から、その実践がいかにして可能であり、いかにしておこなわれるか、その原理について見る必要がある。技術は、行為の形でもなく行為の結果でもなく、行為を可能ならしめる原理である」という言葉にものすごく共感した。これは日日めまぐるしい業務のなか、正しい看護の方向を模索する者にとって大きなヒントとなり、現在に続く問題意識になっている。理論物理学者・武谷と、看護師の間をつないだのは、実践を大切にする思想と姿勢だった。
看護学雑誌(1968年6月)の特集で、「武谷先生に聞く―技術とは何か」という川上武さんとの対談で、「方法論はなぜ必要か」「科学と技術はどう違うか」「技術と技能の関係」「技術者として安全性に責任を」「特権を守るが人権は…」「看護技術の位置づけのために方法論を学ぼう」という柱で話されている。ここに私たちが長年かかって到達した内容がだいたい盛り込まれている。
だが勉強をくり返しても理解できないことが一つあった。先生は、技術論のなかで「技術は客観的で、ゆえに社会的で伝承可能である」としながら、それに対して、技能は伝達ができない非常に個人的な業であるということを書かれている。私は、看護学生に技術論を教えるときに「技術とは客観的法則性における意識的適用だが、技能というのは客観的法則性における無意識的適用だ」と教えていた。それは、客観的な法則性とは、私たちが理解しようとするまいと厳然としてあり、それに気がつかずにやっているのが技能なんだという意味だと自分が受け止めていたからだ。星野さんの『技術論ノート』にもそのように書いてあった。ところが武谷先生は例会で、「技能というのは、主観的法則性の意識的適用だ」とおっしゃった。「思い込み(主観)がなぜ法則性になるのか、理解できない」というと、その後、先生は何時間もかけてそれを説明してくださり、弁証法の諸問題を読むにあたって「一番プリミティブな具体的な希望としては、くり返し読んでくださいということだ。一行でも読み飛ばしたらいけない」という内容の話をされた。
私がいろんな人たちの見解や星野さんの本を引き合いに自分の技術論の解釈の正しさを主張すると、武谷先生は「世論調査をしたんだね。多数決は真実かい?」と聞かれた。「ガリレオは一人で真実をいった。99人が悪魔の声だと思っていたことが真実だった。あなたが誤ったかどうかはあなたが考えることであって、僕は誤っているとはいわない。でも、あなたは世論調査をしたに過ぎない。多数決で99人が賛成していても、1人の意見が真理であることもあることだけはいっておきましょう」といわれた。星野さんは後に解釈を訂正なさっていて、先生はそれを知っていて何時間も討論した後に「星野君はすぐに訂正したはずだよ」といっておられた。
そして最後に「“こんな感じの場合にうまくいく”ということを意識的に適用するのが技能だ。“こんな感じのとき”というのが主観的、個人的に“うまくいく”というのが法則性だ。そして、その感じを獲得するために訓練する。訓練して肉体を通じて得ることは意識的な努力だ。そうやって身につけることが意識的に適用するということ。だから、熟練しなければ技能は使えない。訓練してその感じを本当に体得する過程のなかに意識的というものがある」(主観的法則性の意識的適用)と説明してくださった。
その後、私たちの要望に応えて1983年5月から84年12月まで、12回におよぶ技術論の勉強にお付き合いいただいた。そのなかでは、著作のなかから「科学者の心配」「原水爆と公害」「公害・安全性・人権」「市民の論理と科学」……など多くの論文を指定して読むようにいわれた。気がつくのはこれは現代、世界中で問題になっていることだった。
安全性の問題でも多くのことを学び、セミナーの機関誌では、「安全問題の核」として「平均的に落ち度なくやれるのではなく、最悪の状態の時、危険が起こらないようになっていること」--つまり、最悪の状態が重なったから患者を失わせたというのではダメだといわれている。「病院の安全問題への姿勢」として「医師は単なる技術者、看護婦は全体を正しく運ぶマネージャーである」とし、「看護婦は医師に適切な指示を出させるようにする。医師の指示待ちでは官僚的責任逃れである」と書かれている。
安全性問題で一番大きかったのは「ある保健師の死」だった。アッペ(急性虫垂炎)の診断で救急病院をたらい回しにされて手術を受けたベテランの保健師さんに対して、看護師が「先生はアッペと診断しているのだから、もう起きていいですよ」と起こそうとするが、本人は痛がって起き上がれない。結局、無理に動かされて手術台の上で亡くなるという事件が起きた。そのときの討論で、世田谷病院の当事者の看護師たちが集まってくれ、はじめて当事者を含む安全性の検討会をおこなった。
そのときの武谷先生の言葉は、「医師の診断を絶対視するな」「(患者の)どんなわがままな訴えも一応とりあげて考える」「モダーン(現代的)な技術、効率のよいものは非常に危険がともなうことを自覚せよ。細心の注意と技能レベルが求められる」というものだった。なにがモダーンかといえば早期離床。オペの翌日に歩かせたりするようなことだ。
これも現代の問題に繋がるが、「定型化とデータ過信では安全性は守れない」といわれた。マニュアル化され、その基準に沿って患者を当てはめることや、「データは大丈夫」といって患者の状態を見ない傾向を批判された。そして「100%の安全を守ること。99%安全でも残りの1%で事故は起きる。事故当事者にとっては100%の危険なのだ」といわれた。そして「看護婦の小さな特権は、患者にとってはとても大きなものに感じられる」といわれた。安全性の討論でもこのような技術の話、人権や特権など幅広くものごとを考えることができた。
「特権と人権」に関しては、「日本軍が中国や南方でさんざんなことをやった。今の青年は“あれは俺の親父の代がやったことで、僕たちは関係ない”という。だが、親父を殺された息子は“殺されたのは父の代で俺たちは関係ない”というかどうか。“自分は報復しない。しかし、忘れない”という言葉がある。被害者は絶対に忘れない。植民地支配然り」と話された。これもまさに今の日韓問題を複雑にしている植民地支配における徴用工問題、慰安婦問題と直接繋がる言葉だと思う。
 私たちは、かずかずの臨床現場のなかから生まれた看護技術学の集大成として、1983年から2001年にかけて、教科書にない実際に役立つ技術を目指して大系本(実践的看護マニュアル)を4冊発行した。実践こそ武谷技術論の要であるので、まずおこなっていることのふり返りから、一つの病名ではない患者ケーススタディを積み上げ、チーム医療の強力なパートナーとしての医師を巻き込み、新人がどのように動くか(どこに問題があるか)まで検討し、書き直しを重ねて書きあげていった。それが東京医科歯科大学の医学部の教科書に採用され、中国や韓国でも翻訳されて何千万部も出た。
私たちは、かずかずの臨床現場のなかから生まれた看護技術学の集大成として、1983年から2001年にかけて、教科書にない実際に役立つ技術を目指して大系本(実践的看護マニュアル)を4冊発行した。実践こそ武谷技術論の要であるので、まずおこなっていることのふり返りから、一つの病名ではない患者ケーススタディを積み上げ、チーム医療の強力なパートナーとしての医師を巻き込み、新人がどのように動くか(どこに問題があるか)まで検討し、書き直しを重ねて書きあげていった。それが東京医科歯科大学の医学部の教科書に採用され、中国や韓国でも翻訳されて何千万部も出た。
これは技術論が要になっているだけあって、今見てもこの右に出る看護の技術書はないと思う。武谷技術論を看護に持ち込んだ成果の証だと思っている。
本当の看護をめざして
今は高度医療技術で、生体情報が質・量ともに飛躍的に増大し、高速処理蘇生術のシステム化・高度化が進み、顕微鏡下手術装置、そして人工臓器、放射線治療の進歩、高齢者や新生児を含むハイリスク患者へのチャレンジ、体外受精、遺伝子操作、ヒトゲノムの解明、iPS細胞の出現による再生医療の可能性などめまぐるしく医療技術が発展し、さらにAI化までいわれている。その先、いったいどのように医療技術が進み、その結果、医療現場、看護現場はどうなるのか未知の事象に溢れている。
武谷先生は、脳死患者の臓器移植について「脳死の診断ができるまえにそんなことを決めるべきじゃない。心臓移植をしたい先生は早く脳死の診断を…と思ってやっているのだから」といわれていたし、体外受精の問題については「これはノーベル賞受賞者の精液がスーパーで売り出されるかもしれない」といわれていた。すでにはるか先を見越した言葉にハッとさせられたことを思い出す。
今は医療の機械化が人間疎外をもたらしながらどんどん進行している。みなさんが外来に行っても、おそらく外来でナースの姿を見ないのではないか。部屋に入れば、だいたい医師はディスプレイに集中し、体には触ってくれない。血液ガスの値が優先する思考過程のなかで、患者が呼吸を楽にしてほしいと思っても放置されてしまう。密度とテンポの速さは予想以上に人間疎外をもたらし、医療スタッフ・患者双方が疎外されている。目はディスプレイ、手はキーボード、患者に触れないのが医療の根幹になり、すべてはモニター監視、デジタルデータ監視に頼る。
そして、医療安全としてリスクマネージメントシステムが導入されたが、行きすぎた医療安全が患者の尊厳を脅かしている。患者を縛り付ける拘束をしなければベッドから落ちて病院の責任が問われ、先生たちが一列に並んで頭を下げなければいけない事態になる。子どもが使う図工用のハサミさえ危険だからといってとりあげられ、お尻が蒸れるからオムツの中に手を突っ込むと、すぐその手が縛られるということがたくさんある。理由はすべて「医療安全のため」だ。手術後の麻酔が切れていないのに「お名前は」と何度も聞かれ、その人の背景を理解しようとしない。
にもかかわらず医療事故は後を絶たない。リスクマネージメントとは、患者の安全が第一義ではなく、企業の安全、つまり病院が損害賠償のリスクを減らし、賠償請求されるお金を減らすために訴訟大国アメリカから輸入されてきた考え方だ。だから、いくらそのシステムが導入されてきても、決して事故はなくならない。安全性の考え方の基本に、人権を尊重する、人間の尊厳を冒してはならないということが抜けているからだ。私はこの点から、武谷技術論に立って見直すべきだと思っている。
バーコードで本人確認し、患者の訴えよりもデジタルデータを過信し、患者の安楽性(人間らしさや苦痛緩和)を疎外する。私たちが大事にしてきた生活行動援助が軽視あるいは放棄されている。
看護の専門性の基本は、生命を維持する日常的習慣的ケアを保つことだ。つまり食べたり、眠ったり、トイレに行ったり、体を清潔にしたり、学習をしたり、リハビリやコミュニケーションをしたり、移動したりなど普段通りの生活だ。だが、それがあまりにもありふれた営みであるがゆえに、これを学問にするのはとても困難で、日本で明治から始まった看護は医学の手伝い(アシスタント)とされ、50年間続く戦争の間もずっと看護は医師に附随した仕事だった。戦後改革のなかで、ようやく看護は独立した専門職といわれ始める。生活行動援助--つまり人間が生きていくうえで欠かせない諸諸の営みが、病気であろうと、高齢であろうと、障害を持っていようと自分らしくおこなって生きていくことができる状態を保つのが専門職たる看護の基本だ。
だから、今の看護では、診療報酬制度のなかでなんでもかんでも狭義の医師の仕事を手伝う方に傾いているがゆえに看護らしい看護ができない。看護師が本当の看護に集中できるようになれば、私たちがうれしいだけでなく、患者さんのクオリティライフ(質の高い生活)への貢献になる。なぜなら看護は、注射器もメスも薬も使わず、看護師の全人格を投入して身体ツールを使って患者さんの治る力を引き出し、患者さんに気持ちのよいケアをすることによって患者さんの副交感神経を優位にし、自然治癒力を高めることができるからだ。
この基本が忘れ去られ、看護師も忙殺されてそれが実践できず自分自身に価値を見出せなくなっている。これを技術化し、言語化して伝えていけば、看護はあらゆる最先端医療の先を行くものとして医療全体を牽引していく優位性があると思う。医療は宿命的に不安や恐怖、心配、副作用などの侵襲性をともなうが、看護はプロセス(過程)もアウトカム(結果)も安心・安全で安楽だからだ。
現在介護が社会的な話題になる一方で、看護は何かの事件のときくらいしか出てこない。医療と介護の一括法案といわれるように、国のなかで「医療と福祉」という言葉が「医療と介護」に転換され、看護は介護職より100年前に始まった仕事なのに影が薄くなっている。これを元に戻したい。全国の看護師160万人のパワーを無駄なく社会貢献に活用する道を開くとしたらすごく国民のために役に立つと思う。
武谷先生にこの医療問題と合わせて、現在日本で起きている福島第一原発の処理の問題や日韓問題を提示してお考えを伺いたいが、たぶん先生はこうおっしゃるだろう。「それを決めるのはあなたたちだよ。あなたたちが討論して、あなたたちが決めなさい。あれをああしろ、これはこうしろというのは形而上学的レベルでしょ?」と。





















