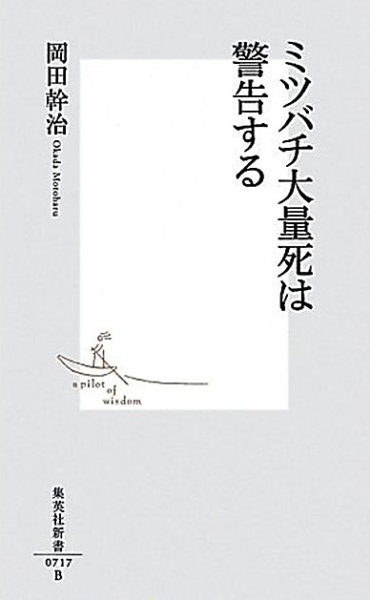 著者はフリージャーナリスト。2009年頃からミツバチの大量死があいついでいることに疑問を持ち、その原因を掘り下げている。
著者はフリージャーナリスト。2009年頃からミツバチの大量死があいついでいることに疑問を持ち、その原因を掘り下げている。
ミツバチは人類が誕生するはるか前に地球にあらわれ、植物の受粉を手伝って、森をはぐくみ生命をつないできた。ミツバチは人間に蜂蜜をもたらすし、ローヤルゼリーやプロポリス(巣を補修するために植物から集めてきた樹脂)、花粉の3つの健康食品も重宝されている。しかしそれよりはるかに大きな恵みは、ミツバチが果樹や野菜の受粉を助けていることだ。
実際、世界の食料の90%を供給する100種の作物のうち、70種以上がミツバチによって受粉している。つまりミツバチがいなくなれば、食料生産そのものが成り立たなくなるわけだ。
ミツバチは発達した脳と神経を持ち、環境のわずかな変化にも敏感に反応する。ミツバチは群れをつくって生活するが、群れは1匹の女王バチと、数千~数万匹の雌の働きバチ、その1割以下の雄バチからなっている。女王バチは2~4年の生涯で、初夏の最盛期には1日に2000~3000個も産卵する。一方働きバチは、生まれた後に育児や巣作りをした後は、死ぬまで外に出て花蜜と花粉、水をとってくる。約50秒以内に花蜜をとってこれた場合、もっと採集すべきだというように、巣の入り口近くで「尻振りダンス」をして仲間の働きバチに知らせるという。
そのミツバチの大量死が日本国内で問題になったのは、2009年の夏からだ。この年、長崎県内では約4000万匹ものミツバチが死んだとの予測が出た。原因は、ネオニコチノイド系の農薬を殺虫剤として水田で大規模に使い始めたからだった。その結果、採蜜量が激減したうえ、花粉交配用のミツバチが足りなくなった。長崎県は全国有数のイチゴの産地で、イチゴ農家は10月~翌年3月頃までビニールハウスでイチゴを育てるが、その交配に必要な約3500群(1群は5000匹)のミツバチはJAを通じて養蜂協会から借りていた。それが足りなくなったのである。
この年、国内各地でイチゴ、スイカ、メロン、サクランボなどの農家が花粉交配用ミツバチの不足に頭を抱えていた。ミツバチが手に入らなければ、受粉を人手でやらざるをえない。しかしたとえばイチゴの場合、それは肉体的に大変なうえ、できたイチゴが赤と白のまだら模様になったり、細長くなったりして売り物にならず、収入が大幅に減る農家が続出した。
そして、この現象は世界的なものだった。アメリカでは2006年、ミツバチ1000万群超が死滅するCCD(蜂群崩壊症候群)が社会的問題になった。国連環境計画(UNEP)は2011年、「ミツバチを含む受粉昆虫を保護しなければ、約2万種もの植物種が今後数十年で地上から消えてしまう可能性がある」との報告を出した。
グローバル化の時代に警鐘
ミツバチ大量死の原因は何か? 著者は各国の研究者の研究成果を紹介しながら、その解明に進んでいく。原因はやはりネオニコチノイド系農薬であり、それを使用することでミツバチの帰巣行動や生殖能力にダメージを与えていたことが明らかになる。
ネオニコ系農薬とは、ニコチンと同種の化学構造を持つ農薬で、日本では2000年代に入ってから生産と使用が急増した。つくっているのは世界三大農薬大手のバイエル社(ドイツ)と住友化学などだ。ネオニコ系農薬は害虫の神経伝達を混乱させる「神経毒」で、殺虫性能はDDTの5000倍以上といわれ、虫が体内にとり込むと摂食、交尾、産卵などができなくなって成育不良から死に至る。しかも効果が長期間続くため、「農薬の使用回数を減らせるので高齢生産者には便利」と宣伝している。これがミツバチ大量死の原因だと、各国の研究者が指摘している。
影響はミツバチにとどまらない。本書では、2000年頃から田んぼで育つ赤トンボが激減したが、それもイネの育苗箱に使用する農薬が2000年頃からネオニコ系に変わったことが原因の一つだとのべている。田んぼはコメを供給するとともに、水源涵養・洪水防止機能や気温を下げる機能を持つが、それも田んぼがたくさんの生き物が育つ「揺りかご」であり、そこで生物多様性が維持されてはじめて、その力は十分に発揮される。そこで動植物が一種、また一種と絶滅していくなら、その機能はいつか一気に崩壊する可能性がある。
戦後、化学合成の技術が発展し、農業生産向上の目的で多種多様な殺虫剤や殺菌剤、除草剤の開発競争がおこなわれてきた。こうした化学物質は、放射能と同様、第二次大戦の申し子として生まれ、大企業によってもうけのために利用されるようになり、巨額のカネが動くために政・官・財、御用学者やマスメディアのムラができて「安全神話」を垂れ流し、その結果、自然の摂理を破壊し人間の生命を脅かすという本末転倒した事態が引き起こされている。こうした社会構造に目を向ける必要があるというのが、著者の結論のようだ。
モンサントやバイエルのような欧米のバイオメジャーが、日本市場をターゲットに、遺伝子組み換えや農薬開発の分野で参入を狙っている今、子どもたちの未来のために警鐘を鳴らす書となっている。
(集英社新書、254ページ、定価760円+税)





















