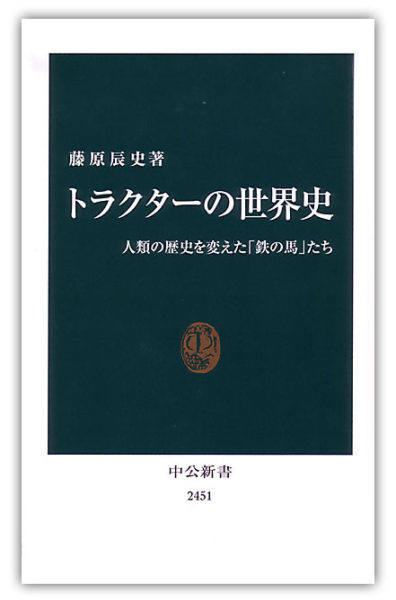 20世紀のモータリゼーションの時代は自動車を中心に描かれることが多いが、本書はトラクターを中心にそれを描きあげている。人間が生きていくうえで不可欠な食、それを得るための農業は、土を耕す行為が基本である。それは土壌の下にある栄養を上にもたらし、土壌内に空隙をつくり、保水能力と栄養貯蓄能力を高め、さまざまな生物の働きと食物連鎖を活性化させて、そこに根を張る植物の栄養価を高め、容量を増やすからだ。数千年にわたってこの土地を耕す作業を担ってきたのは人間であり、また牛や馬である。ここに革命を起こしたのがトラクターの出現であり、それによって農村風景は一変した。本書は京都大学人文科学研究所准教授の著者が、地球の人口を爆発的に増やすことを保証したトラクターの歴史を、各国の実情と歴史に分け入りながらまとめたものである。
20世紀のモータリゼーションの時代は自動車を中心に描かれることが多いが、本書はトラクターを中心にそれを描きあげている。人間が生きていくうえで不可欠な食、それを得るための農業は、土を耕す行為が基本である。それは土壌の下にある栄養を上にもたらし、土壌内に空隙をつくり、保水能力と栄養貯蓄能力を高め、さまざまな生物の働きと食物連鎖を活性化させて、そこに根を張る植物の栄養価を高め、容量を増やすからだ。数千年にわたってこの土地を耕す作業を担ってきたのは人間であり、また牛や馬である。ここに革命を起こしたのがトラクターの出現であり、それによって農村風景は一変した。本書は京都大学人文科学研究所准教授の著者が、地球の人口を爆発的に増やすことを保証したトラクターの歴史を、各国の実情と歴史に分け入りながらまとめたものである。
蒸気機関が発明されたのは19世紀初頭のイギリスだが、内燃機関を積んだトラクターは20世紀初頭のアメリカで産声を上げた。1892年、アメリカの重要な穀倉地帯であったアイオワ州に住む技師、ジョン・フローリッチが内燃機関を搭載したトラクターを開発した。
当時、農作業のなかで牛や馬に犂(すき)を牽(ひ)かせて土壌を耕すという作業はもっとも機械化が難しいといわれていた。しかし、トラクターの誕生によって、牛馬のように飼料を必要とせず、燃料を補給することで犂を牽くことができるし、人や馬のように疲れることもなく、しかも人や馬の何倍もの力をいつまでも安定して出すことができるようになった。この耕耘作業は、小麦の生産に投入するすべての労力のうちの60%を占めており、それを機械化したのだから革新性はめざましかった。またある調査では、トラクターによって、毎日餌を与えるなど動物を世話することに必要な時間を年間で250時間も省くことができたとしている。
トラクターの大量生産に成功したのは自動車王フォードだった。アメリカでは第1次大戦前に使われていたトラクターはわずか1000台にすぎなかったが、1930年代には100万台に達し、1950年代初頭には400万台をこえた。製造各社の競争によって、推進力を作業機に伝え、前進しながら麦を刈り取り紐で束ねる優れものが生まれ、そのほかトウモロコシや綿花、果樹園や林業にも対応できるトラクターも生まれるなど、農業技術の革新が進んだ。トラクターは世界各地に普及し、20世紀以降の爆発的な人口増加を支えている。
他方、トラクターを使った農作業は、20世紀を震撼させた事件の原因の一つにもなっていく。
トラクターによって農業生産力が高まったおかげで、スタインベックの『怒りの葡萄』に描かれているように、経営効率の悪い零細農民は土地を没収されて失業者の群れに投げ込まれ、一方、農場主は大規模化した農地でますます生産力を高め、こうして市場に出てくる農産物は過剰になり、農産物価格は下落する。経営不振で農地を手放す農民が続出し、彼らに機械化投資をしていた地方銀行の倒産があいついだ。この農業恐慌が1929年の世界大恐慌の間接的な原因となった。
また、トラクターは革命と戦争をも牽引した。第1次大戦中に帝政を倒して生まれた革命ロシアは、アメリカのトラクターを輸入して農業の集団化を推し進めた。一方、イギリスとフランスは競ってキャタピラー・トラクターを改良し、塹壕や湿地帯を踏み越える戦車を開発し実戦に投入した。なかでもドイツは「農業用」だと偽って、ベルサイユ条約で禁止されていた戦車を秘密裏に製造した。こうして第2次大戦時にはほとんどのトラクター企業が戦車開発を担うようになり、それによって犠牲を拡大した。トラクターと戦車はジキルとハイドのような双生児の様相を呈した。
また、トラクターは人間と自然との関係にも変化をもたらした。トラクターは家畜と違って糞尿を出さないため、大量の肥料を農場外から購入しなければならなくなり、農場内の物質循環を断った。それにかわったのが化学肥料だが、化学肥料の増産と多投によって土壌の団粒構造が失われ、さらさらの砂になり風に煽られて、アメリカの大都市は昼でも夜のように暗くなる現象が起こった。土壌は、微生物や昆虫、水分、天候、そして人間の耕作によって微妙なバランスの下に保たれている生命空間だが、これが損なわれたのである。戦後これがアフリカに持ち込まれ、砂漠化を促している。
本書はトラクターと日本とのかかわりも詳しい。日本は農地面積当たりのトラクターの台数は世界一である。そのなかで、戦前の日本農業の機械化の中心は岡山だったこと、干拓地の重粘土質の土壌を掘り起こす重労働から農民たちを解放したいという願いから国産の歩行型トラクターが生まれたこと、そしてその開発史の背景にソ連の農業集団化への憧れがあったということは、本書で初めて知ることができた。
では、トラクターは人間を自由にしたのだろうか? 確かに家畜の世話や長時間の耕耘労働、農作業の疲れから人間を解放し、農業生産力は飛躍的に高まった。しかし戦後の日本を見ても明らかなように、政府が田植え、代掻き、収穫、脱穀、乾燥というすべての作業の機械化を推奨するなかで、高額な機械代や肥料代とそれにつぐなわぬ低い生産物価格のもとで、農家は多額の借金を抱える「機械化貧乏」状態に陥り、農業をやめて都市に働きに出る者が続出したのが現実である。
また、食と農の世界そのものが、機械だけでなく種子、肥料、農薬から流通、小売りまでひとにぎりの巨大なグローバル資本の手に握られており、アフリカに種子や化学肥料、農薬、耕耘機レンタルをセットにした「食料増産」という名の支援パッケージを押しつけ、収奪の対象にしている。著者はこれを「農業そのものを農地の外からの管理作業に変え、人類史から消滅させる試みの始まり」と見ている。こうしたところに、資本主義社会の終末期的な矛盾があらわれている。他方、社会主義をめざしたソ連や中国でも、資本主義に変質した後はトラクターが個人所有に戻され、生産・流通は市場原理の下におかれて、すさまじい貧富の格差拡大となっている。
この現状を打開する道はあるのか? 著者は最後に、こうしたソ連型・中国型ではなく、またアメリカのような多国籍企業による大規模化でもなく、トラクターや機械を共有したもとで生産者が協同して働き、それと不可分な形で共同炊事や共同育児がおこなわれるような形で、人間と人間との関係、人間と自然との関係を再構築することを提起しているが、この提起に注目したい。現実にこれと同じ共働・連帯の志向を持って、各地で子ども食堂など住民の自発的なとりくみが勢いよく広がっており、ここに新しい時代の息吹があると思うからだ。
(中公新書、270ページ、定価860円+税)





















