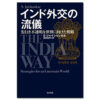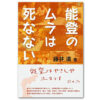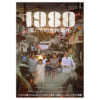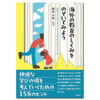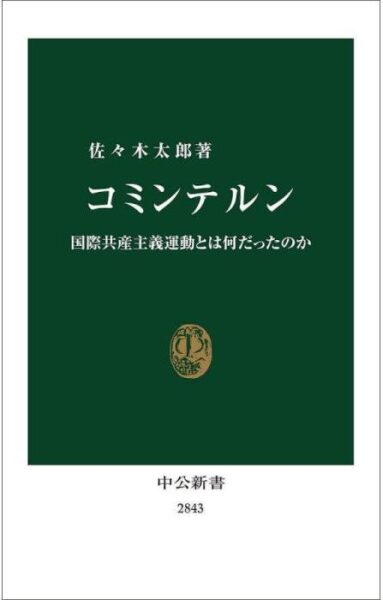 かつて、20世紀のおよそ約四半世紀にわたって、コミンテルン(第三インターナショナル)という組織が各国の労働者階級を中軸にした革命闘争の司令塔として存在した。日本や中国など各国の共産党はコミンテルンの一支部として設立された。この組織は第一次世界大戦後、10月革命を導いたロシア共産党(ボルシェビキ)と当時、革命情勢にあったドイツ共産党を中心に結成され、第二次世界大戦の最中に解散するまで激動する現代史に大きな影響を与えた。
かつて、20世紀のおよそ約四半世紀にわたって、コミンテルン(第三インターナショナル)という組織が各国の労働者階級を中軸にした革命闘争の司令塔として存在した。日本や中国など各国の共産党はコミンテルンの一支部として設立された。この組織は第一次世界大戦後、10月革命を導いたロシア共産党(ボルシェビキ)と当時、革命情勢にあったドイツ共産党を中心に結成され、第二次世界大戦の最中に解散するまで激動する現代史に大きな影響を与えた。
それにもかかわらず、その後は米ソ冷戦構造のもとで、コミンテルンについて語ることがはばかられるような風潮が続いたといえる。著者は今日の時点に立って、コミンテルンについてのこれまでの先入観――ソ連や各国共産党が流布した「公式史観」、一方で反共主義によるコミンテルンへの中傷、雑多な陰謀論など――にとらわれるのではなく、ソ連崩壊後に公開された当時の情報機関の内部文書なども検証しつつ、コミンテルンの実像を描き出そうとしている。
著者は本書執筆の動機について、今の時代の閉塞状況を根本的に打開する方策をさぐるうえで、その淵源を避けては通れないという思いを吐露している。巨大な階級的格差のもとで食べることすらままならぬ貧困が押し寄せ、戦争による虐殺がまかり通る今日において、「過去の時代から一貫して引き継いできた自由と平等をめぐる課題」に対してすら、安心して「主体的創造的な姿勢で向き合う」ことが躊躇される状況も垣間見える。そこに、「20世紀の壮大な実験の挫折」が解きほぐされない現実の一端を感じるからだ。
本書ではまず、マルクスが直接関わった国際労働者協会(第一インターナショナル)、エンゲルスとドイツ社会民主党が中心になって設立した社会主義インターナショナル(第二インターナショナル)の前史を踏まえて、コミンテルンが第三インターナショナルとして結成された事情を明らかにしている。マルクスは労働者階級は国境や民族の垣根を超えて団結すること、「万国の労働者団結せよ」の合い言葉で先進国の同時革命をめざしてこそ、国際的に結びついた資本の鎖を断ち切ることができるとの考えからインターナショナルを組織した。第二インターナショナルには社会主義政党や労働組合が参加し、そのような国際主義を発揚し民族排外主義とたたかうことを宣言したが、第一次世界大戦が迫るなかで、自国政府の戦争を支持するナショナリズムが支配的となり崩壊した。
ロシア社会主義革命は、第二インターの変節と一線を画して国際主義(各国の労働者がともに自国政府の戦争政策とたたかう)を掲げて、広範な労働者・農民・兵士の創意性が発揚されて実現した。レーニンは当時の欧米や日本の帝国主義列強による包囲・干渉、それと結びついた内乱のもとで、ドイツなど近隣の先進国の革命が実現しなければ、ロシアの労農権力は持ちこたえることができないと考え、コミンテルンの設立を急いだ。
著者は、コミンテルンがこうして創設されたことから、その後の運営においても国際主義と諸外国の民族主義との拮抗・対立、またソ連自身のナショナリズムの葛藤がつきまとわざるをえなかったと見ている。そのことは、西側資本主義国との直接的な戦争を回避するために各国間の対立・矛盾を利用するソ連の外交政策と、各国で革命を求める大衆運動をめぐる齟齬としても表れた。
コミンテルンの活動が以前のインターナショナルと大きく異なる点として、その対象が当時新たに勃興した植民地支配下の民族解放運動にまで押し広げられたことがある。メーデーのスローガンに「万国の労働者と被抑圧民族団結せよ」が加わるようになった由縁でもある。
著者はこうしたコミンテルンの戦略の変化について、第一次大戦後のドイツ革命が挫折し、「先進」とされたヨーロッパの革命運動が低迷・腐敗していった事情と重ねてとらえている。コミンテルンはそうした時代背景のもとで、東方のアジアにおける民族革命闘争の発展を労働者階級みずからの問題として重視し、その地で共産党を育てることに力点を置くようになった。
本書では、そのもとでコミンテルンの指導部がロシア革命のやり方を画一的に持ち込もうとして各国の社会的民族的実際と衝突したことや、ソ連の外交に従属させようとする傾向が各国の共産党指導部とのあつれきを生んだ事情を具体的にとりあげている。とくにそのような誤りが、中国革命を一時的に壊滅状況にまで追いやったが、その後中国共産党が農民が主体となった民族民主革命の路線を確立したことによって急速に転換していった経緯もたどっている。
ソ連防衛で各国の運動攪乱 第二次大戦下
とりわけ第二次世界大戦において、スターリン指導下のコミンテルンがソ連防衛の外交政策を変転させて各国の人民運動を攪乱した事情は、陰に陽に今の「左翼・リベラル」勢力の混迷につながっているようである。著者はとくに、ソ連が当初の「反ナチス(反ファシズム)」の外交政策から独ソ不可侵条約の締結へと転換し、ドイツがそれを破棄してソ連に侵攻して後、再び「ファシズム」を敵として「民主主義」を掲げる「連合国」の仲間入りをする過程と、それが各国の反戦・革命運動に与えた影響を浮き彫りにしている。
アメリカやフランスなどファシズムと対抗する国の共産党はコミンテルンによって、その政府の民主主義を称え「枢軸国」(ファシズム)との戦争を促進するよう求められた。つまり自国政府の戦争を支持・協力し積極的に参加することになったのだ。それはまぎれもなく、第三インターナショナルの崩壊を意味した。コミンテルンの解散は共産主義運動内部の国際主義と民族主義とのせめぎ合いにおいて、後者が勝利を収めたことからくる必然の帰結であったといえるだろう。
なお著者は、コミンテルンが組織運営において官僚的な体質を深めたこととかかわって、レーニンがへーゲルの弁証法哲学を推奨し戦略を発展させたが、それを党や組織の運営にまで貫けなかったのではないかと提起している。こうしたことも含めて今後の論議の発展が望まれる。
(中公新書、304ページ、1050円+税)