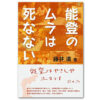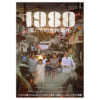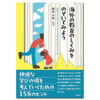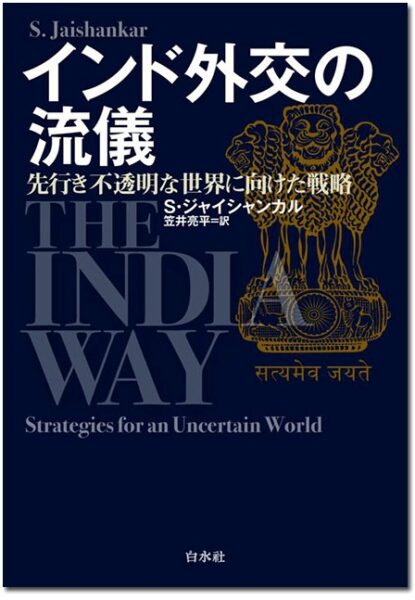
この本は、インドの現職の外務大臣の講演録である。著者は、40年間の外交官時代には、日本、チェコ、シンガポール、中国、アメリカの大使などを歴任した。
約14億人が住むインドは人口世界一であり、しかも若年層が多い。GDPでは米中独日に次ぐ5位で、今年度中にも日本を抜いて4位になるといわれている。世界にIT技術者を提供し、コロナ禍では「世界の薬局」(世界最大のジェネリック生産国)と注目された。BRICSの一員であり、グローバルサウスのリーダーとして世界の中で発言力を高めている。
著者がいうインド外交の基本的スタンスはこうだ。
アメリカは自国第一主義の強化、さらなる孤立化、大幅な支出削減をおこない、長きにわたり国際政治の中核だったものがその力を大きく低下させている。一方、それに代わって中国が大きな存在感を持って登場し、両者の確執が強まっている。
こうした力関係の変化の中で、今こそインドはアメリカに関与し、中国をマネージし、ヨーロッパとの関係を深め、ロシアを安心させ、日本により大きな役割を果たしてもらい、近隣諸国との関係を改善し、アジア・アフリカ・ラテンアメリカ諸国との友好関係とインフラ支援を拡大し、世界平和に建設的にかかわらなければならない。台頭する大国に対しては、距離を置くべきではなく、対抗する国々の疑念を和らげていく必要がある。インドが世界への関与を拡大しているのは、単なる功名心にとどまらず、「皆の協力、皆の発展、皆の信頼」という根本的な願望からくるものだ。
一方インドは、クアッド(日米豪印戦略対話)に加わるとともに、上海協力機構(中国、ロシア、中央アジア諸国などで構成される地域機構)にも参加しており、以前から続くRIC(ロシア・インド・中国)の枠組みとともに、JAI(日本・アメリカ・インド)の枠組みにも加わっている。
著者は、こうしたことは経験不足の人や時代錯誤的な思考の人からは、矛盾したアプローチに見えるかもしれないが、われわれはただ、定説にとらわれずに広く目を向け、見解が一致する点で協力するという是々非々の態度をとっているだけだ、とのべている。互いに競合するプレイヤーに同時に関与していくことで、世界のあらゆる経路を活用して自国の利益を追求している。何事も永遠不変なものはなく、世界の趨勢を正しくとらえることが重要であり、大国が自国優先主義を強めるなかで、インドの場合、ナショナリズムは国際主義の拡大をもたらしている、とのべている。
また同じ立場から、紛争をくり返してきた隣国のパキスタンに対しても、インドから友好関係を築いていきたい考えを伝えつつ、同時に逸脱した攻撃に対しては断固とした姿勢をとっており、それは矛盾することではないとのべている。
本書では、こうした外交政策の特徴を、国家論に関するインドの思想をもっとも凝縮したものといわれる『マハーバーラタ』の内容とあわせて読者に解説している。
大国一極支配から皆の発展へ 力関係変化の中で
では、インドがそうした行動をとる背景になにがあるのか?
著者は、ソ連・東欧が崩壊した直後、アメリカの政治経済学者フランシス・フクヤマが「自由主義世界が勝利し、その結果、戦争や政変のような大事件は起こらなくなる」とのべたことに触れ、「自信過剰な時代のなかで非常に傲慢な主張が展開された」「この自己満足はヨーロッパ中心主義からくるものだが、世界で起こっていることの無理解からくるものだ」という。だが、それはアメリカによる束の間の一極体制でしかなかったし、いまやグローバリズムが各国で深刻な格差や貧困を生み、破綻しているのが現状だ。
かつて中国人は「一世紀にわたる屈辱の歴史」といったが、インド人は二世紀にわたってヨーロッパによる蹂躙と略奪を経験した。インド人には、イギリス東インド会社とイギリス植民地政府によって、大規模な貧困、アヘン交易、奴隷化や飢餓がもたらされた。200年のあいだにインドから流出した富は、イギリスに持ち出された分だけで、現在の価値にすると45兆㌦にもなると推計されている。
そこからインドは、1947年の独立以来、米ソ対立の世界の中で非同盟主義の外交政策をとり、早い段階で脱植民地化を成し遂げた国として、より平等な世界秩序を追求しようとアジア・アフリカ諸国の先頭に立つことをめざした。
ところが「インドは非同盟政策を遂行しており、冷戦構造において西側についていない」という理由で、アメリカはインドを分割してパキスタンを誕生させた。インドの東に位置するミャンマーの軍事政権には制裁を加える一方で、インドの西に位置するパキスタンの軍事政権は同盟国として称賛してきた。また、中国の飢饉であれ、バングラデシュやカンボジアの大量殺害であれ、戦後に起こった深刻な悲劇をめぐっては、人道よりも米欧の戦略を優先し、世論の怒りを無視した。
さらに著者は、2003年のイラク戦争でアメリカは体制転覆というあからさまな主権侵害をおこなったため、そこからわれわれは、圧倒的な力を持つ大国に対抗すべく諸国が結集する「南南協力」のとりくみの重要さに気づいたのだ、といっている。そのアメリカはイラクで失敗し、アフガニスタンから撤退した。惨憺たるツケを住民に残して。
著者は、以上の歴史的経験から西洋の指導者は教訓をくみとるべきだ、と記している。インドは自分たちとは違った場所にあり、違った歴史を持っていることを理解すべきだ、と。
かつて植民地帝国イギリスの没落を身をもって経験したインド人が、今、戦後世界の盟主といわれたアメリカの没落を指摘し、国連改革など世界の新たな枠組みを提唱する言葉には説得力がある。日本は戦後の長きにわたって対米従属構造が続き、独自外交などほとんどない状態におかれてきた。そこからの脱却を求めるわれわれにとって、インドの外交政策に貫かれている徹底したリアリズム、物事を一面的・固定的ではなく柔軟にその変化発展をとらえる思考方法、利害や見解を異にする国であっても積極的にアプローチする姿勢など、学ぶべき点は多い。
(白水社発行、四六判・277ページ、定価3300円+税)