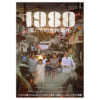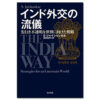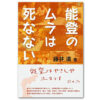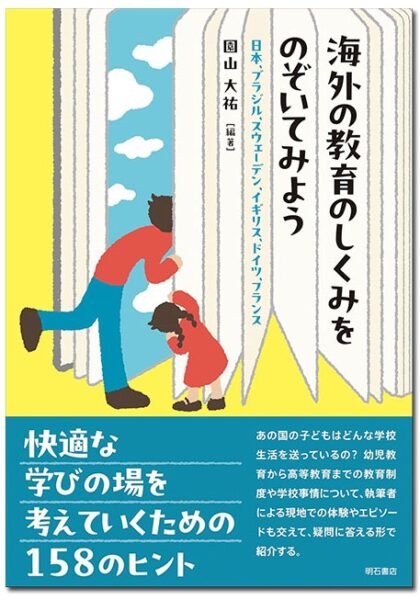 日本では「義務教育無償の原則」といいつつ親の負担は少々でなく、さらに大学に進学しようと思えば高額な学費が必要で、多くの学生が何百万円という奨学金の借金を背負って社会に出なければならない。諸外国はどうなっているのか?
日本では「義務教育無償の原則」といいつつ親の負担は少々でなく、さらに大学に進学しようと思えば高額な学費が必要で、多くの学生が何百万円という奨学金の借金を背負って社会に出なければならない。諸外国はどうなっているのか?
この本は11人の教育研究者や教員たちが、日本、ブラジル、スウェーデン、イギリス、ドイツ、フランス、アメリカ、シンガポールの学校教育の制度と実情をまとめたものだ。執筆者たちが、海外の学校を訪問し、教育行政担当者にあい、現場の教職員や保護者、生徒に聞きとりをして、個別のエピソードや肌感覚的な経験も交えて報告している。
ブラジル 給食も「国家の義務」で無償
まず、グローバルサウスのリーダー的存在であるブラジル。ブラジルは人口約2億人で、先住民と入植者であるポルトガル人、奴隷貿易で連れてこられた子孫のアフリカ系黒人、19世紀末以降の世界各地からの移民という多様な人々が生活している。
ブラジルの憲法は、4歳から17歳までの14年間を義務教育とし、すべて無償と規定している。公立学校であれば、授業料は無料、教科書は貸与性だが無償、ノートや鉛筆、ハサミ、ノリなどの学用品は年度初めに生徒に無償で配布される。制服が無償で配布される地域もある。ちなみにブラジルには小学校が10万校、中学校が6万校ある。
大学は公立(312校)と私立(2283校)があるが、公立大学も授業料は無償。私立大学の月額授業料は、日本円で7540円から45万円までさまざまだが、給付型(返済不要)の奨学金制度があり、試験の成績に応じて低所得家庭の学生たちに、学費の全額または半額の奨学金が給付される。
ブラジルの学校は半日制で、午前クラスと午後クラスにわかれており、夜間クラスが開設されている学校もある。2009年の法律で「学校給食は国家の義務」とされ、全国学校給食プログラムが始まったことで、給食は幼児教育から中等教育まで(0~17歳まで)、生徒すべてに無償で提供されている。半日制の小・中・高校では、午前クラスは朝食・おやつ・昼食の3食が、午後クラスでは昼食とおやつの2食が提供されている。
ただしブラジルは、かつてはポルトガルの植民地で、戦後はアメリカに後押しされた軍事政権が続いたことから、今も貧富の格差が激しい。25~64歳のブラジル人の5人に2人は高校を卒業していないし、今も経済的理由で高校を中退する生徒が多い。
最貧困層の若者の高校卒業率はわずか46%だが、これを84%まで伸ばせば国の富も大きく増えると踏んだ政府は、昨年、授業の出席率や試験の合否に応じて貧困層向けの現金給付制度を始めた。
スウェーデン 日本が学んだ教育の礎
次に北欧のスウェーデン(人口1050万人)を見てみる。日本は歴史的にスウェーデンの教育から多くのことを学んでいる。明治初期の岩倉使節団がストックホルムの男女共学の学校を視察しているし、1913(大正2)年には永井道明がスウェーデン体操教本を編集し、日本の学校体育の礎を築いた。スウェーデンの体育館で跳び箱やうんてい、平均台など日本と同じ器具を見ることができるのはそのためだ。
スウェーデンの義務教育は6歳になる年の秋学期から始まり、1~3年が基礎学校の低学年、4~6年が中学年、7~9年が高学年だ。スウェーデンも基礎学校は授業料、学用品、給食を含めて無料だ。教科書は学校で借り、ワークブックやノート、鉛筆も学校で配られる。遠足に行くときは学校がサンドイッチなどを用意するため、保護者が弁当をつくる必要はない。
高校も授業料は無料だが、教科書や教材、文房具などは自己負担になる。高校生にとっての最大のイベントはスツデンテンと呼ばれる卒業のお祝いで、高校最後の日、卒業生たちはクラスで用意したトラックの荷台に乗り、街を練り歩いて祝福を受ける。
スウェーデンには49の大学があるが、EU(スウェーデンを含む)、欧州経済領域とスイスの市民権を持つ人は、大学の入学申請料と授業料が免除されて、無料で大学に通うことができる。スウェーデンの市民権や永住権を持つ人は、返済不要の学修補助金と返済義務のある有利子学生ローンを受給できる。教材費や交通費は自己負担だが、補助金を申請することができる。
スウェーデンでも、法律で「栄養のある温かい給食を無料で提供する」ことが定められている。ただし、「日本の給食ほどの質は期待できない」という。給食は食堂でビュッフェ方式で提供されるが、子どもたちが自分で取り分けるため、ごく少量しか食べなかったり、パスタにケチャップを大量にかけたり、パンケーキにジャムをてんこ盛りにしたりと、好き嫌いで栄養が偏ることが問題になっているそうだ。
これについては日本の給食が、明治時代に始まった頃は貧困家庭の子どもに対する無料昼食であり、栄養摂取が第一の目的だったものから、戦後は「児童生徒の心身の健全な発達及び食育の推進」といった教育活動の一環として充実が図られてきたことが紹介されている。今、世界に誇る日本の自校式の給食が、民営化・大規模化して新たな問題が生まれていることも、あわせて考えさせられる。
部活の存在も注目集まる 日本の掃除
最後の座談会では、8カ国の学校事情が交流された。そこで注目が集まったのは日本の掃除だ。
日本では教室に加えて廊下やトイレ、音楽室などの特別教室の掃除を、班分けした生徒たちが、教師と一緒になっておこなうことが一般的だ。そのなかで自己の役割を自覚して協働することを学ぶ。他の7カ国がすべて、生徒は掃除をせず、民間の清掃業者に委託するのが当たり前なので、驚きを持って受け止めた外国人の研究者もいた。
ドイツの教育を紹介した研究者は、「日本から来てドイツの学校に在籍している生徒に出会ったことがある。その生徒はみんなの分まで椅子を机の上に載せて、教室を整頓して帰宅していた(ドイツでは放課後、清掃業者が来る前に、椅子を机の上に載せて帰る)。日本の掃除が公共のために役立とうとする道徳心を育てていることは、注目する価値がありそうだ」とのべた。ちなみに、部活があるのも日本とシンガポールだけだった。
こうした面がある一方、イギリスやフランスを含め紹介されている多くの国で、幼稚園や小学校から高校までの授業料や給食の無償化、さらには大学の授業料の無償化をおこなって、その国の将来の担い手を育てることに非常に力を入れていることに比べ、日本の政府や自治体のとりくみがいかに貧弱かが明らかになる。
執筆者たちは、「この本が学校現場で困っている児童生徒や教職員、保護者の何らかのヒントになればと願っている」とのべている。公教育に対する世界各国の考え方をわかりやすく知ることができる一冊だ。
(明石書店発行、A5判・272ページ、3000円+税)