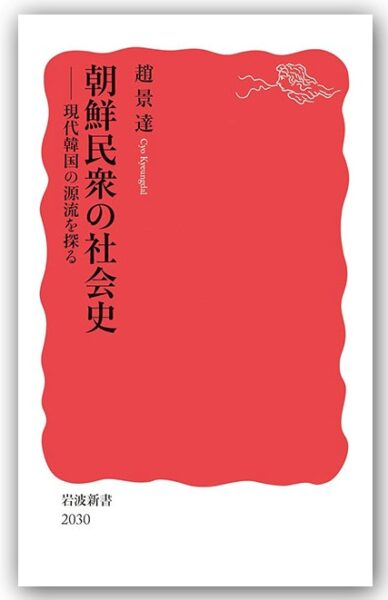
民族一体化をどう成し遂げたか
この本を読みながら、詩人・許南麒の長編叙事詩『火縄銃のうた』を思い出した。朝鮮戦争に向かおうとしている孫に対して、祖母が「祖父は甲午農民戦争をたたかい、父は三・一独立運動に参加した」と朝鮮民衆の物語を語る場面だ。
「朝鮮民衆の社会史」と銘打つこの本は、朝鮮王朝の成立(1392年)の時期から1919年の三・一独立運動までで、なかでも18~20世紀が中心だ。著者は「民衆がどのようにして民族の一体化を成し遂げ、挙族的な三・一運動に至るのかを探っていきたい」と執筆した意図を語っている。著者の趙景達(チョ・キョンダル)氏は元千葉大学文学部教授。
豊臣秀吉の朝鮮出兵へ憎悪
朝鮮王朝は1876年、封建制を維持したまま開国したが、それは日本や欧米列強との不平等条約に縛られたものだった。この本では19世紀後半の朝鮮民衆の意識として、壬申倭乱(豊臣秀吉の朝鮮出兵)の記憶に根ざした日本への憎悪があったうえに、開港以降の米穀輸出で日本商人に不当に買い叩かれ、みずからの飯米に窮するようになった農民が広範にいて、農民の困窮化や流民化が進み、そのなかで反日ナショナリズムが高まっていた点を指摘する。
甲午農民戦争(東学の乱)は、1894年1月の全準(チョン・ボンジュン)をリーダーとする全羅道の民衆蜂起が端緒となり、3月には4000人の農民軍が組織されて漢城をめざした。彼らは腐敗堕落した官僚を批判し、「世を救い民を安んじる」ために、閔氏政権を打倒し侵略者日本軍を駆逐して、国王に善政を嘆願しようとした。
農民軍は各地で歓迎され、沿道から加わる者も出た。5月にいったん和約が交わされた後は、農民軍は全羅道などの一部に自治都市を築いたが、そこでは「上下貴賤男女尊卑の別なし」という平等な共同体が目指され、窮民救済のための米穀を富裕層から徴発したりしたという。
これに対して日本軍は王宮を占領して傀儡(かいらい)政権を打ち立て、日本軍指揮下で日朝連合軍が農民軍殲滅(せんめつ)に動いた。秋の収穫が終わると、農民軍の第二次蜂起には数十万人の農民が参加したが、結局武力制圧されて、その死者は3万人とも5万人ともいわれる。「圧倒的な軍事力の差から、ほとんどジェノサイドといっていいような無惨な死に方」と記されている。
暴力的な武断政治の原型
日清戦争に勝利した日本は、1904年2月、朝鮮に軍事侵攻して日韓議定書を強要し、それを根拠に朝鮮全土の土地を軍用地や鉄道用地として収用し、民衆を軍事物資の運送役夫として駆り出した。また、軍隊とともに入り込んできた商人や土建業者が略奪や暴行などをおこなったため、これに朝鮮人が各地で反抗すると、日本軍は軍律を敷き、破壊活動には死刑を適用した。この過酷な軍律体制が、韓国併合後におこなわれる暴力的な武断政治の原型だ。
このことは否が応でも朝鮮民衆のナショナリズムを高めないではおかなかった。1905年の第二次日韓条約で大韓帝国が日本の保護領となり、続いて1907年の第三次日韓条約で韓国軍が解散となると、それを契機に軍人だけでなく農民や一般庶民がみずから武器をとり、義兵と称して日本軍との戦争状態に突入した。
『ロンドン・デイリー・メイル』特派員が書いた当時の記事は、日本軍が「反乱軍を傍観するのは反乱軍と同罪」といって、村々を見せしめ的に焼き払って破壊したため、かえって一般民衆を義兵側に味方させてしまっている、と記している。この反日義兵闘争の犠牲者も、甲午農民戦争に匹敵するものであったと推測されている。
1910年の韓国併合条約で、公式に朝鮮の植民地統治が始まった。天皇直属の朝鮮総督は軍事・司法・行政・立法の四権を掌握し、小天皇のように君臨した。憲兵警察は反日運動に対する情報収集と弾圧をおこなった。農民へのさまざまな課税と課役が強化され、農産物は安く買い叩かれた。
こうしたなかで1919年3月1日、ソウルのパゴタ公園で学生たちや一般民衆が独立宣言をおこない、「大韓独立万歳」を叫び、太極旗を掲げて市中行進を始めた。合流した人々は数万人に達し、市内各所で独立演説がおこなわれた。農村では農民たちが行進を始め、女子留学生たちは続々と帰国して運動を指導した。海州では妓生(売春婦)たちが指をかんでつくった血染めの太極旗を振りながら行進し、3000人を呼び込んだ。
この三・一独立運動は1年間継続し、参加者は200万人をこえた。これに対して宗主国日本は、朝鮮にいた軍隊や治安機関だけでなく日本からの援軍も呼び、逮捕・投獄・虐殺をおこなった。朝鮮人の死者7500人、負傷者1万6000人、逮捕・投獄4万7000人という記録がある。
韓国併合以降、民族意識の発露さえ封印されていた状態から、この全国的な運動と流血の弾圧を経験して、人々のなかで民族意識はかつてなく高揚した、と著者はのべている。それがまた戦後の独裁政権を打倒する民主化闘争へと引き継がれているのだろう。
一方、日本の政治家のなかでは、いまだに第二次日韓条約や韓国併合条約を「両国が対等な立場で結んだもので有効」とする理屈が横行しており、植民地支配による犯罪をなかったことにして向き合おうとしていない。しかも朝鮮に対する侵略と植民地支配は、日本国内における労働運動の弾圧や戦争の肉弾づくりとセットであった。
こうした態度では、近隣諸国との友好関係を深めることも、世界各国からの信頼を得ることもできないし、次の世代に平和を愛する民族としての誇りを受け継がせることなどできないと思う。
(岩波新書、292ページ、定価1120円+税)





















