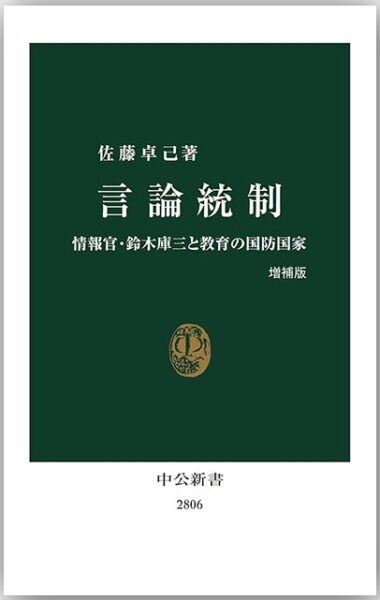 1950年に刊行された石川達三の小説『風にそよぐ葦』は、戦時中の軍部による言論弾圧に抗したインテリ群像を描いている。翌年には映画化され、全国上映された。
1950年に刊行された石川達三の小説『風にそよぐ葦』は、戦時中の軍部による言論弾圧に抗したインテリ群像を描いている。翌年には映画化され、全国上映された。
主人公の新評論社社長・葦沢悠平は、中央公論社社長・嶋中雄作をモデルにしている。「年の頃32、3の情報局情報官・佐々木少佐」のモデルは、陸軍少佐で情報官だった鈴木庫三である。ある日、葦沢は情報局第二部に呼び出される。葦沢は、「軍の意図するものだけを雑誌に盛る」というやり方に反論するが、佐々木少佐から「国家の立場を無視して自分の雑誌の立場ばかりを考えているからこそ、そういう自由主義の雑誌をつくるんだ。君のような雑誌社は片っぱしからぶっ潰すぞ」と恫喝を受ける。
このエピソードは、日米開戦10カ月前の1941年2月、中央公論編集部と情報局との懇談会で、情報官・鈴木庫三が「非協力的な」嶋中社長を恫喝した事件として、敗戦後になって出版された日本ジャーナリスト連盟編『言論弾圧史』(1949年)などで書き残されている。それだけでなく、岩波書店、講談社、実業之日本社など大手出版社の社史には、「鈴木庫三」は言論弾圧の代名詞として使われている。それが小説になり映画になったわけだ。
従来、戦後のジャーナリズム研究では、鈴木庫三はもっとも悪名高い軍人で、戦時中は非協力的な出版社を恫喝し、用紙配給を盾に言論統制をおこなった張本人とされてきた。著者はこれに疑問を呈する。「これまで強い軍部が弱い知識人をいじめたという構図が議論の前提だったが、はたしてこの前提は正しいのか」「記者、作家、編集者は軍部の被害者で、国家権力に激しく抵抗した者だけが英雄的に描かれることが多かったが、実際はどうだったのか」というのが問題意識である。
そこから著者は、遺された鈴木庫三の日記、戦時中から戦後にかけて記者、作家、編集者たちが書き残した文章、生存者への聞きとりなどを集め始めた。すると通説を覆す事実が続出したという。
石川達三は1937年12月、南京攻略戦に中央公論社特派員として従軍した。その後に書いた小説「生きている兵隊」が『中央公論』に掲載された。凄惨な戦場をリアルに描いたこの小説は、内務省から新聞紙法違反により頒布禁止処分を受けた。
記者、作家は「軍部の被害者」か
判決から2週間後、石川は名誉挽回のため、再び中央公論社特派員となって武漢攻略戦に赴いた。今度は軍部の意向に沿ったものにと「武漢作戦」を書き、『中央公論』に掲載された。このとき陸軍省新聞班にいて従軍文士を叱咤していたのが鈴木庫三である。
石川は「武漢作戦」刊行後、文芸興亜会の会則編纂委員、日本文学報国会実践部長など戦時下の文壇要職を歴任し、「極端に言うならば私は、小説というものがすべて国家の宣伝機関となり政府のお先棒を担ぐことになっても構わないと思う」(『文藝』1943年12月号)などと主張している。鈴木庫三とは、日米開戦後いくつかの雑誌で一緒に登場すらしている。
これは石川達三だけではない。当時の多くの芸術家は、芸術家の名に値する批判的精神を持たず、権力の要求に屈従し、お追従をいい、ただ食うためと虚栄心の満足のために世にも哀れな権力のチンドン屋となって、人々を戦争に駆り立てる犯罪的役割を担った。
この本の中にも当時の雰囲気をあらわす証言が幾つもある。その一例が、1940年2月3日の四大総合雑誌『中央公論』『改造』『文藝春秋』『日本評論』編集部と陸軍情報部の親睦会だ。
「(4社のインテリの代表者たちが)有名なヒゲの藤田中佐とか、何々中佐とかいうような将校たちとも、ドテラ姿で酒を酌み交わし、さては芸者とともに踊り、時にはそのまま一夜を共にする者もあったが、明くれば、また同じ浴槽の中で、他愛もない話に興じ、また朝酒が始まるというようなこともあった。これが知的な編集者の振舞いかと疑いたくなる」
天皇制政府・軍部と編集者や作家の癒着のなかで、戦前の雑誌の絶頂期は日米開戦直前の1940年まで続き、庶民の貧窮をよそ目に、「出版バブル」と呼ばれた部数の急増となって大もうけをしていた。
ところが天皇制軍国主義は戦争に敗北し、アメリカが日本を単独占領した。アメリカはすべての戦争犯罪を東条英機ら軍部にかぶせ、天皇を傀儡(かいらい)として支配機構を従え、日本の新たな支配者になった。持ち込まれたデモクラシーの波の中で、軍国主義者から民主主義者へと身軽に飛び移ったのもこうした連中だった。
敗戦後は“民主主義者”へ転身
そのなかで『風にそよぐ葦』は反戦小説として持ち上げられ、共産党機関紙『アカハタ』も高く評価した。だがそれは、「軍部に抑圧された言論」という構図を打ち出すことによって、みずからの過去を忘却したいという願望が込められていると著者はいう。
敗戦後の様子をあらわす証言もある。
「(編集者の無節操として)戦争の末期には軍の報道部に入りびたり、帰還兵の作家に書かせては巨利を博し、戦い終わると同時に帰還作家を戦犯扱いにして上田広や火野葦平には寄りつかず、小島政二郎の色情文学や暴露小説のたぐいで再び巨利をうかがう」
「高圧的な戦争美術論を終始展開していた評論家までが、“問題は必要以上に軍と協力し戦争を鼓吹した陸軍美術協会の幹部にある”と提唱する。占領軍の戦争犯罪者追及のお先棒を担いで、新たな“新生日本”のデモクラシーの鬼たちが跋扈(ばっこ)して狂った季節を現出させている」
時流に乗り権力のチンドン屋となって、みずからを欺き他も欺く流れは、戦時中だけでなく、敗戦後から現在まで続いている。著者が提起している問題は、現在を生きる文化人・知識人、あらゆる表現者にとって他人事ではない。今の世界を見る目は曇っていないか、真実を追求する姿勢は確かなものかを問うものだ。
この本は、2004年に出版された『言論統制』に、その後発掘された新事実・新資料を加え、増補版として今年4月に出版された。著者は、上智大学文学部新聞学科教授。
(中公新書、592ページ、定価1500円+税)





















