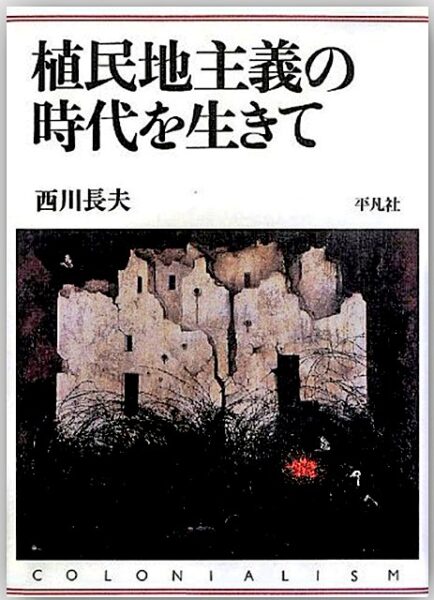 昨年10月以後、パレスチナ情勢が急展開するなかで、16世紀の大航海時代から500年におよぶヨーロッパ中心の植民地主義を根底から見直し克服する課題が、専門家・研究者の間で切実に論議されるようになった。そこでとりあげられる一つの問題は、欧米の宗主国が「文明化の使命」として「野蛮」なアフリカやアメリカ大陸、中東にいたるアジアの先住民を白人に従わせ、それに抵抗するものは抹殺(絶滅)を厭わなかったことであり、その行為を正当化する価値観が今日まで尾を引いていることだ。
昨年10月以後、パレスチナ情勢が急展開するなかで、16世紀の大航海時代から500年におよぶヨーロッパ中心の植民地主義を根底から見直し克服する課題が、専門家・研究者の間で切実に論議されるようになった。そこでとりあげられる一つの問題は、欧米の宗主国が「文明化の使命」として「野蛮」なアフリカやアメリカ大陸、中東にいたるアジアの先住民を白人に従わせ、それに抵抗するものは抹殺(絶滅)を厭わなかったことであり、その行為を正当化する価値観が今日まで尾を引いていることだ。
「朝鮮植民地なかった」 世界史の流れの産物
このことは、ユダヤ人の虐殺(ホロコースト)は大問題となるが、それと同時代にあった植民地における先住民の虐殺はなんの問題にもされてこなかったことに、よく示されている。こうして植民地がなかったかのような風潮が、宗主国の為政者はもとより国民の間にも根強くはびこってきたことは否定できない。
日本における「朝鮮植民地はなかった」「日本は朝鮮の近代化のために良いことをした」などの言説もそうした世界史の流れの産物であり、それ自体が「植民地主義の現象」だといわれる。戦後日本の植民地主義の研究で知られる西川長夫・立命館大学名誉教授(故人)は『植民地主義の時代を生きて』(平凡社、2013年)でこうのべていた。
「西洋の膨張としての近代は、新世界と旧世界の住民たちに対する侵略、略奪、殺戮、武力による支配と抑圧、ペテンと搾取、等々といった恐るべき暴力によって始められ、そして世界の4分の3が植民地化されたという厳然たる事実があるにもかかわらず、輝かしい魅力的な衣装を纏って登場しています。その輝かしい衣装とは、文明や科学、都市、芸術、宗教、さらには革命や人権や民主主義やヒューマニズム、等々、あるいは自由・平等・友愛といったモットーを加えてもよいでしょう」
「人権を掲げる先進国、つまり旧宗主国の人権宣言以後も植民地や奴隷制度を保持し続けていたこと、宗主国が植民地の人権に配慮するのはむしろ、植民地が独立して以後の時代であることは、歴史が示す通りです。人権が先住民にまで及ぶには、先住民の長い闘争の歴史が必要でした。またこうしたいわゆる先進国においても住民の全員が必ずしも人権を尊重されているわけではない。アフガニスタンやイラク戦争の例を生み出すまでもなく、人権の旗の下に多くの人権無視が行われてきました」
また、「“文明化の使命”が植民地支配の合言葉となり、悪を善といいくるめる弁明の言葉となっていたことは周知の事実」だが、日本の台湾出兵や朝鮮「併合」のイデオロギーも「文明化の使命」であったとのべている。同時に、西川長夫は戦後日本における「植民地の忘却」、自覚できない植民地主義がどのように生じたかについて問題を提起してきた。
アメリカ占領下の日本 引揚後の強烈な違和感
その一つが『言語文化研究』(2007年9月号、立命館大学国際言語文化研究所)に発表した対米従属下の戦後日本社会における「植民地の忘却」についてのシンポジウム報告である。そこでは、植民地主義にこだわるみずからの意識の根底には、日本の植民地であった朝鮮、満州で育ち、戦後1年近く北朝鮮に抑留されるなど引揚者としての辛酸をなめた自身の体験とともに、引き揚げ後のアメリカ占領下の日本の風潮への違和感がぬぐえずにきたことをあげ、次のようにのべている。
「米兵と腕を組んで歩く派手な姿の女たち、進駐軍のジープを追いかけてガムやチョコレートをせがむ子供たちを見た時の衝撃、それはまさしく植民地的風景」だった。「小学校の授業や休み時間の遊びもすっかり変わって、学校では英語講師が巾をきかせ、休み時間は野球」であった。こうした「占領下の日本の屈辱的な現実を長い間受け入れることができなかった」。その違和感は、「それが植民地的であるということにこだわり続け」る基点となった。
一方で日本社会では全体として、660万という人口の1割に近い旧植民地からの引揚者があり、また占領下という植民地的状況にありながらも、植民地という言葉と植民地問題が忘れられていった。日本の植民地放棄が「植民地忘却」に結びついたという指摘だ。
「引揚者や復員兵は、かれらの植民地体験を伝えるというよりは、戦後日本人の負の部分として口を閉ざし肩身の狭い思いで生きてゆくことになる。他方、国内における植民地主義の遺制とも言うべき在日朝鮮人(約200万人のうち50万が残る)や中国人その他の存在も、植民地主義の残された現実を戦後の日本人につきつけるというよりは、むしろその現実から目をそらさせるというように作用した」。そのうえ、「占領軍(GHQ)は、彼らを“解放人民”として勝者の側に位置付ける」一方で、「占領下の秩序を乱す危険な存在として支配・管理すべき対象」と見なした。こうして、「日本人の植民地の記憶と体験は密封された」。
西川長夫は、このように意図的に操作された「植民地忘却」は「アメリカ軍を中心にした占領政策がめざした」ものであったが、同時に「日本の政策」でもあり「戦後において植民地研究は学界における一種のタブー」とされてきたと指摘している。さらに戦後日本が「一種の鎖国状態」に置かれ、占領下において学問的にも「植民地研究」が歓迎されなかったのは、「占領自体が一種の植民地化であったから」だと提起している。こうした植民地主義にもとづく日本占領について掘り下げた研究は日本の歴史学界からではなくジョン・ダワーらアメリカの歴史研究者が先行したことや、日本の研究者が自国の占領期について研究するのに、いまなおアメリカに出かけてその資料に依存しなくてはならない状況にも示されている。
アメリカの日本占領 植民地を感じさせない
アメリカの占領政策は「日本人に占領を植民地化と感じさせなかった」という点で「きわめて巧み」であった。そのために占領期以後も「植民地に対する関心とともに植民地主義に対する感性、つまり自分が現に植民地的状況にあり今すでに植民地化されていることに対する感性、あるいは戦後の経済進出が形を変えた植民地主義であることに対する認識を失わせるよう作用」したという。それはかつてブッシュがイラク占領を「日本モデル」でおこなうと公言し、今、イスラエル政府要人がパレスチナ占領、ガザ地区での民間人の虐殺をアメリカが日本に原爆を投下したようにやるといって恥じない状況につながっている。
「広島と長崎は誰の目から見ても人類史に例を見ない残虐行為である。それを告発しないで、自ら“私たちの過ち”とみなし、毎年の例祭を続けるとすれは、それは占領期以後の日本が米国の植民地主義の支配下にあることの、紛れもない証拠となるだろう。過酷な戦争を早く終えるための有効な手段であったと言ってその正当性を主張する者が、原爆投下前後の状況と原爆のもたらした、そして今も続いている被爆者の災害を知った上でそう言えるとすれば、彼は狂っているにちがいない。彼を狂わせているのは、圧倒的な軍事力と経済力に支えられた植民地主義帝国の無知と傲慢に違いない」(『植民地主義の時代に生きて』)





















