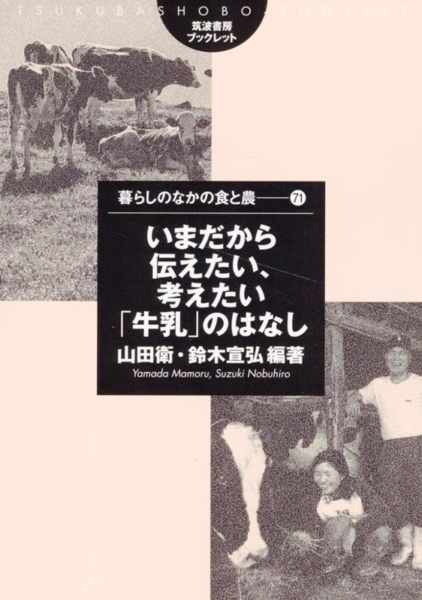 人間生活の基本である衣食住のうち、その不足がただちに生死に関わるという点で「食」が最も重要であることはいうまでもない。現在、物価高で食費を削る家庭が増え、ろくに食べることができず餓死者まで生まれる一方、生産現場では需給ギャップによって過剰生産に陥り、減産したり、せっかく育てた農産物が大量に廃棄されることもある。
人間生活の基本である衣食住のうち、その不足がただちに生死に関わるという点で「食」が最も重要であることはいうまでもない。現在、物価高で食費を削る家庭が増え、ろくに食べることができず餓死者まで生まれる一方、生産現場では需給ギャップによって過剰生産に陥り、減産したり、せっかく育てた農産物が大量に廃棄されることもある。
求める人(需要)があるのに生産力は縮小する――。現在起きている酪農家やコメ農家の危機は、国境をまたいだグローバル金融資本やそれに連なる独占大企業が「食」の市場を支配するなかで生じる矛盾としてあらわれており、国民生活の安定や健康維持を担保すべき「公」の機能破壊とも無関係に論じることはできない。本書は、東京大学大学院特任教授・鈴木宣弘氏の問題提起、千葉県の酪農家・大塚優氏の酪農業についての回顧、生活協同組合である「生活クラブ」が母体となって設立して40年間稼働してきた千葉県の牛乳工場「新生酪農」顧問・河野照明氏の経験談などからなっている。
酪農危機を招いた国策 くり返される国内切り捨て
現在、日本国内ではバターの在庫不足で店頭小売価格が値上がりし、パン屋やケーキ屋などでは国産の業務用バターが品薄のため値上がりどころか手に入らないケースも出ている。国産を使用してきた店では輸入品に切り替えると風味が変わってしまうため、頭を抱える業者も少なくない。
そこで6月26日、農水省は今年度のバターの輸入枠を当初より4000㌧増やし、1万4000㌧にすると発表した。生乳換算で約5万㌧の増加だ。これはたとえば山口県の年間生乳生産量が約1万5000㌧なので、その3・3倍に匹敵する。農水大臣は昨年が猛暑だったため生産量が落ちたと説明しているが、それは副次的要因だ。
酪農業界では2014年にもバター不足に陥ったが、そのときから国は増産のため「畜産クラスター事業」として設備拡大のための融資条件を緩和し、生産者に規模拡大(飼養頭数を増やし、牛舎の拡大や機械化を進める)を促した。酪農家は巨額の借金を背負って増産に励んだが、それが軌道に乗ってきたところで新型コロナ禍に直面。飲食業の休廃業や消費者の経済的困窮から需要が落ち込み、学校給食もなくなったため牛乳や乳製品の在庫が膨らんだ。だが、牛は生き物であり、蛇口をひねるように搾乳を止めるわけにはいかず、牛が死んでしまうためエサなどの経常経費も減らすわけにはいかない。そこに物価高によって生産コストは膨張し、低いままの乳価との挟み撃ちで酪農家は窮地に陥った。
各国では、将来のために国内の食料生産基盤を守るため、余剰となった食料を政府が買いとって生活困窮者への援助物資に回したり、値崩れした食料価格と生産コストの差額を埋めるために農家への所得保障を実施したが、日本政府はそれとは逆に農家に減産を要請。乳牛を処分すれば一時金を支給するとし、赤字補填はせずに脱脂粉乳在庫を減らすために酪農家に重い負担金を拠出させた。大手メーカーも乳価引き上げを渋ったため、廃業が増え、とくに国の号令に従って借金をして生産規模を拡大した農家には膨大な負債がのしかかって自殺者まで出た。
牛が生まれてから乳を出すようになるまでには、最低2~3年はかかる。農家が手塩にかけて育てた現役の乳牛の処分を奨励すれば、需要が回復したときに供給力が追いつかず、不足が起きるのは自明の理であり、農家そのものが倒れてしまえば回復の基盤さえ失われてしまう。現在のバター不足は、この国策が招いたものといえる。
日本は貿易自由化交渉のなかで、世界貿易機関(WTO)で定められた「カレント・アクセス」制度により、チーズやバターなどの乳製品を低関税で年間13万7000㌧輸入してきた。欧米諸国では国内生産者を守るために全量輸入はしていないにもかかわらず、日本だけは「国際約束」として全量輸入し、国内の乳製品はこれとの価格競争を強いられ、そのしわ寄せは生産者に回ってきた。「不足を補う」ことを理由にして輸入枠を増やすことにより、乳製品全体の輸入枠は生乳換算で18万7000㌧に更新され、窮地にある国内生産者の首をさらに絞めることになる。
公的支出なしに自給なし 食料安保の課題
現在、国際情勢悪化のなかで「食料安全保障」が国政において無視できない課題として浮上している。食料自給率37%の日本は、国として食料の生産力を維持し、立て直さなければならないことは誰の目にも明らかであるにもかかわらず、農産物の存亡を市場競争に委ね、対米従属の政治構造もあいまって物量で勝る海外製品を流入させて国内農家を淘汰の波にさらしてきた。飢える国民が増えているにもかかわらず減産するという大矛盾は、公の機能が働いていないことに最大の問題がある。
鈴木氏は本書のなかで、国による農家への価格補填や所得保障なしに国産を維持することはできないと訴える。たとえば現状、乳製品の4割は輸入品であり、その8割はチーズ。国内では飲用乳に比べて加工乳の買い取り価格は安く、なかでもチーズは長期保存が可能という理由で最も安い。その次に安いのがバターだ。これらの製品の生産過程で生まれる脱脂粉乳は需要が低く、在庫を抱えるリスクが高いため、国内ではバターの製造ラインを持っている工場が少ない。対して公的援助が手厚い米国では農協は必ずバターや脱脂粉乳の加工場を持っている。メーカーは利益の最大化が命題であり、国内農家の自助努力に頼るだけでは、対等な競争にもなり得ないのだ。
鈴木氏は、長期的対策として、政府が78億円から158億円規模の資金を投じて国内需要(買い取り)を創出し、輸入チーズを国産チーズに置き換えることができると主張。さらに260億円規模の予算を投じれば、チーズ用の低い乳価を引き下げ、国内メーカーにも原料の国産化を促すことができ、乳価引き下げ分を政府が酪農家に直接給付することができると指摘している。いずれにしても公的な財政支出なしに食料安保の根幹である食料自給を守ることはできない。
かつて戦後の食料難のなかでは、各農家が2~3頭の牛を飼って農耕の労働力にするとともに、乳は飲み、排泄物は堆肥として田畑に還すという完全循環が成り立っていた。それが貿易自由化の流れに呑まれて工業化するにともない、飼料は米国産トウモロコシや配合飼料にとってかわり、それらが止まればお手上げになる構造がつくられてきた。現在の日本の食料危機は、戦後80年をへた国際環境の変化のなかで、輸入依存の考え方が完全に破綻していることを意味しており、国民の生命と健康を守るために国として食料生産を保護し、それを担う生産者の下支えをする新たな国家制度をつくる必要性を突きつけている。
本書は、生産現場の実情にもとづいてこれらの農政課題を考えるうえで示唆に富んでいる。
(筑波書房ブックレット、80ページ、900円+税)





















