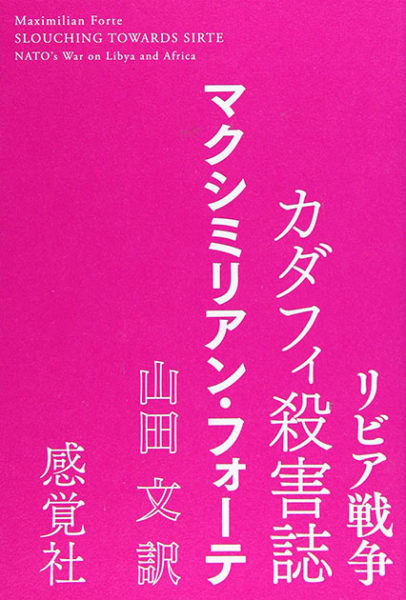
リビア革命の指導者カダフィが2011年、「アラブの春」による内乱とNATO軍の介入によって殺害された。欧米メディアは「カダフィの独裁体制」が崩壊し、自由と民主主義による新しい国づくりが始まると喧伝した。しかしその後10年を経た今、かつて繁栄を誇り汎アフリカ主義を主導していたリビアは、内戦が続き荒廃し、政治・経済は混迷を極めている。
当時、大量破壊兵器の開発計画を放棄し欧米と和解していると見られたカダフィを、欧米諸国がなぜ殺害する必要があったのか。著者(カナダ、コンコルディア大学社会・人類学部教授)は、この戦争にかかわった外交官、軍人、政治家、ジャーナリスト、人権活動家らが書き残した膨大な文書から、マスコミが伝えなかった現実を再現している。そして、「人道的介入」を掲げた欧米の軍事介入の実態と目的を、その背景とともに浮かび上がらせている。
欧米のマスコミはNATO軍の爆撃を「人命救助」「市民保護」のためだとして、それによって市民が保護されジェノサイドが防がれたと大きく宣伝した。しかし、実際にやられたことは、その真逆のことであった。
そのことは、一度攻撃を受けた死傷者を救助する人々や葬儀の参列者までも再度襲撃する「ダブルタッピング」と呼ばれる作戦がとられたことにはっきり示されている。著者は「もし彼らがこの軍事介入を“人道的”だと考えるのであれば、彼らはもっとひどいこともできるということなのか」と、投げかけている。
こうした蛮行が反政府派のリビア評議会と結託してやられた。著者はこのことも含めて、それが人権擁護のためではなくカダフィ体制を転覆するためだけにやられたことを明らかにしている。その目的達成を容易にするうえで、マスコミとともにアムネスティ・インターナショナルなど人権擁護団体、左派が果たした役割が大きかった。
現地の人権NGOを媒介に反政府勢力と結びつき、欧米に対抗的な体制を転覆させ、外資導入に道を開く。これは近年アメリカの覇権拡大の常套手段となっている。本書から、人権擁護団体が「人道主義」「民主主義」を大義名分に事実の誇張やあからさまなウソをばらまき、黒人リビア人への人種差別的な恐怖心を煽ってNATOの軍事介入を擁護し、その残虐行為や民族浄化を正当化するうえで一役買ったことがわかる。
これらNGOに資金を提供し支援しているのが、全米民主主義基金(NED)など政府資金で運営される組織や、アメリカの二大政党と結びついた全米民主党国際研究所(NDI)や共和党国際研究所(IRI)、さらにアメリカ労働総同盟・産業別組合会議(AFL・CIO)などの労働組合団体だ。一部NGOと米国務省のあいだの回転ドア、政官民エリート層のひんぱんな人事交流についてもふれている。
NATOの軍事介入は民衆反乱の方向をコントロールしようとする試みでもあったという。NDIはリビア国内で反政府関係者、人権派弁護士・学者、改革派活動家に直接つながると同時に、国外でさまざまなプログラムを立ち上げ、リビアの活動家に「新しいメディアテクノロジー、政治提言、女性の政治参加」についての研修を受けさせていた。そこでは、アルジェリア、エジプト、モロッコ、チュニジアの活動家と交流させ、たがいに連携・協力できるような手はずも整えていたことも明らかになっている。
著者は、リビア戦争はオバマ以降のアメリカの戦争の手法であることを、ウィキリークスが公開したアメリカ大使館の外交公電などを通して浮き彫りにしている。オバマはイラクでの失敗から、敵地に上陸占領せずに転覆する作戦をとり、「戦闘にたずさわることのできる年齢の男性はすべて戦闘員」だと再定義することで、無差別の空爆を正当化した。
著者はそこから、リビア戦争が世界的に衰退するアメリカによる「軍事的人道主義」の台頭を象徴するものだと指摘している。またそのおもな目的が「人命救助」「体制転換」それ自体にあったのではなく、カダフィやマンデラらによるアフリカの自立性を高める動きやその協力体制が築かれるなかで、それを阻みアフリカ大陸における多国籍企業の市場を開くための布石であったと結論づけている。
アメリカの戦争の旗印である「自由、民主、人権」が単なるプロパガンダではなく、具体的な行動をともなった戦略であることについて、具体的論理的に展開する一冊である。
(感覚社発行、B6判・528ページ、4300円+税)





















