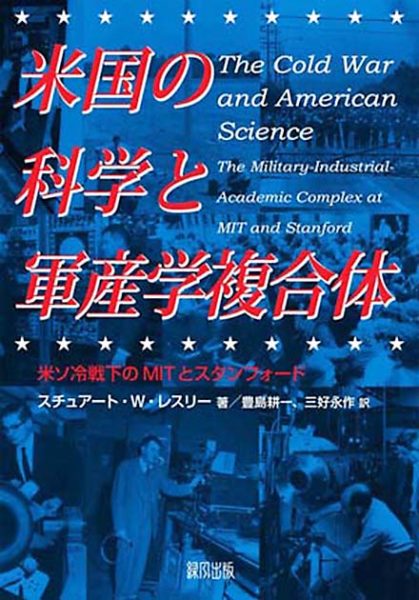
アメリカの戦後の軍事研究体制は軍、ハイテク産業界、研究大学による「黄金の三角形」と呼ばれている。本書はおもにその代表的な2つの理工科系大学、マサチューセッツ工科大学(MIT)とスタンフォード大学に光をあてて、研究者が軍事研究に組み込まれていった様子をドキュメンタリー風に淡々と描いている。そして、科学が軍産学複合体のもとで、いかに閉塞状態に陥るのかを構造的に浮かび上がらせている。
日本学術会議の戦後三度目の軍事研究を拒否する声明(2017年)によって、防衛装備庁の「安全保障研究制度」に大学の多くが応募しないことを確認し、応じないでいる。菅政府の学術会議に対する会員任命拒否と執拗な攻撃は直接的には、このことに起因していると見られている。本書で明らかにされるアメリカの大学における軍事研究の実態は、科学の分野はもとより、日本の社会現実を理解するうえで一つの手がかりとなるだろう。
アメリカの財界・政府は「第二次世界大戦の勝利」の主な原因を、マンハッタン計画による原爆開発はもとよりレーダーやロケット固体燃料など、当時の最先端の科学研究と技術の応用を大学・研究機関と産業とを一体化して動員したことに求めている。戦後、アメリカは世界の警察官として君臨するうえで、その体制を一貫して維持し強化する必要があったし、そのようにしてきた。
ジョンズ・ホプキンス大学の応用物理学研究所(海軍)、カリフォルニア工科大学のジェット推進研究所(陸軍)、カリフォルニア大学バークレー校のロス・アラモス武器研究所(原子力委員会)など、戦争に協力した大学の研究所は解散されることなく軍の機関が新しい契約で維持したり、永続的な計画が整うまで短期的な資金でつなぎとめていた。
朝鮮戦争がその面目を一新させる契機となった。著者はこのとき軍の資金が大量に産業界と大学の研究室に投入されたことで、アメリカの科学の戦争動員が完成し「史上はじめて大学が軍産複合体の全面的なパートナーになった」と指摘している。軍は大学との契約を「応用研究」と「機密研究」のための多額の予算で補い、大学が管理・運営する形でまったく新しい研究所を設立した。MITのリンカーン研究所(防空)、カリフォルニア大学バークレー校のローレンス・リバモア研究所(核兵器)、スタンフォード応用エレクトロニクス研究所(電子通信およびその対抗技術)などである。
トランジスター、電子管、レーザーなどエレクトロニクス分野における電気信号制御の工学的研究がアメリカの軍事研究をけん引し、空気力学、ソニック(衝撃波音)、超音速、マイクロ波、材料科学などの基礎科学の研究と、レーダー、ガスタービン、航空宇宙工学などの応用研究、さらにロッキードなど軍需産業の複合体が形成され、新型ミサイル(誘導弾)開発などの国家的事業が推進された。
その研究の中心にシリコン・バレーがあったこと、それが現在の、AI搭載のロボット殺人兵器やドローン、ミサイル防衛システムなどの開発につながっていることがよくわかる。また、その過程で学問の独自性が崩壊していったことも浮かび上がってくる。
そのもとで、アメリカの科学が軍事的な目的以外で世界を理解し変革する能力を劣化させ、形骸化させるのは必然であった。著者は「この半世紀にわたってアメリカの大学の自治と品位に対する脅威は国家から、より正確にはその軍事機関から来ている」とのべている。
軍事研究反対のストやデモ ベトナム戦争下で
本書ではベトナム戦争下の1969年、MITの研究者や学生たちがアメリカの科学が「軍機関の網の目により一層縛られていく」として、「軍事研究反対」のストライキやデモ行進でたたかったことにふれている。また、1983年にレーガン大統領がうち出した「弾道ミサイル防衛(SDI)計画」をめぐる研究者のたたかいのなかに、今日に引き継ぐべき教訓を見出している。
「スターウォーズ計画」と呼ばれたSDIには、300億㌦もの巨額の研究開発費が投入された。これに対して、MITの教員・大学院生は独自のアドホック委員会を立ち上げ、学長を先頭に「MITへの資金は武器システムの開発に関係すべきではなく、従ってSDIの資金は避けるべきである」と宣言。この機密研究への参加と機密保護の審査が「学問の自由の伝統」に真っ向から対立するとして反対した。
こうしたアメリカの研究者のたたかいは当時、日本の大学への米軍からの資金提供が露呈したこともあって、日本の大学が軍事研究に向き合う姿勢を論議しあう契機となった。それは、今日にいたる日本の科学者が細心の注意を払って、戦争への協力を拒否する根拠につながっている。
(緑風出版、A5判・376ページ、4000円+税)





















