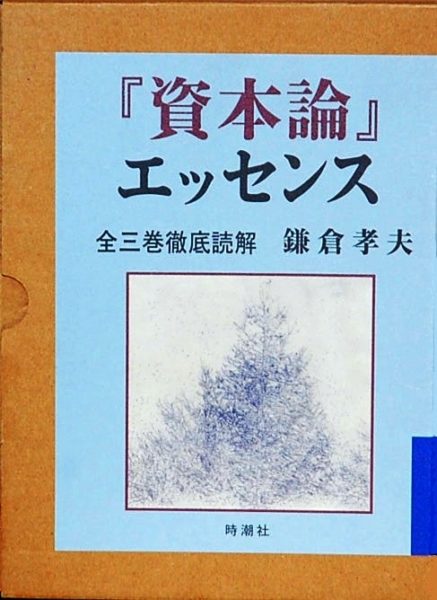
新型コロナウイルスの世界的な感染拡大のもとで、失業・倒産、飢餓、自殺者が一気に急増した。その一方でGAFAをはじめ一部の巨大企業と富裕層はばく大な富を集中させている。為政者の多くが目前の対策に右往左往するなかで、現場の労働者が社会を支え動かしている現実が浮かび上がり、自然と人間の関係、人間労働をとらえ直す機運が高まっている。それはコロナ後の社会の展望を模索しつつ発展している。こうしたなかで、『資本論』(マルクス)が若い世代の関心を集めている。
『資本論』理解の手引きに 長年の研究踏まえて出版
本書は長年にわたって『資本論』研究の第一線に立ってきた著者が、その学習の手引・指針となるようにまとめたものである。副題に「全三巻徹底読解」とあるように、『資本論』の論理展開に即してマルクスの提起を正確に読みとることを重視し、全体系のなかで各章の課題を明確にして理解が深まるように構成、論述している。
『資本論』はマルクスが第一巻を著した後他界し、エンゲルスがその遺業を継いで二巻、三巻をまとめて出版した経緯があり、その意味で未完成の作品だといえる。こうした事情も含めて、『資本論』の理解においては長年、正確さを欠いたり誤ってとらえる傾向があったとされる。第一巻だけで『資本論』のエッセンスがわかるといった風潮もそのなかにあった。
本書では、マルクスが哲学・歴史から経済学、さらに晩年の『資本論』にいたる学問的な格闘の過程で理論を純化・発展させていったことを、他の諸文献や書簡・ノートなどの分析を通して明らかにしている。著者は唯物史観や恐慌論などについて論理を変化発展させていった事情についてもくわしく展開し、社会科学における『資本論』の位置づけと、それが社会変革の理論的根拠となることを示している。
日常生活において「体が資本」「教育投資」などの言葉がかわされ、経済活動でも「元手となる資本」がなければ事業が起こせない。資本こそが社会の原動力であるかのように見える。しかし、なにごともそうだが資本の本質をその外面を追認し、推論・判断することからは把握できない。『資本論』によって、経済学史上はじめて資本の内部で働く諸要素の関連を動的にとらえそこに貫く法則を導き出すという科学的な方法で、資本の本質が解明された。資本の本質は商品と貨幣から構成される流通運動である。
『資本論』は資本を商品の売買の連鎖のなかでとらえ、資本の運動の目的が剰余価値の獲得(金儲け)にあることを明らかにしている。著者は第一巻「資本の生産過程」から第二巻「資本の流通過程」、第三巻「資本主義的生産の総過程」まで通して読むことで、資本間の競争や土地所有など資本主義の全体像とかかわって資本の運動法則が明らかになることを強調している。このことはとくに、株式・証券・国債、土地・不動産などが擬制資本として社会を支配する今日の状況を理解するうえでは、不可欠だといえる。
資本の運動過程において人間の労働力をとり込み、資本の過剰から無理が生じて恐慌をもたらす。それを形のうえで解消するための貸付資本(それ自身に利子を生む資本)、それを具体化した株式=擬制資本があらわれた。利子生み資本はそれ自体、生産過程での価値を生まないことから、その具体的形態は“擬制”でしかありえないのだ。
『資本論』から150年を経た今日、資本主義は株価至上主義のもとで、あまたの「金融商品」が出回り架空の繁栄(バブル)を生み出している。為政者・メディアは経済アナリストを動員して株価を基準に一喜一憂し、資本主義の複雑な経済現象は得体の知れぬものであるかのようにふるまっている。しかし、資本の極限的発展として体現した株式・証券の売買が実体経済に根ざさぬものであり、社会の実体は労働者の共同・連帯した生産活動であることがだれの目にも明らかとなっている。
さらにコロナ禍において、資本の論理によってねじ曲げられ破壊されてきた生態系と人間の関係を見直す論議が発展している。とくに人類社会の存立に不可欠な農業生産と食料の流通をめぐって、これを営利追求・価値増殖に取り込む資本の本質が露わとなり、生産者・労働者との対立が鋭さを見せている。自然観・人間観・労働観をとらえ直すうえでも、『資本論』は貴重な示唆を提供している。
資本の利潤追求を目的とする大工業による生産力の発展は、その生産力の担い手である労働者の労働力を乱用することで、労働者の肉体的・精神的破壊をもたらさざるをえない。『資本論』は同時に、それが土地の収奪による自然力(自然の循環法則)の破壊をもたらすことで農村でも労働力を無力にし土地を疲弊させ、ひいては「大工業」自体の破局をもたらすことを明らかにしている。
本書でも、労働過程が人間と自然(土地・水・森林・鉱山等)との物質代謝、つまり自然物を利用し加工しさまざまな生産物を生産する過程であることにふれて、人間労働はそれ自身は自然力であるが、自然に主体的に働きかけることによって自分自身の天性的に持っている能力を発展させることだと提起している。それが構想・計画を持った目的意識的な創造活動である点に、本能的に活動する動物と決定的な違いがあるのだ。
人間労働のこうした本性は、資本主義のもとでも社会の実体として貫かれている。問題はその生産過程が資本の側の目的意識的な支配のもとに置かれていることにあるだろう。
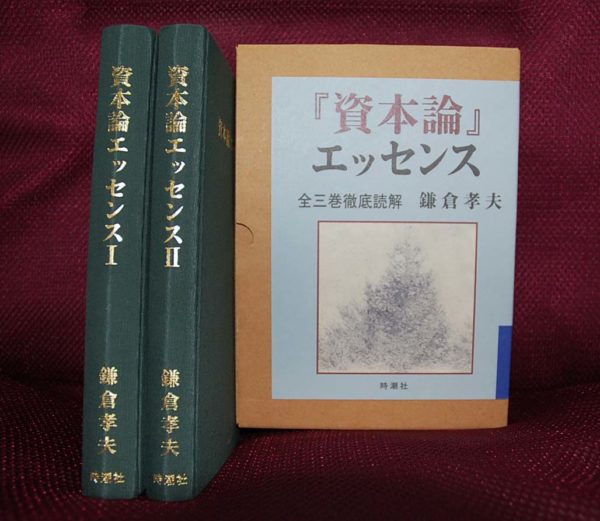
(時潮社発行、A5判・上製本、Ⅰ・Ⅱ巻セット、1万2000円+税)





















