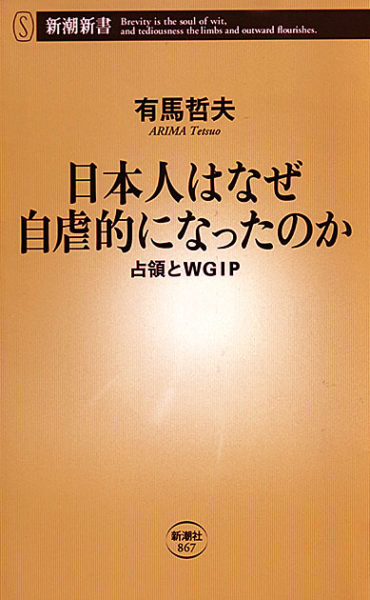 著者は早稲田大学教授(メディア論)。「先の大戦は、アメリカが日本軍国主義をアジア諸国から排除した戦争で、それは正義の戦争だった」「原爆投下は戦争を終わらせるために仕方がなかった」という考え方や、「中国の南京大虐殺などアジアへの加害」をとりあげて被爆体験の継承に難癖をつける考え方が、戦後日本の教育やマスメディアを通じて流されてきた。著者は、その根源はアメリカにあり、占領期にアメリカがつくったWGIP(ウォー・ギルト・インフォメーション・プログラム)がこの心理戦で決定的な役割をはたしていることを、欧米の公文書館にある歴史資料から実証的に明らかにしている。そこから第二次世界大戦の真実に迫ろうとしている。
著者は早稲田大学教授(メディア論)。「先の大戦は、アメリカが日本軍国主義をアジア諸国から排除した戦争で、それは正義の戦争だった」「原爆投下は戦争を終わらせるために仕方がなかった」という考え方や、「中国の南京大虐殺などアジアへの加害」をとりあげて被爆体験の継承に難癖をつける考え方が、戦後日本の教育やマスメディアを通じて流されてきた。著者は、その根源はアメリカにあり、占領期にアメリカがつくったWGIP(ウォー・ギルト・インフォメーション・プログラム)がこの心理戦で決定的な役割をはたしていることを、欧米の公文書館にある歴史資料から実証的に明らかにしている。そこから第二次世界大戦の真実に迫ろうとしている。
心理戦とは軍事戦にひき続いてアメリカが重視したもので、日本人の心を支配し、二度とアメリカに立ち向かうことができないようにする目的でおこなったものだ。すでに第二次大戦中から、陸軍や海軍、OMI(戦時情報局)、OSS(戦略情報局)に心理戦を担当する部局がつくられ、多くの社会科学とコミュニケーションの専門家が動員されるとともに、ジョージ・ギャラップ(世論調査の創始者)、フランク・スタントン(二大ラジオ放送網の一つのCBS社長)、エドワード・バレット(ニューズウィーク編集長)などメディア企業の幹部も動員された。
WGIPとは、「日本人の苦難の責任が日本の軍国主義者たちにあること」「連合軍の占領目的は日本に民主主義をもたらすためであること」「一部の日本人およびアメリカ人が原爆の使用は残虐行為であると考える傾向をなくすこと」「日本人に極東国際軍事裁判(東京裁判)を受け入れさせること」などの考えを刷り込むためにアメリカがおこなった心理戦のことだ。それはGHQのCIE(民間情報教育局)が実行し、戦時中から心理戦を担当してきたマッカーサーの側近、フェラーズ准将やダイク准将がその中核を担ったという。
ダイクは「私たちはまだ戦いの最中なのだ。右のジャブを打ったら、相手が立ち直る前に左のジャブを打たねばならない」といっている。
そこには最初から、日本単独占領を首尾良くやるために天皇をかいらいとして利用するという統一方針があった。だから東京裁判で天皇の戦争責任が免罪されるとともに、「国民全体が徹底的に反省し懺悔しなければならぬ」(1945年8月28日、東久邇宮首相の記者会見)という考えが刷り込まれた。非戦闘員の大量虐殺にほかならないアメリカの原爆投下や全国空襲は不問に付された。GHQは、日本のマスメディアを戦時中のまま存続させてそれを掌握し、占領政策の広報機関にすると通達を出した。
以上のような内容の洗脳をおこなうために、CIEは『太平洋戦争史』をつくって各新聞に連載させるとともに、その内容を全国の学校で教えるよう文科省に通達を出させた。また、同じものをラジオの『真相はかうだ』という番組で、CIEがシナリオを書き日本の俳優に演じさせた。
とくに東京裁判の準備として、「戦争中のマニラ」「南京の暴行」といった日本軍の残虐行為をとりあげることを重視せよとの指示を出している。
だがこの米占領軍の政策が、何の抵抗も生まなかったということはできない。本書のなかでも、当時のNHK職員が『真相はかうだ』について、「“真相は知りたいが、あの放送を聞くと何か悪寒を覚える。この解説者ははたしてわれわれと手をつないで日本の再建のために立ち上がる同胞であろうか”とはわれわれ周囲の大多数の見解であった」と書き残している。
戦後左翼といわれる人たちのなかには、戦前の天皇制軍国主義は厳しく批判するが、日本を占領したアメリカについて、まるで「民主主義の旗手」のようにみなす傾向があるが、そこにアメリカが日本占領のために持ち込んだマインドコントロールの影響があることを否定することはできないだろう。そして、この対米従属構造は現在も続いている。
著者自身、原爆投下はソ連の影響力を排除するためだったこと、戦後アメリカは岸信介ら旧体制指導者らを巣鴨プリズンから釈放し、CIAの秘密資金を与えて総理大臣になるのを助けたこと、今憲法九条を一番邪魔だと思っているのはアメリカの政治支配層だということを正しく指摘している。
同時に、東京裁判のためにアメリカが日本軍の残虐さを意図的に強調したからといって、戦前の日本軍国主義がおこなったアジアへの野蛮な侵略戦争や強制連行などの数々の非道な行為それ自体をなかったことにすることはできない。事実は事実として次世代に伝え、対米従属一辺倒でなくアジア諸国との平和と友好を模索することこそ、独立国としての誇りある態度ではないかと思う。アメリカも日本も、どちらの側からも植民地を奪いとるための戦争だったのであり、それによって幾多の兵士や銃後の国民が犠牲になったことを曖昧にすることはできない。
(新潮新書、286ページ、定価840円+税)





















