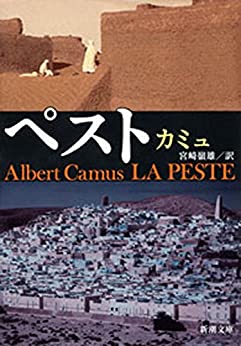 新型コロナウイルスの感染拡大が世界的に広がるなか、フランスの作家、アルベール・カミュが一九四七年に発表した『ペスト』が読まれているという。『ペスト』新潮文庫版は、例年5000部程度の増刷だったが、今年は2月以降だけで15万部をこえる増刷となっている。また、フランス、イタリア、イギリスでもベストセラーになっている。文学者などの意見をふまえつつ、どんな内容が共感を呼び、それによってどんな思想的営みが広がっているか考えてみた。
新型コロナウイルスの感染拡大が世界的に広がるなか、フランスの作家、アルベール・カミュが一九四七年に発表した『ペスト』が読まれているという。『ペスト』新潮文庫版は、例年5000部程度の増刷だったが、今年は2月以降だけで15万部をこえる増刷となっている。また、フランス、イタリア、イギリスでもベストセラーになっている。文学者などの意見をふまえつつ、どんな内容が共感を呼び、それによってどんな思想的営みが広がっているか考えてみた。
下関市の大手書店に聞くと、『ペスト』は「今年初めに数冊注文したが、その後もお客様からの問い合わせが続き、売れ続けている。コロナの感染が広がる今と重なるところがあるからのようだ」という。
下関市で教鞭をとるフランス文学の教員は、「今の社会状況とリンクするからだろう。授業でもとりあげたい」とし、「人間の力ではコントロールできない自然の脅威に囲まれ、それでも少しでも犠牲者を減らそうと懸命に努力して次の世代につないでいく。今回だけでなく、そのようにして歴史が積み重ねられてきた。今の危機的な状況のなかで、この本を読み、逆に落ち着いてそういうことを考えるようになっているのかなと思う」と話した。
作家の平野啓一郎は、「コロナとのたたかいは長期戦になる。だからこそ、目先のことでなく、これからの世の中どう生きていくかを考える時間にあてるべきだ。大きな時間の流れのなかで人間が疫病とどうたたかってきたかについて、本を読むこと。『ペスト』では、非常に大きな困難に直面するなかで、根性論ではなく、現状を克服するクリエイティブな知恵を出し合うことの大事さを学ぶことができる。日本を良い方向に変えるきっかけになればと思う」とのべている。
同じく作家の高橋源一郎は、「『ペスト』は2年前に終わった戦争やナチスをペストにたとえ、人間の力をこえた大きな力に襲われたとき、人々はどのように混乱し、どう立ち向かうかを徹底して
考えた小説だ。多くの人が亡くなったけれども、そのとき患者の命を救うために立ち向かった人たちがおり、その記憶は決して忘れてはならないし、それを次世代が引き継いでほしいということがいいたかったのではないか」とのべている。
『ペスト』は194*年、フランス領アルジェリアの要港、オラン市を舞台にしている。春先にネズミの死骸が次々と、数え切れないぐらい発見されるところから物語は始まる。続いて原因不明の熱病による死者が急増し、感染拡大を防ぐためにオラン市は封鎖される。外部とまったく遮断され、いつ終息するかもわからぬ閉塞感のなかで、オラン市の市民たちの10カ月にわたるたたかいの記録という体裁をとって書かれている。
6月末には真夏の気温上昇と1日の死者のうなぎ登りの上昇が一致するなか、町から出ることを重ねて禁止し、違反者には投獄の刑をもって臨む旨の布告が新聞に発表された。海は禁止されて夏の楽しみは奪われ、観光旅行は禁止されてホテルは空き室だらけとなった。電車の乗客はできるだけ背を向け合って互いに伝染を避けようとし、頻繁にただの不機嫌だけに起因する喧嘩が起こった。時とともに食料補給の困難が増大し、そこに投機が介入してきて、貧しい家庭ほど苦しい事情に陥った。棺桶も墓地も足りないなか、まさに戦場を思わせる埋葬の様子も描かれる。
極限の場は、それぞれの人間の本性を浮き彫りにする。医師リウーが「病気は48時間以内に死をもたらすペストであり、放置すれば2カ月以内に全市民の半数が死ぬ」としきりに主張した結果、ようやく県庁で保健委員会が招集された。だが県知事は、ペストと認めれば予算を伴う仮借ない措置をとらねばならないため責任逃れから尻込みし、県知事を忖度する医師がヨイショする。こうして初動に失敗し後手後手に回る様子は、日本の今を見るようだ。
事態打開のきっかけは、他県から来た医師タルーとリウーとの出会いだった。タルーは「県の保険部門の組織がまるでダメだ。あなた方には人手も時間も不足している」「当局に任せておいたら、みんなやられてしまう。しかも彼らと一緒にわれわれまでも」といい、当局抜きで志願の保健隊を組織することを提案する。「私の友だちが最初の中核になってくれるだろう。当然、私も参加する」というと、リウーも「この仕事は命にかかわる。でも大勢の病人がおり、目の前で苦しんでいるのだから、もっとも急を要するのは彼らを治してやることだ。その後で当局も反省するだろう」と一致する。経験のある老医師カステルは、外来の物でなく、この町を荒らしている菌自体の培養によって血清を製造する努力を始めた。
そしてカミュは、けっしてこの二人の医師だけを英雄にせず、事態の進行のなかで人間的な新しいモラルに目覚めた裏方の人たちにも光を当てている。最初はペストに神の懲罰を見、人々に悔い改めることを説いていたパヌルー神父は、罪なき幼児の死に直面したときそれを反省し、みずから保健隊に身を投じて病に倒れた。若い新聞記者ランベールは、最初個人の幸福が第一だと主張し、ペストの町を脱してパリの愛人の下に帰ろうと努力するが、「すべてを見た今、僕はもうこの町の人間だ。この町を捨てて彼女と再会しても、きっと恥ずかしい思いがするだろう」といって、縁の下の力持ちになる決意を打ち明けた。
この作品はフィクションではあるが、著者の戦争体験が深刻に投影しているというのは、多くの評者の一致した見方のようだ。カミュはドイツがフランスを占領したとき、仏領アルジェリア・オラン市の私立学校で教鞭をとりつつ、反ナチのレジスタンスに参加した。その真情は、カミュの分身でもあろうタルーの「僕は今の社会に蔓延する虐殺に、たった一つの根拠でも与えることは絶対に阻止しようと誓ったんだ」という言葉にもあらわれている。タルーは、市民がペストから解放され歓喜に浸っているときに、ペストによってリウーに見守られつつ帰らぬ人となるが、そのようにして亡くなった人を決して忘れず、次の世代にその遺志を受け継いでほしいという願いが込められていると思う。
それにしても、「もう政府に任せておけない。われわれみんなで人の命を救おうじゃないか」という力は、カミュの生きた時代よりも今の方が格段に強まっているのではないか。





















