
すずき だいゆう 16歳で米国に留学し、大学、大学院で教育学を学ぶ。帰国後、通信教育で教員免許を取得し、6年半、千葉の公立中で教壇に立つ。2008年に再渡米し、大学院博士課程へ。2016年、研究の成果である『崩壊するアメリカの公教育 日本への警告』(岩波書店)の出版を機に、一家で高知県土佐町に移住し、2019年4月に土佐町議会議員選挙でトップ当選。教育を通した町おこしにとりくんでいる。
--------------------------------
今、なぜいろいろな問題が子どもたちや学校現場で起こっているのかを考えたとき、それをとり巻く社会が鏡のように映し出されているだけだと思う。教育関係者は狭い教室や学校のなかで答え探しをするという罠に陥りやすいが、逆に子どもや先生たちに起きている問題を通して社会のあり方そのものを問い直すという作業が求められているように思う。
最初に自分の紆余曲折について話したい。私は16歳から大学院の修士課程までアメリカで勉強した。日本に帰って自分の目で教育現場を確かめてみたいという思いがあり、千葉で公立中学校の教員になった。当初から日本の教育全体に関心を持っていて、一人の教員として子どもの教育でやれることはたくさんあるが、日本の教育システムに対してできることは限られていると感じた。
当時、アメリカでは新自由主義教育改革といって市場原理をとり入れた斬新で大胆な改革がおこなわれていた。それを研究して日本に帰って教育システムを変えていきたいという思いを持って再渡米した。研究していくうちにつれて疑問点が見えてきた。何よりも自分の子育てを通して感じるところが大きかった。
私が在籍していたコロンビア大学はニューヨークのマンハッタンにあるが、同地域はアメリカ黒人文化の拠点の一つであるハーレムに隣接していた。最初はモーニングサイド・ハイツといわれる「山の手」の方に住んでいたが、再渡米2年目から家賃が安いハーレムの方に移った。
そして娘が小学1年生になるときに驚いた。ニューヨーク市は、学校選択制で20校を選んで教育委員会に提出するという制度だった。私は公教育にプライドを持っていたので「選ばないこと」を選んだ。その結果、フタを開けたら娘の同級生はみんなアフリカ系やラテン系アメリカ人だった【写真①】。アメリカは経済格差が肌の色、人種の違いとして出るのだ。もっと驚いたのが、学校に音楽、美術、体育の先生もいないことだ。さらにもっと驚いたのが貧困率で、8割以上が最低生活水準以下の家庭の子どもたちだった。さらに5人に1人がホームレスで毎朝違う場所から通学する状態だった。

【写真①】鈴木氏の次女が入学したクラス。ハーレムにおける人種隔離が顕著にわかる(鈴木氏撮影)
一方でわずか2㌔しか離れていない隣の学区では、音楽、美術、体育の正規教員がいる。その他にバレエ、バイオリンを専門に教える先生がおり、屋上にビニールハウスがあって、そこで栽培した無農薬野菜を給食でシェフが出してくれる。生徒たちの肌も明らかに白い。何が「公」で何が「私」なのかの境界が揺らいでいると感じた。考えてみれば20校の学校説明会に行くゆとりのある親、膨大な情報を精査分析できる能力のある親は限られている。「平等な競争」というがそれは幻想にすぎない。
ハーレムという貧困地域では、テスト教育を徹底的にやるが逆に音楽や美術といった感性を養うような全人教育をやっていなかった。自分はやれることを全部やろうと思い保護者会長までやり、校長と組んで感性を育てる教育にも力を入れていった。それによって生徒数はどんどん増えていった。残念で皮肉なのが、その学校は今ではエリート校になってしまって、生徒も白人が多くなって地元の子が少なくなっている。
私はどこでどの学校に行っても遜色ない満足のいく教育が受けられるのが公教育だと思っていた。
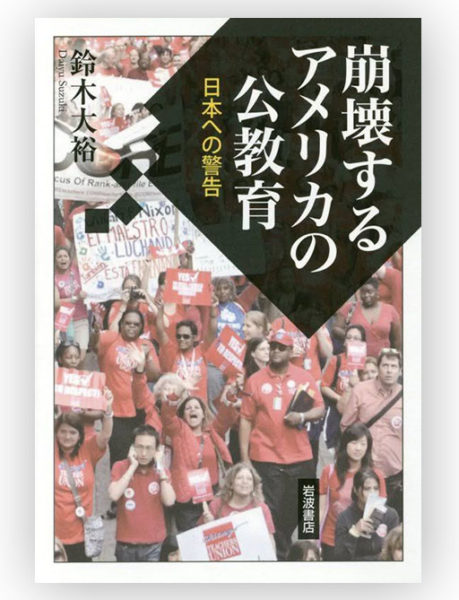
ところがアメリカでは経済格差が、教育格差となり、学校を通して格差社会を再生産しているように感じた。また、テスト対策ばかりをして塾と何が違うのかという疑問もあった。何をもって教育というのか。「公」と「教育」という民主主義社会の根幹をなす二つの概念そのものが崩壊しつつあるという問題意識を持った。2016年に執筆した『崩壊するアメリカの公教育:日本への警告』のタイトルはそのような思いからつけた。ではなぜアメリカではこのような格差が許されるのだろうか。
数値化で子どもを管理 投資削り競争煽る
1983年のレーガン政権のもとで『危機に立つ国家』という報告書が出された。アメリカの公教育が危機的な状況にあり、読み書きも満足にできない子どもたちが多く、このままいけばグローバル経済における国家の衰退は目に見えている、という内容をセンセーショナルにうち出した。問題の根幹は富裕層と貧困層の教育格差にあり、読み書きができないのは貧困層の子どもたちで、教育予算もままならず十分な教育を受けられていないからだった。本来は、富の再分配をおこない、貧困層の子どもたちの教育を手厚くするという選択肢もあったが、アメリカがとったのは、市場原理を導入して公教育を市場化する選択肢だった。競争原理を導入すれば、教育だってよくなるという考えだった。その流れの根底にある考え方が、新自由主義だ。
新自由主義についてミシェル・フーコーが「社会のあらゆる活動を経済的にのみ分析するまったく新しい世界観」と定義している。そうなると人間は経済的合理性が行動の基準になって、一人一人が起業家という新しいアイデンティティを身につけて生きていくことになる。では、新自由主義が教育にどんな影響を与えるのだろうか。教育は個人に対する「付加価値的な投資」とみなされ、お金を出せば市場で買える「商品」へと形を変える。子どもは「将来の労働力」と見なされる。学校と教員は、教育という商品を提供する「サービスプロバイダー」になって、子どもと親はそれを受けとる「カスタマー(消費者)」になる。教育委員会はといえば、「カスタマーサービス」へと性質を変えていくのだ。
アメリカで市場原理をとり入れた教育改革の一環として、公設民営学校、教員の能力給制度、ビジネスマンを校長に迎えるなどのイノベーション(改革)と呼ばれるものがおこなわれた。それが国策として前面に出たのが2002年の「落ちこぼれ防止法」だった。そもそも「落ちこぼれ防止法」は、1965年に貧困撲滅キャンペーンをやったジョンソン大統領のもとで出された「初等中等教育法」の改定法だ。
1965年のときは教育格差は「教育機会の格差」だといわれ、教育の平等保障のために「国家の投資責任」が問われた法律だった。ところが「落ちこぼれ防止法」では、同じ法律にもかかわらず、教育の平等保障の概念が180度変わり、教育格差は「学習到達度の格差」だとみなされた。いかに国家が貧困層に投資をするかではなく、いかに教育現場、学校や先生たちが工夫や努力をして、貧困層と富裕層の学習到達度の格差を解消するかという問題にされ、政府の投資責任から、「教育現場の結果責任」へとすり替えられた。
こうして始まったのが学力テストと結果責任を軸とした教育の徹底管理だ。州や市の学力調査で、成績の悪い学校が廃校に追い込まれた。テストの点を上げるだけだったら民間の方がいいではないかという発想になり、税金を公立学校ではなく、民間に渡して塾のような公設民営学校が出てきた【写真②】。これは人気の公設民営学校の抽選時の写真だ。公教育のなかで「あたり」と「はずれ」があって当然ということが正当化され、義務教育における公立学校の序列化が進んだ。テストの点数だけで学校や教員や生徒が評価されるため、朝7時には登校して、夕方6時まで勉強をするというスパルタ式の公設民営学校も出てきた。

【写真②】人気の公設民営学校の入学抽選会の風景
マニュアル化する授業 評価はAIに委ね
当時アメリカでは教育産業と政治の癒着が激しかった。教育産業にしてみればテストをすればするほどもうかる。そのため州のテスト、区や町のテスト、模擬テストやドリルなどどんどんテストが増えてきた。公立小・中学校のランキング本が書店で売られ、それを親が読んで学校を選ぶようになってきた。
そんななか、貧しく教育的ニーズが高い子どもたちが集中する地区で教えることが教員にとってリスクになっていった。点数が悪い学校は廃校にされたり、教員が解雇されたり、減給されるリスクがあるからだ。だから、選べる教員は郊外の富裕層の子どもが通う、テスト漬けとは無縁の全人教育をしている学校に移るようになった。そして都市部の貧困地区の子どもを教える教員が不足した結果、大学出たての教員免許も持っていない素人でも教えられるように、誰でも点数がある程度上げられるように授業のマニュアル化が進んでいった。また、テストの点数を上げるだけで良いのであれば、「カリスマ講師」の授業をまねればいい。こうやって「教え」というものがテクニックとなって売られるようになっていった。
誰でも子どもを扱えるように、生徒指導のマニュアル化も進んだ。例えるならば、ベルトコンベアで流れてきた野菜を、形や大きさが悪いという理由で、どんどん排除していくようなシステムだ。大事なのは、排除される子どもたちの中には点数のとれない子や特別支援を必要とする子たちも含まれていったことだ。究極的にいえば、生徒の点数をあげるだけでいいなら、もはや教員はいらずAIに任せておけばいいのだ。この【写真③】は、ロケットシップ・エデュケーションといって、当時アメリカで最も急成長していた公設民営学校チェーンだ。この学校ではこのシステムによって、1時間で最大130人の生徒を見ることができる。こうなったら教員免許を持った先生はいらない。教育という人間の営みをコンピューターに委ねてしまい、非正規の教員を監督官として1時間15㌦で雇うことによって、年間に約5000万円の経費を削減できるという。それが経営者の利益になるのだ。

【写真③】仕切りの中で勉強する子どもたち(LaborNotesのウェブサイトより、2013年12月)
後にカリフォルニア州立大学の名誉教授となったアーサー・コスタは、次のようにいっている。「教育的に大事で測るのが困難だったものは、教育的に大事ではないが測定しやすいものと置き換えられてしまった。だから今、われわれは学ぶ価値のないものをどれだけ上手に教えたかを測定しているのだ」。ここから見えてくるのは、計測可能なエビデンスに翻弄されたアメリカ教育界の姿だ。
米国の後追いする日本 GIGAスクール等
では日本の教育はどこに向かっているのか。一番大きかったのが、2007年の第一次安倍政権のもとで43年ぶりに復活した全国学力調査だ。もしその名の通り調査であるならば、サンプリングで十分なはずだが、あえて全員参加形式にした。なぜか。第二次安倍政権で、規制緩和がされて都道府県別の成績が開示されるだけでなく、教育委員会が許可すれば学校別の成績まで開示できることになった。すべての学校がテストを受けて、知ろうと思えば学校別の成績も知ることができる。そうなった時点で、市場原理の歯車が動き始めている。そうして「市場型」学校選択制への道が開けたのだ。教育の多様性というよりも、教育市場で保護者がカスタマーとなって子どもの学校を選択して、学校は生き残りをかけて生徒を奪い合うというシステムだ。もちろん税金を投じて民間企業に学校の運営を委託する公設民営学校という発想も出てくる。実際に大阪では1校の公設民営学校の運営が始まっている。
各学校でテストも確実に増加している。2018年には、都道府県の約7割が全国学力調査に加えて、都道府県独自の学力調査をやっている。そして政令指定都市の85%が市独自の調査をおこなっている。それに加えて中学校は毎学期ごとに定期考査がある。アプリをつかった補習などもおこなわれるようになってきた。東京都足立区では教員の初任者研修を大手の塾に委託している。テストの点数を上げればいいのであれば、カリスマ講師がいる塾にテクニックを学べばいい。AIの活用も始まっている。そうなれば教師が教える必要もなくなるわけだ。先生はコンピューターに不具合があったり、生徒が寝ていたら起こすだけでよくなってしまう。
コロナ禍でGIGAスクール構想なども動き出している。タブレットやICTは単なるツールにすぎず、よくも悪くもない。ただ、私は優先順位の問題だと思っている。教員不足が叫ばれているにもかかわらず、莫大なお金をコンピューターの方に費やしている。優先順位がおかしいのでは、と問うていく必要がある。
一方でコロナ禍で少人数学級制を求める運動が起こり、40人学級から35人学級にするという一定の成果があった。でもこの運動の意義は、学級の人数が5人減ったことではない。1人1台タブレットを持たせるというGIGAスクール構想が多額の予算をかけておこなわれているなかで、もし少人数学級を求める運動が起こっていなければ「全部リモートでいいじゃないか」「授業もオンラインで受けられるなら学校に行く必要がない」「先生をそんなに莫大な予算を使って雇う必要はない」という声が上がり、1人の監督官が130人を相手にするというアメリカのようになりかねなかった。
その意味でGIGAスクール構想に対するブレーキとして一番価値があったと思う。ただ、GIGAスクールは少人数学級制の57・3倍の予算を投じている。ここの優先順位の問題を議論しなければならないのではないだろうか。
学校はそもそも複合的な機能を持っている機関だ。託児所、食堂、学習塾、音楽教室、スポーツジム、修学旅行という旅行会社みたいな機能まである。そういう豊かな学校教育から、授業だけを摘出してオンラインでやることの愚かさを考えなくてはならない。
日本では2020年度から新学習指導要領が始まった。そのうえで見落とされている大事なポイントがある。学習指導要領は本来は、何を教えるか、何を学ぶかというカリキュラムの基準だったはずだが、何ができるかという学習到達度のパフォーマンスの基準へと形を変えようとしている。こうなったら早く安く効率的にいかに点数を上げるかという議論になりかねない。注意をはらうべきだと思う。
そのなかで日本の教育改革を象徴するような事件が起きた。大阪市の吉村市長(当時)が、大阪市が全国の政令指定都市のなかで学力調査の結果が2年連続最下位だったことに怒って、「翌年度からは全国学テの結果を校長のボーナス、教員の給料、学校への予算配分に反映していく」といい始めた。そして「子どもたちの学力向上の努力をし、結果を出す教員が高く評価されるのは当然だ」といった。この発言にどう答えるか。
元マサチューセッツ工科大学(MIT)の博士ノーム・チョムスキーは「民衆を受け身で従順にする賢い方法は、議論の範囲を厳しく制限し、そのなかで活気ある議論を奨励すること」といっている。今、全国学力調査の点数をどうにか上げようと各都道府県や学校や先生が活発な議論をしている。そんななか、何をもって「学力」というのかが問われていない。フタを開けてみれば、国語と数学の2教科(理科は3年に1回)の点数なのだ。たった2教科で子どもや学校や教員を評価していいのか。「学力とは何か」を問うことで見えてくるのは、極端に狭く偏った土俵で勝負を強いられているのは子どもたちだということだ。
見失われる人間的成長 標準化された「学力」
教育の数値化、標準化の象徴的なものとして、経済協力開発機構(OECD)によるPISA(国際学習到達度調査)がある。なぜフランスに本部があるOECDが、世界の公教育を遠隔で評価し、比較できるのか。
それに関して、なぜ西洋社会ではここまで数値に依存するようになったのか。その歴史を紐解いているのが、セオドア・ポーターという歴史学者だ。研究を通して、彼は数値化を「距離のテクノロジー」と称している。その象徴が、教育の世界でいえばPISA型学力テストだ。「学力」を数値化し、標準化することによって、学校に行かなくても、子どもや先生や授業を見なくても、地域の環境を見なくても評価できてしまう。
だが、学校では授業だけではなく休み時間や給食時間、部活の時間など、ずっと子どもを近くで見守っている教員だからこそわかるその子の長所や課題があるはずだ。それを抜きにして教育の評価を数値化し、その子に会ったこともない人に評価を委ねるというのは、教育者にとって自殺行為なのではないか。数値化の暴力性すら感じる。だがPISAが各国の教育政策に多大な影響を与えていることを私たちが当然のように受け入れている事実は、新自由主義が私たちの心の奥底まで浸透していることを物語っている。
『崩壊するアメリカの公教育』の八章で、西岡常一さんという法隆寺最後の宮大工棟梁の話を紹介している。『木のいのち 木のこころ』という本のなかで、昔の宮大工の棟梁は、1本1本の木の癖を見抜き、それらを組み合わせることで、木を上手に、長く生かす心構えを持っていたという。同じヒノキの山でも斜面によって生え方が違い、南側の斜面に行けば、太陽をさんさんと浴びて幹の太い立派な木がなっているが、そういう木は柔らかく柱には向かない。逆に過酷な環境で育った木の方が強く柱に向いているという。斜面を変えれば風向きが変わる。風向きが変われば、風に折られないように木はねじれる。「癖は何も悪いものではなく、強さであり生命力なのだ」と西岡さんはいう。しかし資本主義の発展にともない、そのような宮大工の知恵と技はすたれていった。より速く、より安くと効率性が求められるようになり、捻れた木をまっすぐに挽く製材の技術が発達し、規格通りの建築ばかりが増えていった。
設計書ありきで、それに合わせた使いやすい木を製材所からとり寄せて組み立てるのか、それとも棟梁がプロの距離感で、木の癖を見抜き、組み合わせることで、唯一無二の建物を創造するのか。ここにこそ、今日本の教育界が求められている「生かす」というパラダイムシフトがあるような気がする。
どんな社会を作るのか 教育の商品化に抗し
教職員に講演するとき「目の前の子どもだけ見ていても、その子のことは救えない」といっている。私たちは選挙に関心を持つ必要があるし、社会のいろんな問題に目をむけて点と点を線でつないでいく必要があるのではないかと思う。本の九章でシカゴの教職員組合のストについて書いた。先生たちが教育だけでなくて貧困や人種問題、政治などの問題に声を上げて、点と点を線でつないでいった。それに保護者や市民が理解を示し、協力した。アメリカの保護者のなかで広がった新自由主義教育改革への反対運動が「オプトアウト」だった。
保護者たちが「私たちがデータを提供しているから、このシステムが成り立っている」といい、子どもたちにテストを受けさせないという運動だった。私たちは「学力向上」という否定のしようのない、でも空っぽなスローガンに踊らされている。そしてそれを支えているのもわれわれ自身だという視点が大事だ。
私たちは何を子どもたちに教えたいのか、どんな学校であってほしいのかをまず議論しなければならない。しかし、それもせずに「学力向上」に邁進することで私たち自身が新自由主義的なシステムの歯車になってしまっている。インドのガンジーが「いかなる搾取も搾取される側の協力によって成り立っている」といった。これはとても大事な視点だと思う。新自由主義を支えているのは私たち自身だという認識を持たなければパラダイムシフトは起きないと確信している。
この度、新書大賞をとった斎藤幸平さんの『新人世の「資本論」』でも、SDGsを新自由主義のパラダイムのなかでやっても意味がなくまやかしに過ぎない、ということをいっている。今のパラダイムを抜け出さずに「教育改革」を追い求めても新自由主義に絡めとられるだけだ。必要なのは子どもの教育を通して社会のあり方そのものを問い直し、パラダイムシフトを起こすことだと思っている。






















戦後のほとんどの期間を自民党に支配されてきた学校教育が異常なのは当然。あまりに異常で、これは家畜化教育だと断言できる。