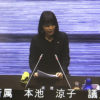下関市立大学で13日、「シンポジウム 大学改革の潮流と下関市立大学の将来」が催され、郷原綜合コンプライアンス法律事務所・郷原信郎氏、明治学院大学社会学部・石原俊教授が講演をおこなった。同大では、前田晋太郎市長の指示により、新たな専攻科の設置と特定の教員採用が決定されたことが問題になるなかで、これらを可能にする定款変更が下関市議会で可決された【関連記事】。国公私立を問わず「大学ガバナンス(統治)改革」によって学問の自由や大学の自治を圧殺する方向が強まるなか、両氏は歴史的・社会的な視点から、この問題点とともに大学のあり方を考えることを提起した。二氏の講演内容を紹介する。

大学ガバナンスにおけるピア・レビューと自治
明治学院大学 石原俊
 大学のガバナンス・意思決定、あるいは統治は非常に特殊な構造を持っている。それは「学問の自由」「大学の自治」という二つのキーワードでとらえられる。これが日本の大学でどう展開し、現在どうなっているのか、下関市立大学の最高規則・定款の変更が、大学ガバナンスの歴史のなかで、どのような位置にあり、どんな問題をはらんでいるのか考えたい。
大学のガバナンス・意思決定、あるいは統治は非常に特殊な構造を持っている。それは「学問の自由」「大学の自治」という二つのキーワードでとらえられる。これが日本の大学でどう展開し、現在どうなっているのか、下関市立大学の最高規則・定款の変更が、大学ガバナンスの歴史のなかで、どのような位置にあり、どんな問題をはらんでいるのか考えたい。
営利企業であれ官庁であれ、一般的な組織のガバナンスは、基本的にトップダウン、あるいは業務命令型になっている。これは社会学者マックス・ウェーバーが「官僚制」という言葉で呼んだ秩序だ。規則や法律を守りつつも、その範囲において業務命令やトップダウンの指示がおこなわれる。
それに対して近代の大学は特殊なガバナンスを持っている。これは「教育」と「研究」にかかわる部分においてだ。その部分にかんしては官僚制的な秩序が留保され、専門家集団(おもに教員からなる教授会からなる会議体)による合議(ピア・レビュー)、相互評価によってものごとを決めていくという一種の大学の自治がつくられてきて、尊重されてきた。西ヨーロッパやアメリカで少しずつ違う歴史を持っているが、非研究者からなる経営意思決定機関(理事会や執行部)や、あくまで一領域の専門家である学長が一方的に意思決定をすることを排し、さまざまな専門・専攻分野から成り立っている多様性を担保するために、教育研究に関しては自由を確保しなければならないということだ。これが近代の大学においてつくられてきた「大学の自治」「学問の自由」だ。
これは近代の日本でも、明治憲法下で一定の制約はありつつも徐徐に発展してきた。まず最初に、教育研究内容、カリキュラム編成権の自治が帝国大学などで獲得されるようになり、徐徐に教員人事における審議権も獲得し、専門家同士が審査して採用や昇進を決め、基本的に大学の管理者は受け入れるといった原則が発展してきた。
ところがこれはファシズム期に挫折を見た。明治憲法下では官立高等教育機関の教員(教官)の人事権は、最終的に天皇大権に帰属していたため、それに付け入って、政官軍から大学の教員人事・教育研究内容に介入し、場合によっては教育研究のあり方を弾圧したり、教員を一部追放したり学生を弾圧することが起こった。それにみずから加担する教職員も出た。結果として、これが大学における学問の自由だけでなく、日本社会全体の言論や思想の自由の圧殺にまで影響を与えた。
戦後期日本の「学問の自由」「大学の自治」
この反省の下、戦後の日本国憲法では大学の自治・自由が大きく制度的に保障された。憲法で「学問の自由」が独立した条文で定められ、この憲法二三条を根拠としてさまざまな法体系が整備されてきた。このもとで、国立大学や公立大学で、教員人事や学部長の選出などに関しては、学長が教授会による選考・選挙結果を基本的に追認する。学長の選出に関しては文部大臣が教職員による選挙結果を承認するといった体制が主流となってきた。公立大学や中~大規模の私立大学においても、学長や理事会、設置者(自治体)の長が、教授会や教職員による選考・選挙結果を承認する体制が主流となった。
戦後、韓国や台湾、東南アジア諸国では独裁政権が長く続き、学問の自由・大学の自治はなかった。東側諸国では共産党独裁政権の下で大きく制約されており、日本の大学の自由は、ある意味特権だったが、それが徐徐に世界に広がっていったといえる。日本国内でも当初は「学問の自由」はある種の教養市民層の特権だったが、進学率が上がることで多くの学生に広く共有されるようになってきた歴史がある。下関市立大学もこうしたなかで設立され、発展してきた。
摩耗する「学問の自由」「大学の自治」
大きく転換点を迎えたのは2004年に始まった国公立大学の法人化である。法人化によって国公立大学の教員は、教授会の意思決定や学長選出などにかんする自治を認めてきた「教育公務員特例法」という法体系が適用されなくなった。法人化によって組織の自由度が増した面も否定はできないが、「自治」を定めた法体系が徐徐に掘り崩されていった。
たとえば、国公立大学において、学長選出の方法が徐徐に、教員による投票から学長選考会議による指名へと移行している。さらに多くの大学で学長選出のさいの意向投票が撤廃されている。学部長選出の方法も、これまでは教員による投票を学長が承認していたが、徐徐に「学長による直接指名」に移行している。教員人事も学長が指名する人事委員会などが審査する形に移行している。
この流れが絶対悪だといいたいわけではない。ただし問題は、これらのプロセスが「学問の自由」「大学の自治」という歴史的・社会的意義、とりわけ学長・学部長などの選出や教員人事におけるピア・レビューの重要性について議論・論点が深められないまま、「トップダウンがいい」と、なし崩し的に事態が進行していることだ。
2014年6月に成立した「学校教育法および国立大学法人法の一部を改正する法律」も大きな変化だ。ここで「教授会が重要な審議をおこなう」としていたものを、「教授会は意見を述べる」機関に変えた。文科省はこれに先だって各大学の担当者を霞が関・虎ノ門に呼び出して、「教授会の審議結果が学長の決定を拘束すると解釈可能な内部規則は“違法”であるから、すべて定款や学則から削除するように」と圧力をかけた。背景には下村博文文科相や経済団体をはじめ、政財界からの圧力があったといわれている。この勢力は大学の事業の固有性や組織の特性を毀損してでも大学ガバナンス改革の推進、トップダウン化を進めたいという意思がある。文科省がそれらの圧力に負けて各大学に押しつけようとした。
この悪影響が国公私立大学ともに及んでおり、こうした法改定の解釈を悪用する経営陣(学長・理事長・理事会)や設置者(自治体の首長や議会与党など)が次次とあらわれた。とにかく教育研究領域のピア・レビューや組織上のガバナンスの自治原則を無視してもいい、毀損してもいいと考え、悪用する人たちが続出するようになったのが現状である。
中教審の大学ガバナンス改革推進の内容
ただし、これは近代の大学の原則の曲解であるといえる。
この法改定がおこなわれる直前に、文科省で一番重要な審議会である中教審が2014年2月に「大学のガバナンス改革の推進について」という審議結果を出した。中教審には教育研究関係者も入っているが、財界、政界の出身者、官僚も入っており、ある意味公平に意見を聴取しながら決めている文章だ。ここでは「大学のガバナンスにおいて、これまで教授会などの意思決定が強く、しかし責任をとるのは学長であり、権限と責任が一致しないので、これは問題だ」と指摘し、21世紀の大学ガバナンス改革のスローガンに「意思決定(権限)と責任の一定程度の一致」を掲げている。これは必要なことではないかと思う。
一方で、「教授会等の構成員自治に基づく自律的運営を基礎とし、また、学問の多様性・継続性を維持すべき社会的な使命を負うなど、営利を追求するコーポレート・ガバナンスとは本質的に異なる点も多いことに留意する必要がある」とし、「教授会のような合議制の組織は、大学固有の組織」であり、教員専門家集団による人事やピア・レビューは必要であると指摘している。
あくまで経営においては学長や理事長が責任を負うため、経営の側面では教員などの意見を聞きつつ、理事会等が最終的な意思決定をする必要がある、教育研究と経営を分離せよといっているわけで、これは世界的な流れでもある。
教授会については、学校教育法九三条改正によって、「学長に意見を述べる」存在になったが、中教審は①学位授与、②学生の身分に関する審査、③教育課程の編成、④教員の教育研究業績等の審査等について、「教授会の審議を十分に考慮した上で、学長が最終決定を行う必要がある」としており、これらの「重要な事項」について、教授会や教育研究評議会(下関市立大学の場合は教育研究審議会)の意見の尊重が必要な点は当然変わらないとしている。
また、学部・学科の廃止、キャンパスの移転などについては、学生の教育環境や研究の多様性・継続性に大きく影響するので、単なる経営事項ではないとし、「学部・学科・専門(専攻)、分野の新設・改廃などを、理事会の経営的観点のみや設置者の意向のみから決定してはならない」としている。
公立大学についてはとくに指摘があり、「公立大学は当該地域のニーズに応じて設立されたという経緯があるため、学部・研究科のみならず、大学そのものも自治体のイニシアティブの下で見直しが図られる場合も少なくない。しかしながら、地域の学生を教育し、地域に役立つ研究を機動的に行う組織である公立大学が、安定的に教育研究活動を行うことが重要である」としている。これは、公立大学における学部・学科・専門(専攻)分野の新設・改廃などを、地方自治体の政治的観点や(その意向を受けた)理事会等の経営的観点のみから決定してはならないという注釈がついている。
下関市立大学定款改定が意味すること
下関市立大学の定款改定(2019年)は、これまで設置していなかった理事会を新たに設置するという定款改定だ。理事会が教育研究に関する重要な決定をおこなうとし、その内容には教育内容、研究内容、カリキュラム等に関する最終的な決定が含まれている。学部の改廃、コース・専攻分野の改廃等の決定を理事会がおこなう。そして教員の人事、新たに採用する教員の審査、決定、教員の昇進や懲戒など、すべて最終決定を理事会がおこなうという定款改定が市議会で可決されたのである。
これまで、たとえば教員の人事は、人事委員会が審査し、専門家である教員の代表数名が新たに公募をおこない、応募してきた候補者の履歴書や業績を審査し、審議し、教授会に持ち込んで審査・審議し、そこで決定した候補者について教育研究審議会で審議して候補者を決定し、最終的に学長・理事長が決定し、採用が決まるという、非常に専門家によるピア・レビューによる審議がおこなわれている。しかし、場合によってはこのプロセスを省くことができると解釈できる定款改定がおこなわれてしまった。
「学問の自由」「大学の自治」の歴史や原則を踏まえたうえで、この定款改定が意味することを考えるとき、以下のようなことがいえる。
①少なくとも戦後75年、紆余曲折や漸次改革をへつつも蓄積・継承されてきた大学ガバナンスの原則や慣行に照らして、「異例中の異例」といえる。これはピア・レビューをへることなく経営陣が決定できなかった教員人事、業績審査、教育研究内容、カリキュラムなど、大学の自治の「最後の砦」というべき部分が、非研究者・非専門家を含む大学経営陣によって、一方的に決定・改廃しうるような定款「解釈」を導きかねないからである。
②教員集団による大学の自治は、教学のみならず経営事項の一部に及ぶといった見解は現在も一部に根強いが、そういった見解は横に置き、教育と経営の分離を認めるとしても、今回のように理事会、あるいは首長の指名した理事長が、教育研究審議会や教授会の審議・審査をへずに教員の採用・昇任・懲戒を決定できると「解釈」しうる定款改定は、教育研究と経営の分離をこえて、(一部ワンマン経営の小規模私大にみられるごとく)「経営による教学の支配」を目指すものになってはいないか。
今回の定款改定にともなって生じうる事態は、下関市立大学はもとより、日本の公立大学全体さらには日本の大学全体にとって、決定的なガバナンス改変の先鞭となる可能性がある。
ただし、これは大学の自治や学問の自由という原則を担保するためのガバナンスの歴史を踏まえたときに、以上のような定款の「解釈」はあり得ないだろうということだ。
--------------------------------
「社会的要請に応える」コンプライアンスの視点から公立大学のガバナンスを考える
郷原総合コンプライアンス法律事務所 郷原信郎
コンプライアンスとは何か
 私は、「コンプライアンス」を「法令遵守」ととらえることは誤っているといってきた。たんなる誤りではなく、これが、世の中にさまざまな弊害を与える。
私は、「コンプライアンス」を「法令遵守」ととらえることは誤っているといってきた。たんなる誤りではなく、これが、世の中にさまざまな弊害を与える。
端的な例でいうと関西電力の不祥事だ。高浜原発の地元有力者から関西電力の幹部が多額の金品をもらっていたことが明らかになり、大変な批判を受けた。しかし会長・社長は当初、これだけ重大な問題が起きているにもかかわらず辞任しなかった。「不適切だが、違法ではない」というのが言い訳だ。これはまったく通らず、世の中からさらに大きな批判を受けた。まさにこうした言い方に「法令遵守」が凝縮されている。
コンプライアンスを法令遵守ととらえることには大きく二つの弊害があると考えている。
一つは「法令」の問題だ。法令にばかり視点を向け過ぎると大切なものを見失う。法令によって物事の解決をはかるのが司法的手段だが、司法的手段ばかりにこだわっていても、あらゆる問題を適切に解決できるものではない。法令や司法をどのように使っていくのかについては世の中、国、社会によってさまざまな考え方がある。日本社会はとりわけ、「法令」にこだわり過ぎることが、さまざまな弊害をもたらしている。
もう一つは「遵守」という言葉だ。遵守は「いいから守れ」「つべこべいわずに守れ」という意味だ。これが出てくると「なぜ守らなければならないのか」と質問する動きが封じられる。なぜかを考えること、それを巡って議論することもやめてしまう。それが「遵守」という言葉がもたらす思考停止作用だ。世の中にある規範やルール、倫理などについても「とにかく守ればいい」という考えが大きな弊害をもたらす。ルールには守ることによって実現していこうとするものがあるはずだ。それが何かをまず考え、ルールを活用していく方向に転換していかなければならない。われわれは「遵守」という姿勢を脱却していかなければならない。
では、コンプライアンスとは何か。私は「組織が社会の要請に応えることだ」といってきた。企業であれ官公庁であれ大学であれ、個人と違い、組織は生まれながらにして活動し、存在する権利を与えられているわけではない。組織は社会が認めてくれるからこそ、存在し活動することができるのであり、社会の要請に応えることは当たり前のことだ。
しかし、組織には多くのさまざまな個性・考え方を持った人がおり、全体がまとまってさまざまな社会の要請に応えていくのは容易ではない。しかも「社会の要請」を的確に把握することは容易ではない。世の中はどんどん複雑多様になるし、どんどん変化している。だから組織は常日頃から、あらゆる社会の要請に応えられるよう努力し、とりくみをしていかなければならない。それがコンプライアンスだ。
大学に対する社会的要請
これを大学に置き換えたとき、どう考えればよいのか。
大学の社会的機能には①知的創造、②経済的価値の創造(この機能に特化した同じような組織が民間の研究機関)、③学生の人間形成への貢献、④学生の経済的付加価値を高めていく(この機能に特化したのが専門学校)といったものがある。
大学に対する社会的要請の一つに「教育」がある。需要者である学生のニーズに応えることだ。需要に応えることによって自由競争原理で解決していくのが経済社会の一つのベースになっているが、大学の場合、「需要に応える」ことですべてがうまくいくわけではない。学生の需要に応えることは重要な要件だが、すべてではない。
二つ目に、社会的貢献があり、その一つに研究成果で社会に貢献することがある。ただ、研究の成果が社会にどのようなメリットをもたらしているのか、評価が難しく多様だ。研究成果には「経済的価値をもたらす」面と、「文化的貢献」がある。とりわけ文化的貢献は最終的に評価されるのに長い時間がかかり、画一的な評価は難しい。また、教育を通して社会に貢献することも大学の社会的貢献の一つだが、大学だけで教育の成果が生み出されるものではない。それだけに教育と社会的貢献の因果関係が明確ではなく、評価も複雑だ。
これら社会からの要請にどれだけ応え、どれだけコストがかかっているかという点が、経済性の問題になるが、研究・教育の「成果」の評価が容易ではないことから、「経済性」の評価も単純ではない。
大学のガバナンスとは
これら大学の特徴を踏まえ、「社会からの要請に応える」ことを前提に、大学のガバナンスを基本的な視点から考えたい。
大学の場合、経営面では理事会・執行部、研究・教育内容については教授会と、二つの面から意思決定がおこなわれる。問題は、経営上の意思決定と研究・教育との関係だ。研究の社会的価値、教育成果は客観化が困難である。一方、評価を十分にしなければ研究・教育評価が聖域化し、いわゆる「ぬるま湯」になる。そこで両方の調整が非常に困難な問題になってくる。研究・教育が独立した世界になり、外から口が出せなくなるのは問題だ。しかし、経営上の意思決定という視点からだけ研究・教育をとらえるわけにはいかない。重要になってくるのは、研究・教育に関しても内部の研究者側がしっかり説明責任を果たしていくこと、経営上の意思決定に研究・教育の価値評価をどう反映させていくかである。
大学組織における学生の位置づけは非常に難しい問題である。教育という面では需要者=取引の相手方だが、大学は社会にいろんな価値をもたらしていくべき存在だ。そのうえでは学生は大学と共同関係でもある。学生の位置づけも複雑で微妙だ。
大学組織の法的な規定
法人としての大学組織が法律的にどのように規定されているか見てみたい。
私立大学は「私立学校法」の定めるところによって設立される財団法人だ。寄附行為がおこなわれることによって始まり、理事長・学校長も含め五人以上の理事、二人以上の監事が置かれる。そこを中心にした意思決定がされるが、「法人運営に広く学校法人の教職員や卒業生等の意見を取り入れるため理事の二倍を超える数の評議員で組織する評議員会が必置機関」となっている。寄附行為をおこなったオーナーの考えに従っていけばいいという単純なものではない。運営についてはさまざまな議論がされ、さまざまな価値について評価がおこなわれるなかで意思決定されることが必要とされている。
公立大学は、現在「公立大学法人」となった。地方独立行政法人法によって設立される地方独立行政法人の一つだが、法律上の制約があり、「設立団体は、大学の教育研究の特性に常に配慮しなければならない(六九条)」となっている。これが他の地方独立行政法人と異なる点だ。そして運営組織が法令で規定されており、経営審議機関、教育研究審議機関が設置される。設置団体の決定通りに、経営上・教育上の意思決定がおこなえるわけではない。
一方で公立大学は、設立団体の長が中期目標を策定する。これについては法人の意見に配慮することになっている。設置団体のガバナンスを中心にしつつ、大学側の意見に配慮するという制約を設けている。
公立大学のガバナンスでは、具体的な組織運営などは、地方公共団体の裁量に委ねる弾力的な制度設計であるものの、「教育研究の特性に配慮する」という部分で大きな制約をかけている。ただ、議会の議決を経て定款を変更することは法律上可能だ。このように設置者である地方自治体の意思がある程度、反映される方向での制度改革がおこなわれているのは確かだ。
文科省は改革の方向性として「自主自立的な環境の下、魅力ある教育研究を積極的に展開(予算、人事等の規制緩和)」「“民間的発想”によるマネジメントを取り入れ、効率的におこなっていく」「能力、成績に応じた弾力的な人事システムの導入」などを示している。
問題は、こうした改革の方向性と、大学という組織のコンプライアンス(社会の要請に応えていくこと)、そしてガバナンスの複雑性という関係だ。単純にとらえることができるのかという点に大きな問題がある。大学が果たして行く複雑な価値を、大学の歴史と伝統を守りながら、改革の方向性と調和させていくためにはさまざまなことを考えていかなければならないのではないか。
公立大学におけるガバナンス暴走の危険
公立大学の場合、基本的な方向性として「設置団体中心のガバナンス」になっている。しかし、私人が寄附行為によって設立する私立大学ですら、運営については大学の特色に配慮した制約がある。公的な役割を担うべき公立大学では、当然それ以上に十分な配慮がおこなわれなければならない。設置団体中心のガバナンスだけで、十分に機能するのかということだ。それぞれの大学には、長年の歴史のなかで大学をどのように運営していくことがもっとも社会の要請に応えることができるかということについて、知の蓄積がおこなわれている。そうした大学としての社会的要請への応え方と、大学の運営が設置団体中心のガバナンスになることとの関係は、今後も議論を重ねながら調和をはかっていかなければならないのではないか。
日本の地方自治体の首長は大統領に近く、法律上は首長に権限が集中している。ということは、公立大学のガバナンスを自治体中心にしようとすると、首長中心のガバナンスになる。これが果たして公立大学として社会の要請に応えることと一致するのかということだ。「民主主義」は、多くの人の意見を国や地方自治体の意思決定にできるだけ反映させるうえで極めて重要な考え方だ。しかし、大学の運営や教育研究のあり方と民主主義との関係は非常に微妙だ。大学が社会の要請に応える構造は複雑だが、自治体のガバナンスは極めて単純で、両者のあいだには大きな問題があるのではないか。
自治体側が「こういう機能を果たしてもらいたい」「こうした社会の要請に応えてほしい」と首長中心のガバナンスとして考えた場合、これが将来にわたって多くの社会的要請に応えることに添うものになるかどうかという点にも極めて困難な問題がある。地方自治体にはさまざまな意見をとり入れながら慎重に意思決定する自治体もあれば、強いリーダーシップを持った特定の人が一気に物事をおし進める自治体もある。大学が長期的に社会の要請に応えていくことを考えたとき、少なくとも特定の人に権力が集中しているような自治体のガバナンスが公立大学のガバナンスに大きく力を持つようになることは、長期的に見たときマイナスになることが考えられる。これらの問題を考えつつ、公立大学のガバナンスというやっかいで困難な問題を考え続けていかなければならないのではないか。