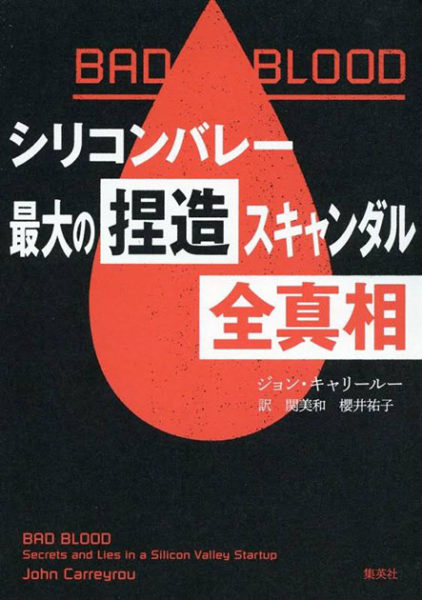 本書は、「シリコンバレー史上最大の詐欺事件」といわれる、血液検査ベンチャー企業「セラノス」の不正事件を追ったものだ。この10年あまり、米国のメディアが「第二のスティーヴ・ジョブズ」と持ち上げた、女性初のユニコーン企業(企業価値が10億㌦をこえる未上場企業)の創業者エリザベス・ホームズ。彼女は、「指先からとるわずか数滴の血液で200種類以上の検査ができ、あらゆる病気を調べることができる画期的技術を開発した」「検査は通常の半額以下ででき、数時間で結果が届く」と主張して時代の寵児となり、2014年にセラノスは企業評価額90億㌦以上(約1兆円)という途方もない評価を受けた。
本書は、「シリコンバレー史上最大の詐欺事件」といわれる、血液検査ベンチャー企業「セラノス」の不正事件を追ったものだ。この10年あまり、米国のメディアが「第二のスティーヴ・ジョブズ」と持ち上げた、女性初のユニコーン企業(企業価値が10億㌦をこえる未上場企業)の創業者エリザベス・ホームズ。彼女は、「指先からとるわずか数滴の血液で200種類以上の検査ができ、あらゆる病気を調べることができる画期的技術を開発した」「検査は通常の半額以下ででき、数時間で結果が届く」と主張して時代の寵児となり、2014年にセラノスは企業評価額90億㌦以上(約1兆円)という途方もない評価を受けた。
だが、著者であるジャーナリストが2015年10月に書いた新聞記事を契機に、それがねつ造と虚言にまみれたものだったことが暴露された。SEC(米証券取引委員会)は2018年3月、エリザベスと共同経営者サリーを「長年にわたる計画的な詐欺」の罪で提訴。エリザベスは50万㌦の罰金を払い、実験室はすべて閉鎖となり、現在彼女は刑事裁判の被告の席にいる。本書はその一部始終を明らかにしている。

エリザベス・ホームズ
エリザベス・ホームズは、起業家と医学者の遺伝子を持つ裕福な家庭で育ち、「博士号なんて興味ない。お金もうけがしたいの」といってスタンフォード大学を2年で中退。2003年に19歳で血液検査機器の会社「セラノス」を創業する。
エリザベスが開発したという血液検査機器「エジソン」のしくみは、簡単にいうとこうだ。まず自分の指先を針で刺して数滴の血液を絞り出し、それをクレジットカードを厚くしたような白いプラスチック製カートリッジに移す。それを、リーダー(読み取り器)と呼ばれるトースターサイズの細長い箱に挿入する。すると読み取り器は、カートリッジから抽出したデータ信号を無線でサーバーに転送し、データが解析されて結果が送り返されてくる。
だが、このエジソンは頻繁に誤作動を起こす。正しい結果が得られるかどうかは誰にもわからないし、そもそもエジソンの検査の有効性を示す厳密な科学的検証はなにもされていなかった。だから、投資家や製薬会社、政府機関の前で実演するとき、セラノスのスタッフはうまくいったときの結果を前もって録画しておいて、それを毎回実演の最後に見せていた。ペテンである。だから他の研究機関で同じ検査をすると、しばしば違う結果になった(後からわかったことだが)。
また、セラノスが提供する250種類の検査のうち、エジソンを使ってできる検査はわずか12種類で、それ以外の検査はすべて自社開発ではなくシーメンスなどの市販検査器を使っておこなっていた。だから、本社で実演するときは、訪問客の検体をエジソンに入れるふりをして、訪問客が見ていないすきに検体をとり出して検査技師に渡し、市販検査器で検査をおこなっていたという。まさに売るためには手段を選ばず、である。
そもそもエジソンは、セラノス社自身の品質管理試験に、3回に1回は落ちていた。検査室の運営もめちゃくちゃで、無資格者が患者の検体を扱い、血液の保存温度も守られなかった。
問題は、この検査が人々の健康と命に直接かかわっていることだ。たとえばある医師は、この検査結果をもとに脳梗塞のリスクのある患者に処方する抗凝血剤の投与量を調節するが、多すぎると出血しやすくなり、少なすぎると血栓ができて命とりになる。そしてエリザベスが余命わずかながん患者にこの不完全な医療機器を使おうとするに及んで、社内で「患者を実験台にするな」との無言の抗議が広がった。これが著者の取材に対する内部告発につながっていく。エリザベスが不都合な事実を闇に葬るために社員を監視し、逆らう者は首にし、社外に放逐した後も「余計なことをしゃべると名誉毀損で訴える」といって弁護士を差し向けて脅迫するが、それに元社員が屈しなかったのも、「患者の命を守りたい」という使命感からだった。それが本書を読むと伝わってくる。
それにしても大学中退の何の技術も持たない若者が、どうして米国の名だたる投資家から巨額の資金を調達できたのか?元国務長官ジョージ・シュルツやヘンリー・キッシンジャーがセラノスの取締役に名を連ね、オバマやヒラリー・クリントンとべたべたの仲になり、当時の副大統領バイデンが「ここは未来の検査室だ」と持ち上げるなど、政界の大物を次々と巻き込むことができたのはなぜか?
その鍵は、次のことにあるようだ。
超低金利のもと、金あまりの市場のなかで、世界の投資家はより高いリターンが得られる投資先を血眼になって探している。それがシリコンバレーに流れ、グーグルやアップル、フェイスブックなどに続く次のスタートアップ(急成長するベンチャービジネス)を求める。これに対して起業家は、「どこまで事業の規模を拡大できるか」と大風呂敷を広げて自己を売り込むことが常態化している。ベンチャーの世界での成功の条件は、企業価値を高めることに尽きるからだ。
とくにテクノロジーとヘルスケアを掛けあわせたヘルステック市場は、今後もっとも拡大が望める領域として世界中の投資家の資金が大量に流れ込んでいるという。ルパート・マードックがセラノスの最大の投資家になったのも、シリコンバレーのスタートアップ投資がいかにもうかるかを経験していたからだ。
また、セラノスの高い企業価値の源泉になったのが、いくつもの巨大製薬会社と契約を結んでいたことだと著者はのべている。世界の製薬会社は毎年何百億㌦もの大金を投じて新薬の有効性と安全性を確かめるための臨床試験をおこなっているが、エジソンを採用すれば製薬会社の研究費を最大で30%削減できる、とエリザベスは触れ回っていた。
つまり、米国の金融資本主義そのものがバクチ経済化しており、患者の命を救うため、人々の健康と生命を守るためという本来の目的が後景に退き、金が金を生むマネーゲームをいかに勝ち抜くかが主な目的になっていることが、今回の大スキャンダルによって浮き彫りになった。そのもとで、最初にエリザベスを「第二のビル・ゲイツ、スティーヴ・ジョブズだ」と持ち上げたのがスタンフォード大の花形教授、チャニング・ロバートソン(セラノス取締役会顧問)であり、次にはそうそうたる投資家や政治家が彼女の庇護者となり、さらにメディアがその太鼓持ちをやった挙げ句、史上最大の詐欺事件をみなで支えてしまうという結末になった。まさに資本主義の終末期的な状況である。
(集英社発行、B6判・415ページ、定価1900円+税)





















