今、先端技術を使った工業製品を生産して莫大な利益を得ようとし、それに必要な鉱物資源を手に入れるために、アジア、アフリカ、ラテンアメリカで森林を伐採し、先住民の住処を奪い、鉱山の有毒物質を垂れ流して耕作地や河川・海を汚染していることが問題になっている。そして、風力や太陽光などの再生可能エネルギーや電気自動車に転換するためには、こうした自然破壊的な鉱山開発がさらに大規模に進むことが予想されることから、この問題に注意を喚起する発言があいついでいる。

映画『アバター』の一場面
アメリカのジェームズ・キャメロンが監督を務め、脚本も書いた映画『アバター』は、この現実に起こっている問題をフィクションとして描き、風刺したものだ。日本でも2010年に劇場公開されたが、日本のメディアは3D映像の珍しさを話題にしただけだった。
この映画は、莫大な資金力を持った資源メジャーと鉱山会社、また中国など新興国の鉱山会社が、途上国において、豊かな自然と共生している先住民を強制的に移住させ、自然を破壊して鉱物資源開発をおこなっていることを批判的に描いたものだ。アメリカでも大きな反響があったが、一部保守層から「米海兵隊を侮辱する反米映画」という非難の声が上がり、米陸軍曹長による訴訟に発展した。また、同じ年にはインドの先住民族がみずからをナヴィに重ね、『アバター』と同じことがインドのボーキサイト鉱山で起こっていると国際世論に訴えて、インド政府が英系資源メジャー・ペダンタ社の開発を差し止める事件も起こっている。
映画のストーリーは次のようなものだ。舞台は22世紀、アメリカの投資会社はパンドラという星に、1㌔が2000万㌦(約20億円)もするレアメタル「アンオブタニウム」の鉱床があることを発見し、それを手に入れるためのミッションを開始する。鉱床は、熱帯雨林に似たジャングルの中の先住民族ナヴィが暮らしている村の地下にあり、鉱石の採掘のためには彼らを移住させなければならない。
そこで現地に学校をつくり、英語を教え、米国式教育をほどこして先住民族を懐柔しようとするが、彼らは先祖代々受け継いできた文化や生活様式が奪われることを拒否している。そこで元米海兵隊員のジェイクらを送り込み、ナヴィを手なずけ、だまして移住させようとする。送り込むといっても、ナヴィと人間の遺伝子を組み合わせ、ナヴィと同じ肉体を持ち、その意志はジェイクの脳の働きで遠隔操作する「アバター」としてそうするわけだ。
ところがアバター(ジェイク)は、ナヴィの村で暮らすなかで、先住民族の言葉を学び、動植物や昆虫とつきあう知恵を学び、動物を獲って食べるときに生き物に感謝する気持ちや、「森から得たエネルギーは借り物だから、いずれ返さなければならない」という考え方を学ぶ。こうしたことをなにも知らないスカイ・ピープル(地球人)は、頭がカラッポだということも…。ジェイクの世界は逆転し、ナヴィの村の方が本当の世界ではないかと思い始める。
そのとき、業を煮やした開発会社が巨大ブルドーザーで森林伐採を始めた。先住民族が抵抗すると、次には元海兵隊大佐が指揮する傭兵部隊がガス弾やミサイルをぶち込んで掃討作戦を始める。そのときジェイクは、先住民族と一緒にたたかう道を選んだ。
途上国の鉱山の採掘現場は、先進国の人々の目に触れないように隠されている。見られたくないことをやっているわけだ。それを白日の下にさらしたことで、この映画は大きな反響を呼ぶことになった。
世界の鉱山開発現場をルポ
それは映画ではなく現実に起こっていることだということが、資源ジャーナリストの谷口正次氏が表した『教養としての資源問題 今、日本人が直視すべき現実』(東洋経済新報社)を読むとわかる。
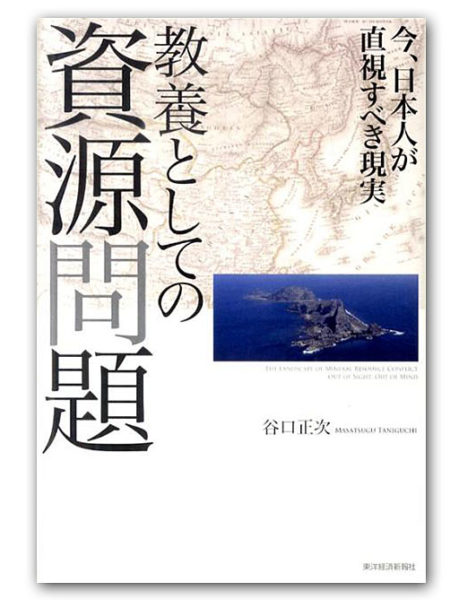
この本では世界各地の鉱山開発の現場をルポしている。一つの例として、南西太平洋にあるパプア・ニューギニアという国のブーゲンヴィル島の銅鉱山開発について見てみたい。
この島では1970年代後半、当時世界最大であった銅鉱山が開発された。その権益の8割を握っていたのが、英・豪資本のリオ・ティント・グループという資源メジャーで、ここで原鉱石を採掘・選鉱して海外の精錬所に輸出していた。この鉱山はピーク時には年間5億㌦の銅・金・銀収入を上げていたが、その利益の8割は外資が持っていき、残りの2割をパプア・ニューギニア政府が手にしたため、ブーゲンヴィル島の人たちには何の恩恵もなかった。
それどころか毎日13万㌧ものテーリングと呼ばれる廃棄物が生まれたが、それはそのまま川に投棄された。有害化学物質によって熱帯雨林の樹木は立ち枯れし、大量の魚が死に、飲み水まで汚染された。
この島の先住民たちは鉱山の操業に抗議して立ち上がり、1980年代後半には反対運動は頂点に達した。何度も鉱山会社に補償を求めたが埒があかないため、ついに1988年にブーゲンヴィル革命軍を結成して鉱山を占拠し、パプア・ニューギニアからの独立を宣言した。
ところが、鉱山から得られるロイヤリティに大きく依存していたパプア・ニューギニア政府は、話し合いによる解決方法をとらず軍事行動に出た。国軍に制圧を命じたのだ。しかし国軍は海岸には上陸したが、鉱山には攻め入ることができなかった。そこで1996年、政府は、世界銀行から開発目的で調達した資金のうち3600万㌦を使ってイギリスの民間戦争請負会社サンドライン・インターナショナル社と契約を結び、軍事侵攻を依頼した。だが、戦争請負会社が四機の攻撃用ヘリや57㍉ロケット砲などの調達を始めると、その情報が国中に広がり、クーデターによって首相はその座を追われ、契約はキャンセルになった。
こうした大きな問題を抱える鉱物資源開発を、今後再エネへの転換によってより大規模にやろうとしていることに、世界各国で厳しい視線が注がれている。





















