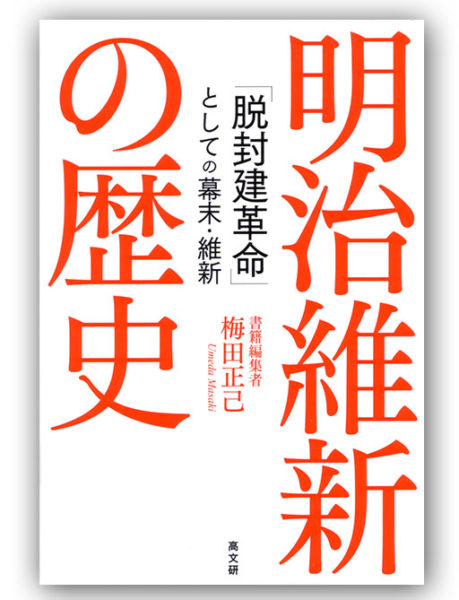
明治維新は、封建制から近代国家へと大転換させた日本史上画期的なできごとであった。しかし、世界史のうえでもフランス革命に匹敵するこの偉業についての評価は諸説入り乱れ、「国民的認識」は150年たった今も定まっていないと著者はいう。そして、その最大の理由が「マスメディアを通じて、無責任な方言、妄言が野放しで横行していることにある」と続けている。
司馬遼太郎は明治維新に献身した志士たちを「若衆組が棒を振って勇んでいる」、尊王攘夷を「外圧に対する悲鳴のようなもの」といって維新の「貧弱さ」をふりまき、ベストセラー作家となった。最近、「日本を滅ぼした吉田松陰と長州テロリスト」といって、欧米列強の植民地化に抗して幕藩体制をうち倒し四民平等の社会をめざした志士たちを醜く描いた『明治維新という過ち』(原田伊織・著)が版を重ね、講談社文庫に入ったこともその延長線上にある。
著者はこうした戯言がまかりとおるまでになった背後に、日本の歴史学界において近年、明治維新の歴史的意義が正面から論じられず、維新史研究が混沌とした状況におかれてきたことがあるとのべている。事実、明治維新史学会においても、1980年代ごろから研究が細部を深める方向に傾斜し維新を総体として深める視点が弱まったことを問題にするまでになっている。
著者は維新史を専門とする研究者ではない。しかしその分、民衆の素朴な実感をともなって、明治維新によって「人々の暮らしから社会の仕組みまでが根底から変わった」ことを、複雑に入り組んだ幕末・維新の諸事件を整理立てて描くことで浮かび上がらせている。そして、明治維新が封建制から脱却した革命であったことを明確にすることの意義を強調してやまない。
「封建制からの脱却」を口でいうのはたやすい。しかし、それがいかに重大で決定的な歴史的転換であったかについては、近年問題にされない傾向があったといえるだろう。265年間続いた徳川幕藩体制でも、270余もの小さな「くに」に分割・分権され、人口のわずか6~7%にすぎない武士階級の、さらにその最上級の特権士族たちによって世襲的に独占され「圧倒的多数の人民はただ一方的に支配される宿命」とされていた。そのような支配構造が何人も打ち破り難い壁として立ちはだかっていたのだ。
著者はそのような観点から、明治維新の全過程を2つの段階――ペリーの黒船来航から西南戦争までの「脱封建革命」と、時期的には交錯するが鳥羽伏見のたたかいから大日本帝国憲法までの「近代天皇制の成立」――に区分することを提唱している。その前半部分、つまり倒幕によって身分制を廃し、中央集権国家への政治・社会体制へと土台から変革して新しい政府を建設する過程が、本書の叙述の大部分を占めている。
最初に、「尊王攘夷」論について、国学、水戸学によってつくられた「神としての天皇観」「尊王イデオロギー」を志士たちが政治的に利用した必然性を明らかにしている。志士と呼ばれた下級・中級武士ら知識層は「封建体制を破壊して新たな近代国家の建設をめざした変革者たち」であった。彼らは「分断的・閉鎖的な国家・社会の構造を破壊して強力な中央集権制国家をつくりださない限り、欧米列強に対抗することはできない」という明確な問題意識を持っていた。そのような社会革命を達成するためのスローガンとして「尊王攘夷」が強力に作用していったのである。
明治維新による近代統一国家の建設は、そうした日本特有の歴史的な土壌のもとで神権的な天皇のもとに統合するという形態で成し遂げられていった。著者は、明治新政府がそのために、それまで人民には知られていなかった天皇の存在を周知徹底し、その権威を背景に学制発布、徴兵令、地租改正などをおし進めていったことを強調している。
当初は近代革命実現のために利用された「尊王攘夷」はその理念の制約から、新政府の元勲たちによって人民を抑圧し、排外主義を正当化するイデオロギーとして再利用されていった。そして、皇国史観のもとでの国家総動員があおられ、第二次世界大戦の深刻な結果に行き着いたのである。本書の展開から、天皇制軍国主義が国民に筆舌に尽くしがたい苦難を強いたことをもって、明治維新の革命的な意義を抹殺することはできないことを論理立てて明確にすることができる。
本書でも、幕末から明治初期にかけて百姓一揆、村方騒動、打ち壊しが続発し、それが封建社会の土台、幕府の屋台骨を揺るがし、倒幕への流れを勢いづけていったことを明らかにしている。こうしたことは、明治維新を根底において支え、推進した勢力が当時の日本の生産を担っていた農民たちであったことを示すものである。
また、長州の高杉晋作が士農工商の身分を問わぬ奇兵隊、人民諸隊を結成し、徹底して農民の側に立つ規律を徹底したことで民心に支持されたことが、民心の支持を失った幕府軍との勝敗を決定づけたことを明らかにしている。そのうえで、それとは対照的に、明治の革命のリーダーであった伊藤や山縣らが結局、国民を天皇の「臣民」とみなして侮蔑する「人民観」から抜け出せなかったことの意味を考えさせるものとなっている。
「脱封建革命」の内実は、経済的側面とくに生産様式からいえば資本制の全面的導入による産業革命であり、それは「殖産興業」を掲げた国策として急速に発展した。今日とくにコロナ禍のもとで、行き詰まった日本社会の資本主義からの脱却「ポスト・キャピタリズム」をめぐる論議が活発になっている。働く者が主人公となった社会を建設するうえで、明治維新を正当に評価し継承・発展させることが求められている。本書はそうした論議の素材となる一冊だといえる。
(発行・高文研、B6判・408ページ、2400円+税)





















